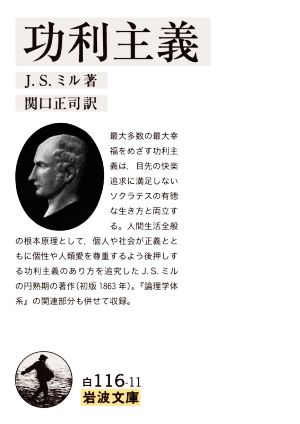
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 文庫
- 1224-14-00
功利主義 岩波文庫
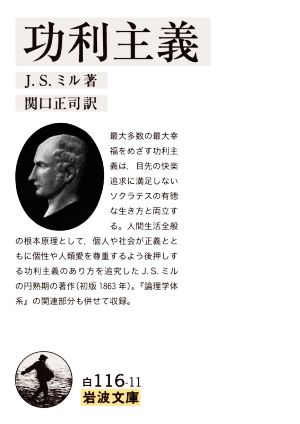
定価 ¥935
825円 定価より110円(11%)おトク
獲得ポイント7P
残り1点 ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品【送料無料】
店舗受取なら1点でも送料無料!
店着予定:1/20(火)~1/25(日)
店舗到着予定:1/20(火)~1/25(日)
店舗受取目安:1/20(火)~1/25(日)
店舗到着予定
1/20(火)~1/25

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
1/20(火)~1/25(日)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 岩波書店 |
| 発売年月日 | 2021/05/18 |
| JAN | 9784003900048 |


店舗受取サービス
対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
さらにお買い物で使えるポイントがたまる
店舗到着予定
1/20(火)~1/25(日)
- 書籍
- 文庫
功利主義
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
功利主義
¥825
残り1点
ご注文はお早めに
商品レビュー
4.3
12件のお客様レビュー
功利主義の核心として強調されるのは、「快楽にも質があり、高次の快楽を選び続けることが人間の豊かさを形づくる」という基準。満足した豚より満足していない人間を、満足した愚者より満足していないソクラテスを選ぶという比喩は、量より質を優先する姿勢を端的に示す。功利主義は「行為する前に、自...
功利主義の核心として強調されるのは、「快楽にも質があり、高次の快楽を選び続けることが人間の豊かさを形づくる」という基準。満足した豚より満足していない人間を、満足した愚者より満足していないソクラテスを選ぶという比喩は、量より質を優先する姿勢を端的に示す。功利主義は「行為する前に、自分の選択を自覚的に扱う」立場でもあり、衝動ではなく“理性的に最も良い結果を生む行動を選び取る”ことを倫理の中心に据えている
Posted by 
19世紀イギリスの哲学者ミルは功利主義を倫理学の体系に高めあげた。「満足な豚であるより、不満足な人間である方が良い。それと同じように、満足な愚者であるより、不満足なソクラテスである方が良い」という名文句が有名。
Posted by 
大学の講義の課題として選んだ。抽象的で自分としては難解な部分も多かったので、理解したとは言い難いが、功利主義の良さと、曖昧な部分を学べた。批判されていることに対する反論を述べる部分が多かったが、確かに批判していることもわかるし、反論している部分もわかる。道徳基準としては、答えを出...
大学の講義の課題として選んだ。抽象的で自分としては難解な部分も多かったので、理解したとは言い難いが、功利主義の良さと、曖昧な部分を学べた。批判されていることに対する反論を述べる部分が多かったが、確かに批判していることもわかるし、反論している部分もわかる。道徳基準としては、答えを出すということ自体難しいと再認識させられた。低級な満足と高級な満足など、面白い考え方が多くて面白かった。
Posted by 


