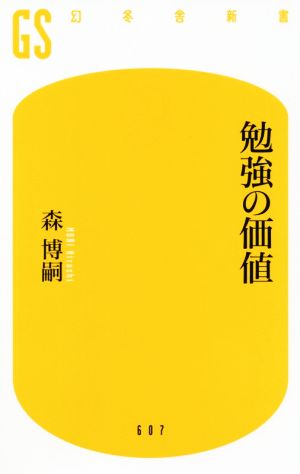
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 新書
- 1226-32-02
勉強の価値 幻冬舎新書
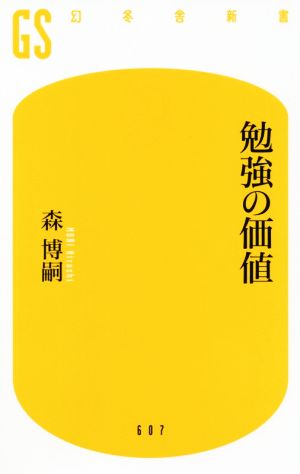
定価 ¥946
330円 定価より616円(65%)おトク
獲得ポイント3P
在庫あり
発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
2/17(月)~2/22(土)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 幻冬舎 |
| 発売年月日 | 2020/11/26 |
| JAN | 9784344986091 |


店舗受取サービス
対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
さらにお買い物で使えるポイントがたまる
店舗到着予定
2/17(月)~2/22(土)
- 書籍
- 新書
勉強の価値
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
勉強の価値
¥330
在庫あり
商品レビュー
3.8
82件のお客様レビュー
「勉強とは、釘を打つ練習である。」 だから、楽しいわけがない。 楽しくなるとしたら、それは、その練習の先に作りたいものが見えている時だ。 勉強を楽しいものに見せかける教育とは、音楽に合わせて釘を打ちましょうと言うとの同じ。 試験で競わせるのは、釘打ちコンテストをするのと同じ。 ...
「勉強とは、釘を打つ練習である。」 だから、楽しいわけがない。 楽しくなるとしたら、それは、その練習の先に作りたいものが見えている時だ。 勉強を楽しいものに見せかける教育とは、音楽に合わせて釘を打ちましょうと言うとの同じ。 試験で競わせるのは、釘打ちコンテストをするのと同じ。 どちらも本質ではない。 作りたいものが見つかるまで、釘打ち練習は楽しいわけがない。だから勉強が面白くない君は正しいと、と教えた方が良い。 なるほど。 本書冒頭のまえがき部分だけで、この切れ味である。 なにしろ局面局面での切れ味がすごい。 「『勉強が何の役に立つのか』と問われた時に僕は『あなたは何の役に立つのか?』と問うことにしている」 「義務教育において、1番大切な目標は、『自分の勉強の発見』だ、と僕は考えている。これを掴んだ子供には、もう学校の先生は必要ない。」 「早く未来の目標を決めなさい、と子供を急き立てるのは間違っている、と僕は考える。何故なら、子供はまだ広い視野を持っていない。そんな状態で、未来の可能性を限定することは、あまり得策とは言えない。」 「人の意見に反対するような場合、『あなたはこれも知らないのか?』といった物言いをする人が多い。(略)丁寧に説明し、『知った上でも意見は同じですか?』と尋ねれば済む話である。」 本書前半からいくつか、グッと来たところを抜粋した。 まことに切れ味が鋭い。 この本に問題があるとしたら、この本を読んで勉強を始める人はたぶんいないということだろう。 そういう人は多分、怒っちゃうから。 勉強してきた人は(少なくとも)そんなに腹を立てずに読めるし、共感することや、新たな気付きがあるだろう。
Posted by 
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
森博嗣さんの本は飄々としていて、凝り固まった私の考えに新しい視点を与えてくれるので最近はまっていて、気になったタイトルがあったら手に取るようにしている。 現在、試験勉強をしたり英語の勉強をしたりと、勉強を日常に組み込んでいることもあり本書を読むことに。 --- 森さんによれば、勉強の楽しさは作りたいものへ近づくプロセスが生み出している。そのため、教える側が手を差し伸べすぎると勉強はつまらなくなってしまう。 学校教育ではかられる個人の能力さの優劣は、人間の優劣ではない(森さんは学校の集団教育に懐疑的)。学校の試験において数値で測られる経験を通じて「いかに知識を蓄積するか」が勉強であると勘違いしてしまう。 ただし、学校教育に意味がないわけではない。 子供の時にイヤイヤながらも広いジャンルを勉強したからこそ大人になって選択して学べるようになることもあるためだ。 ただ、多くの人が勘違いしているのが、「学びたい」という気持ちを「教えてもらいたい」と解釈してしまうことである。 本来、創造的な体験は、自分の頭の中から湧き出るもの、極めて個人的な経験であるため、外部からは、せいぜいヒント的なものしか得られない。「教えてもらう」姿勢では主体性がなくなってしまう。 そのため、自分を自分の先生にして学ぶのが一番いいのだが、そのためにどうすればよいか。森さんは「考えることから始めましょう」と述べている。 問いを考えたら、調べたり周囲に助けを求めるのではなく、まず自分が答える。 名前という知識があっても、それがどういうものかがわからないと教養とはいえない。そういった知識の集積はコンピュータのほうがはるかに得意だし、知識を収集しても本当の勉強ではない。答えることよりも問う方がずっと難しいのだ。 「気づく」と「思う」「考える」の違いについての森さんの考えが印象的だった。 「気づき」は、ある像について「思う」ときに、予期しないところから湧き上がる別の「思い」があり、それらを関連づけることをいう。 本当の楽しさは個人的なものであり、自分一人でも楽しくて仕方がないものではないだろうか。 --- 学校教育の中でいかに高得点・好成績をとるかを意識して来た身としては、目が開くことばかりだった。 制限時間のある試験は、発想できない子どもを作るのではないか?との問いかけにドキッとしたし、「勉強する」≠「教えてもらう」については反省するしかなかった… 数学の応用問題が苦手な自分には数学の面白さが今までわからずにいたのだが、「おもしろい数学」のような本を読んだりしてわかった気になるのではなく、自分の中から湧き上がる「これがしたい」「これはなぜだろう?」という動機によって動かされないと本当の面白さは分からないんだろうなと感じた。(N=1ではあるが)研究者の考えに触れられたような気がして、やはりおもしろい読書体験だった。 試験等の目標に向かって頑張るのもいいが、それで本当に何がしたいのかを忘れないようにしたいと思ったし、心から楽しいと思える活動が見つけられれば幸せだろうなと思った。
Posted by 
かなり良かった。 「勉強は楽しくない」から始まり、「作りたいものがあって、それを実現するための勉強は楽しい」に落ち着く。 勉強というと受験のような競争が想起されるが、競争に意味はない。楽しいことが一番だし、勉強は最高に楽しい。
Posted by 


