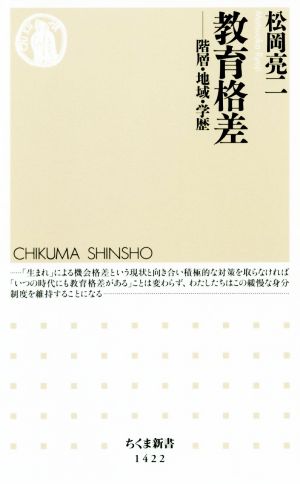
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 新書
- 1226-32-02
教育格差 階層・地域・学歴 ちくま新書
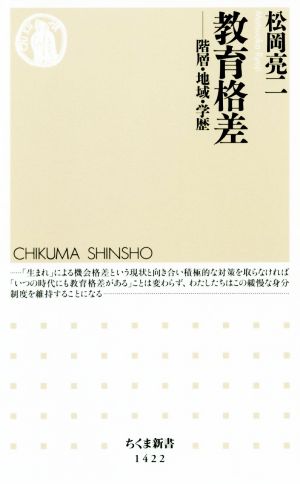
定価 ¥1,320
385円 定価より935円(70%)おトク
獲得ポイント3P
在庫あり
発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
2/22(土)~2/27(木)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 筑摩書房 |
| 発売年月日 | 2019/07/05 |
| JAN | 9784480072375 |


店舗受取サービス
対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
さらにお買い物で使えるポイントがたまる
店舗到着予定
2/22(土)~2/27(木)
- 書籍
- 新書
教育格差
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
教育格差
¥385
在庫あり
商品レビュー
3.8
66件のお客様レビュー
本質要約:文句を言うだけでは勝者になれない 5章までの事実データと解析、考察を踏まえての本質を抽象的なまとめとしたが、教育格差において、制度や政策には当然プロコンがある 敗者は「文句たれ」で勝者は「変化に(素早く)適応する者」と言うのが事実だろう 制度が悪いなどと他責でいてはい...
本質要約:文句を言うだけでは勝者になれない 5章までの事実データと解析、考察を踏まえての本質を抽象的なまとめとしたが、教育格差において、制度や政策には当然プロコンがある 敗者は「文句たれ」で勝者は「変化に(素早く)適応する者」と言うのが事実だろう 制度が悪いなどと他責でいてはいつまでも勝者に移れず、変わったルールの中で「どうすれば勝てるか」を自責で考える勝者との差は開く一方で、勝者たちは勝っている以上、サイレントマジョリティである これは、あらゆることに一定言える本質でもあるが、「教育」においてはこの「スタンスの取り方」で恩恵/損を受けるのが子どもたちであることは、最も重要で忘れてはならない部分だろう
Posted by 
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
地域による学歴格差はいつの時代もあり、世帯収入や学歴などの住民の社会経済的な格差拡大へつながり、児童・生徒の学歴達成を左右し得る教育環境の差になる。 23区で教育意識が高いのは、「大都市だから」ではなく、「近隣住民の大卒割合が高いから」である。すなわち、集合的な階層(近隣階層)によって、人々の選択、行動、意識は変わる。 どの高校に入ったかで大きく異なる高校生活を送ることになり、学校間で卒業後の進路に大きな差がある。 中流階級の親は子どもの生活に意図的な介入を行うことで望ましい行動、態度、技術などを形成しようとする「意図的教育」を行うのに対し、労働者階級・貧困家庭の親は大人の意図的な介入がなくても子どもは育つと考える「放任的養育」を行う。 親学歴は父母の学校行事・保護者活動の参加頻度と関連があり、父母の学校参加頻度の増加は児童の学校への適応化を促している。 小学校入学までの幼児教育で形成される小学校入学時点での学力が、小4時の学力と関連している。 「子どもの意志」に任せた上での大学進学率は両親大卒で65%、両親非大卒で32%と、「子どもの意志に任せる」というが、「子どもの意志」は生まれた環境によってだいぶ異なる。 「小さな学校」として子どもの自由を尊重し、部活や補修・課題を廃止すれば、公教育の枠割は縮小し、「生まれ」は今以上に直接的に引き継がれる。 多くの生徒が学習せずに時間をゲームやメディアに使うのは、他に打ち込めるものが見つからないから。
Posted by 
データが多く読みにくさがあるけど、内容はとても興味深かった。 教育格差は高校や大学など、分かりやすい学歴として可視化されるよりずっと前から存在する。生まれた時からそれぞれが生きる環境によって「ふつう」が異なり、行き着く先も異なる傾向が高い。 振り返ってみると、学生時代の私にと...
データが多く読みにくさがあるけど、内容はとても興味深かった。 教育格差は高校や大学など、分かりやすい学歴として可視化されるよりずっと前から存在する。生まれた時からそれぞれが生きる環境によって「ふつう」が異なり、行き着く先も異なる傾向が高い。 振り返ってみると、学生時代の私にとっての"社会"なんてせいぜい学校やら習い事やらの関わりにとどまるもので、もっと大きな"社会"の中で自分がどこにいるかなんて分かってなかった。 自分自身で選択できない子どもにとって、自分が見えてるものが「ふつう」でないことを認識するのは難しい。"親ガチャ"という言葉はあまり好きじゃないけど、親の収入や考え、教育方針で子供の将来が変わるのは残酷だけど否めない事実だなとデータからもよく分かった。 本著を読み、いろいろ思いを巡らせている自分は、新書を興味深く読めるくらいには教育面では恵まれた環境で育ったし、他の読者もそういった方が多いんじゃないかなと予想する。本当に苦しんでる人や届いてほしい人には届きにくくなってしまっているのも何だか皮肉のように感じる。 教員でもない、誰かの親でもない自分がこの教育格差問題に対してできることと言っても正直思いつかないけど、こういった現状があることを認識することは大切にしたい。 個人的には、「総括」の 「子供の頃に制度やルールに従うことを余儀なくされる度に、大人がしっかりと考えた相当な理由があるのだろうと違和感を飲み込んできた私が期待していたほど、頑健な合理性のあるものなどなく、恣意的に決まっていることばかりであると…」 という箇所が、自分と同じだ、、!と嬉しくなった。
Posted by 


