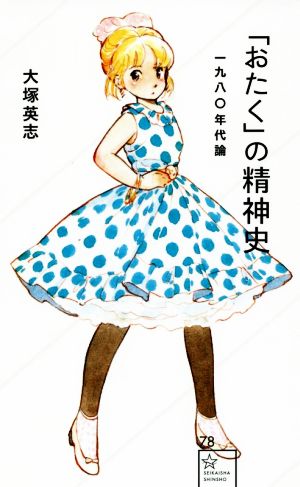- 書籍
- 新書
「おたく」の精神史
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
「おたく」の精神史
¥1,430
在庫なし
商品レビュー
5
2件のお客様レビュー
おたく オタク P.7 …〈おたく〉やその「文化」が学術的思考の対象になること自体が、「冗談」が「本気」に転倒してしまったこの三〇年間に日本で起きた、僕が近頃では「見えない文化大革命」と皮肉を込めて述懐する事態 鈴木敏夫は新左翼セクトに関わったことがある 子ども調査研究所 「...
おたく オタク P.7 …〈おたく〉やその「文化」が学術的思考の対象になること自体が、「冗談」が「本気」に転倒してしまったこの三〇年間に日本で起きた、僕が近頃では「見えない文化大革命」と皮肉を込めて述懐する事態 鈴木敏夫は新左翼セクトに関わったことがある 子ども調査研究所 「東大全共闘の関係者で大学院に戻れなかった人々が調査員を称して集まりつつ政治活動もやっていた」 渋谷陽一 橘川幸夫 村上知彦 新左翼運動とサブカル ファーストガンダム パレスチナ問題 …ガンダムという新左翼敗北文化から宮崎駿という未だ終わっていない旧左翼への「再転向」 物語消費論は単なるマーケティング理論 P.18 「労働者階級」に代わって「大学生」が日本の大衆文化の主流の消費者となっていたことに始まり、本来「教養」の担い手としてあるべきだった「大学生」が、単に文化の消費者へと変容していく中で、サブカルチャーは「労働者階級」の文化としての大衆文化ではなく、「中間層」の消費文化へと変化した。 P.63 …「新人類」が、特別な才能や実績に基くものでなく、いわば「先着順」であった 手塚治虫 漫画記号説 上野千鶴子 消費社会論 アニメージュ アニメーターに漫画を描かせる P.201 …八〇年代的な「身体」からの転向としてオウムと出産本ブームは同一の現象だった 偽史作り 風の谷のナウシカ AKIRA 栗本慎一郎 ビックリマンのマーケティング 経済人類学者 衆議院議員 斎藤純 世間話=都市伝説 P.452 まんが・アニメのキャラクターの出自が「鳥獣戯画」でも「浮世絵」でもなく、明治期に入りこんだミュシャやアール・ヌーヴォーの女性画と、一五年戦争下に流入したミッキーの書式 早坂未紀
Posted by 
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
素晴らしい本だった。いろいろな本を読んでいるが、読んでいる中でこんなにも別の世界に連れて行かれて、そして戻ってきた時には違う自分になっているある種の通過体験、そういうものをできる読書は限られている。大塚英志氏は私にとって、本を読む意味を残しておいてくれている、とてもありがたく貴重な著者なのです。 さて、帯に「私的1980年代論」とある通り、『物語消費論』や『彼女たちの連合赤軍』と違って、あるテーマを様々な角度から検証・深堀りする内容にはなっていない。扱う内容は私的で散漫に見え、「このことは以前論じたのでここでは深くは立ち入らない」みたいな頻繁に記述が出てくる。また、やや著者本人の肩入れ具合によって記述が左右しているような印象を受けていたら、あとがきに「本書は八〇年代をノスタルジックに回顧するものではない。そのように筆が走っている部分があるが、それは本書の弱点である」と書いてあって、全くその通りだと思った。しかし、私はその筆の走りも嫌いじゃないな〜と思う。その筆の走りにこそ、大塚英志氏のある種の根本が見え隠れして、私はその部分に深く共鳴するから。 氏の一連のおたく論の見取り図のような本になっており、キーワードとしての「隘路」を最も私的で瑣末なおたく文化的側面から描いている。論をさらに深く展開できる部分は、別の著作が出版されているし、文学の側面の検証の『サブカルチャー文学論』と裏表になっているような印象を受けるので、これらをまとめて読むことで、なんとなく氏の思想が浮かび上がってくるのではないかという予感が初めてした。 全体として示唆に富んでいるのだけれど、私が特に感銘を受けたのは「上野千鶴子の妹たち」だった。ここで提示されている「フェミニズムのようなもの」は他の女の人にとっても妄想かもしれないが、私の中のある種の感情を鋭く突いてきて驚いた。ここまで「フェミニズムのようなもの」についてきちんとまとまっている文章は他になかった気がするのだけれど、もしあったら教えてください。そして私は、日本のフェミニズムが今もなお、若い女の人たちの感情を掬えてないのは、この「フェミニズムのようなもの」という部分をまるっきり取りこぼしているからではないのかと思うのです。しかし、江藤淳といい大塚英志といい、男性の側からこのような女性も気づいていないある種の違和というか、女の身体と近代の問題を敏感に感じ取る言説が立ち現れるのは本当に読んでいて面白い。 そして、終章の「二〇十五年の「おたく」論 『黒子のバスケ』事件と「オタクエコシステム」における「疎外」の形式」も素晴らしかった。昨今の二次創作などにおける受け手の送り手への侵犯が、実際には収奪と隷属のエコシステムであるという論には激しく同感だった。この創作者を擬態させられた消費者のことを、なんとなく気持ち悪く思い、またそこに甘んじていたり、その文化こそが新しく・先駆的で・力があるのだという風潮に私がイマイチ乗れないのは、うっすら「こいつら搾取されているだけじゃない?しかも巧妙に自己実現しているような気分にさせられているだけで」と感じていたからなのだと気づいた。 読みながら、私が小さい頃、母親がピンクハウスのトレーナーを着ていたのを思い出した。胸のあたりにファンシーなクマのプリントがされているトレーナーで、私はそれを可愛いと思いながらも、それはあまりに少女趣味で、母親という記号との噛み合わなさに居心地の悪さをどことなく感じていたような気がする。少女でありたいと願いながら母になってしまった人間のことを思ったりなどした。そしてもちろん、黒木香は私の学校の先輩である。八〇年代は遠いように見えて、微妙に近い。
Posted by