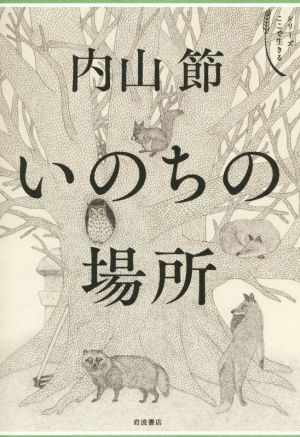
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1215-02-02
いのちの場所 シリーズ ここで生きる
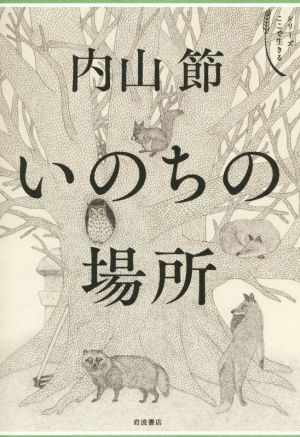
定価 ¥2,310
1,210円 定価より1,100円(47%)おトク
獲得ポイント11P
在庫わずか ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 岩波書店 |
| 発売年月日 | 2015/10/30 |
| JAN | 9784000287302 |
- 書籍
- 書籍
いのちの場所
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
いのちの場所
¥1,210
在庫わずか
ご注文はお早めに
商品レビュー
3.4
6件のお客様レビュー
(「はじめに」の部分で印象に残った箇所) 他者との関係を意識することの中に、私の「いのち」は存在している。また、人によってはその人が持っている信仰が、つまり、その信仰との関係が死の人の「いのち」を存在させることになったかもしれない。自然との関係や思い描く他者との関係、ときに神や仏...
(「はじめに」の部分で印象に残った箇所) 他者との関係を意識することの中に、私の「いのち」は存在している。また、人によってはその人が持っている信仰が、つまり、その信仰との関係が死の人の「いのち」を存在させることになったかもしれない。自然との関係や思い描く他者との関係、ときに神や仏との関係がその人の「いのち」を支え、「いのち」を与えたのである。「いのち」は自然や神仏を含む他者との関係の中に存在していた。 上野村に暮らす人々は、自分たちの命が自然、その村の共同体、その村の生業、先祖、伝統との関係のなかで存在している。そこに暮らす人々はその共同体によって自分の命の置き所や生き方死生観を諒解する。その人たちにとっては、その場所と共同体の中で生きることが、絶対的に一番よく、満足できるところである。生きることの価値は、その共同体が教えていた。そして、ありふれた普通の一生を成し遂げることが重大であった。その共同体の生き方をまもってこそ、村の人々は生を納得し、死を諒解した。 シュティルナーやヴァイとリングがみていたものは、人間のいしきは思考は決して自由なものではないということだった。資本主義や共産主義などの様々な社会的な思想やそのそのとき思想の傾向に依拠して、物事をとらえている。しかし、自分では自分で自由にものを考えていると思っている。この錯覚が社会を支えている。 同じことが「いのち」に対しても言える。誰もが「いのち」とは何かをわかっていると思っているが、実際にはその時代、その社会が概念を提供し、その概念を受け入れているだけだったりする。 そして、生の意味、死の意味も論証できることではないし論理的に説明できることではないが、その共同体の中に居たり、共同体が教えてくれたりすることで、共同体の内部にいるとそう思えてくる、ということを超えないのである。これも信じるという行為のなかで生きていることになる。 柳田國男によると、伝統社会では、生と死は親しい関係にあったと述べている。その親しさは、先祖=祖先を祀るという行為を通してくる。祀るからこそ、その祖先はこの世界に戻ってくる。ときに、子孫たちを見守っている。すなわち祀るという行為が生者の世界をつないでいる。 祀るという行為によって、死者ち生者をつないでいる。仏壇や神棚にお茶た食べ物を置いたり、声をかけたるすることも、祀る行為である。死者は消えてしまった人ではなく、関係の中に存在している。このような習慣が今も続いているということの中に、伝統社会から受け継いできたものが、今も精神の古層にも凝っていることが示されている。 つながりを成立させているものが、祀るという行為である、それは共同体が定着させた。人々の思い、願い、祈りが生み出したものである。いわば願いをとして人々は生者の世界と死者の世界を親しいものにしてきた。 「おのずから」の世界 ミラン・クンデラ「存在の耐えられない軽さ」 人間の命は誰かや何かに管理できるくらいに軽いものとして人間を扱う社会がある。
Posted by 
簡単な言葉で書かれているし、それほど分厚い本ではないのに、読み進みません。 内山さんの言いたいことを本当には分かってないんだろうなという気がしました。
Posted by 
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
生者と死者、地域の自然が一体となった関係の中にいのちが存在するという上野村の死生観を紹介し、現代の個人主義的「いのち」観を批判するという内容。 著者は死んだら終わりの現代の個人主義的「いのち」においては、自分以外のいのちは自分を満足させるためのものでしかなく、利他的行動は全て自己愛だということを言い出す(言いすぎだと思う)。共同体的「いのち」では共同体の継続が非常に重要で、共同体の中で暮らすことが自然と村民の生きる意味となり、自分と他の「いのち」の関係を尊ぶということなのだが、それも裏を返せば共同体の存続に有害なものは排斥されるのだということになってしまうのでは。共同体のような狭い閉じた人間関係は逃げ場がないから、それなりの毒を生みはぐくむものだし、エゴの部分はどうしたって出てくると思う。 「いのち」観は共同幻想(社会的現実?)であるというのも同意するし、「知性の彼方にあるもの、合理的にはとらえられないものは、『そう思う』『そう感じる』ということ抜きには語りえないのである。それはもっとはっきりした言い方をすれば、『そう信じる』ということにつながる」という箇所は好き(私はそれを非常に肯定的にとらえているのは違うけど)。 祖先から続く生者と死者の縦軸、共同体の横軸の関係の中にのみ「いのち」がある、という主張は頷けるものなんだけど、論が雑に感じたりあまりに個人主義を攻撃するので手放しには賛同できない感じ。 西洋ーキリスト教ー個人主義・孤独な「いのち」という論の組み立てをしているけど、序盤で触れているショーペンハウアーみたいに自己と他を峻別し、魂をとらえようとする姿勢ってキリスト教というよりはプラトニズムで西洋哲学の伝統では?と思う(これはほぼ他の本の受け売り)。もちろんそれがキリスト教にも反映されてはいるけど、キリスト教はどちらかと言えば関係の断絶ではなくて、聖書で「永遠のいのち」と表現されるような神と人の大きな縦軸の関係性、「ヘブライ人への手紙」で言われるように信者の「共同体」の横の関係あってのものではないか。「いのち」が孤独に堕ちていったのは死生観からその関係が引きはがされたためであって、その辺りをキリスト教は個人救済だから~と雑にするのは納得いかない。さらにユダヤ教も個人救済で個人主義の源泉というのもあまりに無理がないだろうか。そのレベルで言えば仏教だって個人救済で個人主義ということになるだろう。 「近代の思想は宗教を社会思想から外した。それはきわめて妥当なことだった」というのは、どうしてなのか。著者の好きな共同体的死生観って、かなり宗教に支えられていたと思うけど。だからこそ政治にも不可分に関わっていくわけだし。結局日本ー仏教ー共同体の「いのち」観という著者の設定したラインの擁護ありきという風に読めてしまう。本文中に和辻哲郎を引いていたが、著者も悪い意味で和辻哲郎っぽいところがある。 著者は上野村の共同体にこだわっているが、私たちはもはや自然や死者や共同体の関係から引きはがされた「いのち」観の現代に生きているのだから、自分で関係性を生み出し、座標を取らなければならない。人類にそれに耐えうる強さがないから、孤独だとか居場所のないという「いのち」観にとどまっているのが現状なのだろうけど。自分で座標を打てるのは現代の良い所ではあるから、著者が言うほど個人主義も絶望的には思わないが、家族とか友人という本書で触れられているようなものでは誰もが確かな関係性を得られないのも事実。結局もう共同の幻想はなく、戻ることもできず、どこまでも個人、どこまでも自分…でやっていくものなのだろう。
Posted by 



