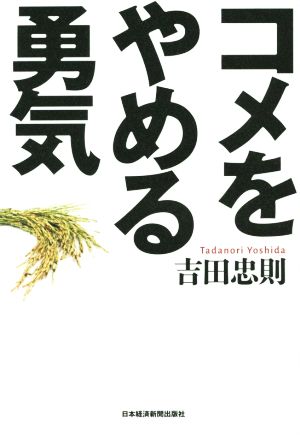
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1210-01-26
コメをやめる勇気
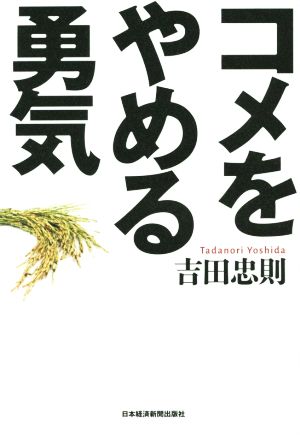
定価 ¥1,980
220円 定価より1,760円(88%)おトク
獲得ポイント2P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 日本経済新聞出版社 |
| 発売年月日 | 2015/01/01 |
| JAN | 9784532356262 |
- 書籍
- 書籍
コメをやめる勇気
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
コメをやめる勇気
¥220
在庫なし
商品レビュー
3.3
8件のお客様レビュー
「コメをやめる勇気」 吉田忠則(著) 「コメをやめる勇気」という表題が、実に曖昧なのである。誰がコメをやめるのか?コメを食べることをやめること?コメを作ることをやめること?コメに補助金を出すことをやめること?日本人がコメをやめること?そして、なぜ勇気がいるのか? 日本語は、主語が...
「コメをやめる勇気」 吉田忠則(著) 「コメをやめる勇気」という表題が、実に曖昧なのである。誰がコメをやめるのか?コメを食べることをやめること?コメを作ることをやめること?コメに補助金を出すことをやめること?日本人がコメをやめること?そして、なぜ勇気がいるのか? 日本語は、主語が不鮮明でも、言葉が成り立つので、このようなセンセーショナルな言葉も、曖昧に使うことができる。 日経新聞の経済部編集委員が書いている。農業のジャーナリストとして、書くにはあまりにもお粗末なのである。なぜなら、コメをやめるには勇気がいるそうだが、コメをやめてどうするか?は個々の事例を挙げているが、それではどうするのか?が書かれていない。多分「コメをやめる」という言葉を表題にするには、勇気がいったのだろう。「コメをやめる(ということを書くことの)勇気」かもしれない。 米の生産量が減っている。米の消費が減っている。ということは、コメをやめる勇気がなくても、コメをやめている人が増えている。コメの労働を少なくする田植え機などが開発されることによって、兼業農家というシステムができた。それがコメをつくる仕組みとして重要な役割をした。その兼業農家が高齢化して、集団離農が始まっている。つまりコメを作るシステムの崩壊である。だから、コメは勇気がなくても、コメ作り農家は消え去っているのだ。 では、何が問題なのか?「農政はまるで思考停止のように、コメにこだわり続ける。」「コメ本位主義ともいうべきモノカルチャーの農業と農村から脱皮するときが来た。」「需要が減り続ける分野に、みんなで経営資源を投入するのは合理的でない」ふーむ。「みんな」なのかよ。はっきりと農水省と言えない。 つまり、現在のコメ政策で、えさ米にバカげた補助金をつけていることをやめるべきだと書かれていない。新潟では、えさ米が、10アールに国の補助金8万円、県の補助金8万円が出され、10アールあたり16万円の補助金があるという。コシヒカリ10俵とり、1俵15000円で売ったとしても、15万円にしかならない、だったら飼料米の方がいいだろうという話だ。コシヒカリがえさ米になっている。さぞかし、牛たちは美味しいコシヒカリを食べて満足だろう。 明らかに、農水省はおバカさんな予算を組み立て、コメの値段を高くしようとしている。 農水省は、毎年コメの補助金に3000億円を使って、コメの値段をつり上げようと苦心している。 消費が減っているのは、コメが高いからだ。そういう現実にも目に向かない。越後ファームの1kg 5400円のコメを褒める。アホか?誰が食べるねん。そんな高いコメ。 農水省が、日本のコメを食べさせないようとしているし、飼料米に多大な補助金を投入して、コメの価格を吊り上げている。コメをもっと正常な形で、マーケットが決める仕組みを作らない限り、コメ産業は生き残れない。越後ファームや山形ガールズを取り上げて、お茶を濁しているが、本質に目を向けない日経ジャーナリストの限界ともいうべき記念碑的な本である。 聞くところによると農業研究者が、飼料米の補助金を研究し、批判すると研究費が減らされるという。まさに、ガースーの本領である。気に入らないものは、研究するなということだ。日本は、まともな考えで、批判する人を排除して行く社会になった。 「それでも稲作を続けますか」ではなく、「それでもバカなコメへの補助金を農水省は続けますか?」なのである。日経新聞ジャーナリストの著者は、そこまでいう勇気がないようだ。
Posted by 
コメ政策による日本農業の衰退について、非常に上手く説明されている。日本の農業政策を考える上で必読の本。
Posted by 
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
この分野の関係者でないとわかりにくいかもしれないが、マニアックかつ幅広に書かれているところがすごい。 独立系の記者みたいな感じさえする。 そして、あくまで食えるか食えないか(生計を支えるもの/経営として成り立つか)という切り口で書いているところもすごい。 兼業農家のバッファー吸収の在り方(農業リスクを会社員収入でカバー) 従業員を雇用し続けるために、収益性の薄れるコメを一部辞めてトマトハウスを作ったJAおばこ、 農産物と工業製品の契約の違い。 農業に欠けているのが、消費者の求めるものを敏感に察知するマーケティング力とできたものを効率的に消費者に届けるシステム。 農協による市場出荷は、大量の(あまり特色では差がでない)ものを安定的に捌くには効率的なシステムだった。食料不足の時には機能したが、供給過剰になると、消費者と生産者の関係を分断するという難点の方が大きくなった。 既存の農業経営にとって変わろうとするのではなく、農業を理解し、仕入れと販売の両面で競争力を高めようとする流通企業の参入。 これを読んですごく感じたのは、表面的な世間で言われることが問題なのではない。何が問題なのか、よく考えてみることだ。例えば、企業が農地の所有権を取得できないことが問題とはほとんど誰も考えていない。 「企業」ではなく「農家」に土地所有権を限定していたからと言って、農業がうまくいっていたわけではない。 ―”正しいのは、「農家はもうかりにくい」という点だけだ。赤字になれば農家も企業も撤退する。農家が赤字でも頑張れたのは、兼業というシステムがあったから。 農業界が企業による農地の取得を拒み続ける心理の背景は、「よそもの」をいやがるムラの論理。いったん、相手がまじめに農業をやることがわかれば、村の態度は一変する。農地は、どんどん集まるようになる。 昔は合理的であった制度が、今の社会条件下でも合理的であり続けるのか。北村先生が、人間ドッグならぬ法律ドッグに!と書いていたのを思い出した^^; だから制度は改正する。 農地の転用期待なんかも、昔はあったが、今はだいぶ薄れてきたのかな。 時代は刻一刻と変わっていく。その中で、以前は無理だったこともできることがあるかも知れない。 自分で、問題の構造的理解を深め、時代背景を追いたいと思うようになった。
Posted by 



