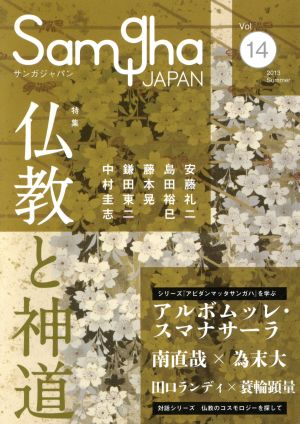
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1215-02-00
サンガジャパン(Vol.14) 特集 仏教と神道
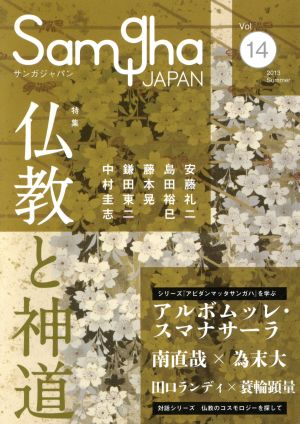
定価 ¥1,980
1,155円 定価より825円(41%)おトク
獲得ポイント10P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | サンガ |
| 発売年月日 | 2013/06/22 |
| JAN | 9784905425526 |
- 書籍
- 書籍
サンガジャパン(Vol.14)
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
サンガジャパン(Vol.14)
¥1,155
在庫なし
商品レビュー
0
1件のお客様レビュー
サンガジャパン、volume14の特集は『仏教と神道』。 伊勢神宮と出雲大社の式年遷宮に合わせてのテーマで、目下とても興味を持っているトピックのため、興味深く読みました。 さすが、仏教専門の雑誌だけあり、とても読みがいのある内容。 この雑誌で神道について詳しく語られた文章を読む...
サンガジャパン、volume14の特集は『仏教と神道』。 伊勢神宮と出雲大社の式年遷宮に合わせてのテーマで、目下とても興味を持っているトピックのため、興味深く読みました。 さすが、仏教専門の雑誌だけあり、とても読みがいのある内容。 この雑誌で神道について詳しく語られた文章を読むのは初めてです。 まず、「神道の浄め」論文で語られた、古事記のスサノヲノミコトの分析がとてもクリアで、曖昧で矛盾に満ちているように思えた神話がわかりやすく捉えられるようになりました。 これまでスサノヲは、手がつけられないあらくれ者として天界を追放されながら、ヤマタノオロチを智謀をもって退治したヒロイック性も持つ、幾通りもの側面を持つ複雑な神だと思っていましたが、そもそも彼は、死んだ醜い姿を夫に見られた母イザナミの哀しみを受けて、哀しみの子として生まれ出たとのこと。 けれど、彼はイザナギの体から生まれたため、イザナミとは血のつながりがないという不思議さが存在します。 母の哀しみを次いで、父に追放される神。 人間的というか、人間よりもはるかにスケールが大きな、情動的な面を持っています。 その粗暴さは、ヤマタノオロチを退治することで統御され、英雄的な神となったとのこと。 つまり、スサノヲに受け継がれたイザナギの怒りは、ヤマタノオロチの破壊力に比されるものだったとのこと。 ようやく彼は、出生の因縁から解き放たれたということを意味するのだそうです。 古事記は神話であり、とりとめのない、あまり根拠のないストーリーなのかと思っていましたが、そういった見方をするとイニシエーションとしての深い意図を感じます。 日本各地で盛んなスサノオ信仰。ようやく納得がいくようになりました。 また、"スサノヲの「荒魂(あらみたま)」がなければ「浄め」と「和み」をもたらす「歌」が出てこない"との記述に、歌の誕生は、清らかな心からではなく、暴力的な魂を鎮めるといった意味合いが強かったのだと気付かされました。 仏教と神道とは、日本の宗教としてほぼ同列に並ぶものだと思っていましたが、仏教が日本に伝来した時、神道はまだ神道の形を成していなかったそうです。 それどころか、神道が宗教として独立したのは戦後になってからだそう。 それまでは、自然信仰という漠然とした祈りの形式のみがあったそうで、仏教のようなシステムは成立していなかったとのこと。 お祈りの作法も寺社ともに違いはなかったようです。 「神道」という概念は、仏教が日本に伝来してきてから作られたということに思い至らなかったため、新鮮でした。 仏教を取り入れたことで、さまざまな知識も合わせて導入され、日本は周辺諸国と肩を並べる技術発展を遂げられるようになったということ。 かつては仏教は、建築学や理数学など、すべての学問と通じていたようです。 そして、日本宗教を語る上で避けては通れない、神仏習合についても詳しい考察がなされていました。 もともとの日本宗教が神仏習合だったため、伝統的な日本の文化や芸能について語るときに、神仏を完全に分けてしまうと、ほとんどのものが説明不可能になってしまいます。 現代の宗教が、説明しづらいものになっているのは、分けられた結果としての混乱がまだ続いているためではないでしょうか。 神仏習合として挙げられる修験道は、仏教よりもむしろ道教に近いものなのだとか。 いろいろな知識を取り入れていく日本では、さまざまな宗教が混ざったものが伝統的な日本宗教として成り立っているのでしょう。 八幡神も稲荷神も、それぞれに神を祀っているものと思っていましたが、八幡神は辛嶋氏の祖先神で稲荷神は秦氏の祖先神だということには驚きました。 祀られているのは、神話の神ではなかったとは。 また、仏教を導入したとはいえ、日本人は論理としてではなく身体的に理解していったという指摘も興味深く感じました。 例えば「空」がどういったものかの説明が難しいのは、日本人が「空」を教理ではなく実感的に捉えているためだとのこと。 その実感的理解が発展していき、さまざまな日本文化が生まれていったそうです。 結果として、日本に今ある宗教は、日本にしかない固有の特色を持つものになっていったのでしょう。 どの寄稿も読みがいがあり、自分がもっと知識を有していれば、さらに楽しめる内容であったことでしょう。 こうした形で仏教と神道について並び示した特集はこれまで読んだことがなかったため、より深く勉強していくにあたり、今後も何度も読み返していきたいと思います。
Posted by 



