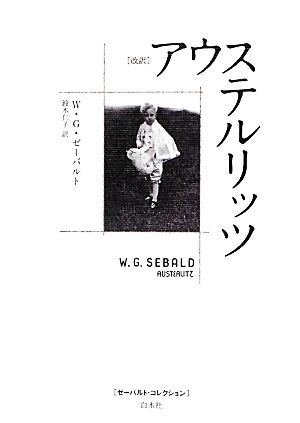
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 書籍
- 1222-01-03
改訳 アウステルリッツ ゼーバルト・コレクション
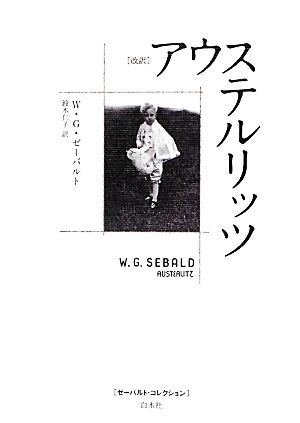
定価 ¥2,860
2,475円 定価より385円(13%)おトク
獲得ポイント22P
在庫わずか ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品【送料無料】
店舗受取なら1点でも送料無料!
店着予定:1/4(日)~1/9(金)
店舗到着予定:1/4(日)~1/9(金)
店舗受取目安:1/4(日)~1/9(金)
店舗到着予定
1/4(日)~1/9

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
1/4(日)~1/9(金)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 白水社 |
| 発売年月日 | 2012/06/25 |
| JAN | 9784560027349 |
- 書籍
- 書籍
改訳 アウステルリッツ
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
改訳 アウステルリッツ
¥2,475
在庫わずか
ご注文はお早めに
商品レビュー
4.6
13件のお客様レビュー
主人公は商用の旅で、印象的な人物に偶然出会う。 何十年か後に、その人に再び偶然出会い、交流の中で彼の物語を聞く。 アウステルリッツという彼は子供の頃牧師館に預けられ、すぐ寄宿舎のある学校へ行く。その後大学で働いて、今は早期退職している。 最初は今していること、駅や建築など関心があ...
主人公は商用の旅で、印象的な人物に偶然出会う。 何十年か後に、その人に再び偶然出会い、交流の中で彼の物語を聞く。 アウステルリッツという彼は子供の頃牧師館に預けられ、すぐ寄宿舎のある学校へ行く。その後大学で働いて、今は早期退職している。 最初は今していること、駅や建築など関心があることの話をしている。話がどこに向かうのけわからないが、その話を聞くことで読者もアウステルリッツという人物に寄り添うことになる。が、だんだん過去の話になる。 そして、牧師館の前にはどこにいたのかというルーツの話へ。 牧師館では別の名前を付けられていたが、本当はチェコにいたユダヤ人夫婦の子だということが判明。子供だけでもとイギリスに養子に出すことで逃がされたことを知り、プラハへ向かい、子供時代を知る人に再会する。 アウステルリッツの語りは彼の内面の声であり、聞き手の主人公は彼を客観視する目線となり、アウステルリッツという人と、彼を通して当時のヨーロッパの変遷が浮かび上がる。読者はアウステルリッツの目線で世界を見る。他人の目で世界を眺める、が叶う作品。
Posted by 
1960年代、ベルギー旅行中にアントワープ中央駅で出会った青年アウステルリッツと「私」は建築史を通じて親しくなり、その後もヨーロッパで何度も再会するが、75年に「私」が生まれ故郷のドイツへ帰国すると連絡が途絶えてしまった。その20年後、またも奇妙な偶然によって再会を果たすと、アウ...
1960年代、ベルギー旅行中にアントワープ中央駅で出会った青年アウステルリッツと「私」は建築史を通じて親しくなり、その後もヨーロッパで何度も再会するが、75年に「私」が生まれ故郷のドイツへ帰国すると連絡が途絶えてしまった。その20年後、またも奇妙な偶然によって再会を果たすと、アウステルリッツは自らの生い立ちと隠されたルーツを「私」に語りはじめる。育った家庭に対する違和感、寄宿学校での少年時代、過去から目を背け続けた日々、突如蘇ったプラハの記憶。「まやかしの間違った人生」を生きたのではないかと苦悩する男の目を通して、豊かなディティールと共に描かれる芳醇な悲しみの物語。 「私」が旅先で知り合ったミステリアスな年長者の生に隠された秘密を知る、という構成は、どうしても『こころ』を連想せずにいられない(解説で多和田葉子も言っている!)が、先生と違ってアウステルリッツは自死を選ばない。生死のわからない父と、かつての恋人マリーを探し求めながら生きることを選択する。読後のこの圧倒的な寂寥感たるや。 悲しみ一辺倒では勿論なく、この人特有のユーモアが本作にも全篇に渡って散りばめられている。地獄を生き生き語って町の人を震えあがらせるのが大好きな説教師だった養父のイライアスも変な人だし、そんな家に馴染めず、昔水没した村のアルバムを眺めて妄想を膨らませるアウステルリッツに、不思議な話を聞かせてくれる靴屋のイヴァンなど、バラの町での幼少期はキャラの濃い歴史小説のような趣き。 続く寄宿学校でのパートでは、『トーマの心臓』のエーリクに似た甘えん坊のジェラルドが登場。世話係の下級生だったジェラルドとその母アデラと過ごした日々は、アウステルリッツ自身が「あそこで時を止めるべきだった」と言うとおり、本作で最も多幸感に満ち満ちている。アデラが住む博物標本だらけの海辺の別荘の描写も含め、ここはきらきらした昔の少女漫画風のタッチ。そして学校卒業時から、本当の自分の名前を知ったアウステルリッツの魂の彷徨がはじまる。 たとえばこの物語をノンフィクションとして差しだされていたら、私はアウステルリッツともっと距離をとってこの小説を読んだだろう。ナチスによるユダヤ人の強制労働と虐殺というシリアスな現実を受け止めるとき、自然に心が距離を取ろうとしてしまうのは防衛本能のようなものだと思う。そんな心の壁を「フィクション」はたやすく超え、深いシンパシーにいざなってしまう。それは物語の功であり罪でもある。 本書における虚構性の取り扱いはとても繊細だ。語り手の「私」を通して、「…とアウステルリッツは語った」という一文が繰り返し挿入される。それはカギ括弧を伴わないアウステルリッツの語りが量的に「私」の地の語りを圧倒するなかで、「私」という聞き手の存在を読者に思いださせる唯一のよすがでもあるのだ。アウステルリッツが他者の言葉を引用すると、「…とヴェラは言うのでした、とアウステルリッツは語った」と間接話法の螺旋階段が発生し、のめり込んで聞いていた話が急速に「過去」という絵に収まっていくのを見ている気分になる。「私」を通すことでアウステルリッツの語りに没頭しきれず醒めてしまうとも、〈本当らしさ〉が高められているとも言える。『移民たち』と同じく、添付された写真たちも事実と虚構の境を攪拌していく。 アウステルリッツという人は、言うなれば〈忘却されたものたちの擬人化〉なのだと思う。波打つ金髪はジークフリートに喩えられ、「私」の10歳年上にも10歳年下にも見える〈暗い美青年(ボオ・テネブル)〉。戦争によって過去と現在を失った彼は、時間から追放されてしまった孤独な吸血鬼だ。彼は自分が血を吸うかわりに、人類が血を流し殺しあってきた歴史を建築に見る。石造りのヨーロッパの街に刻まれた傷跡が人のかたちをとったもの、それがアウステルリッツなのだろう。 アウステルリッツの語りは美しい。語るものことごとくが失われているがゆえの美しさである。作中、ジェラルドのおじは、私たちの胸を深く揺さぶるのは「現実に存在していない現象」であり「光の効果」だと語る。アウステルリッツの道程に美しさを見いだす我々読者は、ある意味で破滅にすら鈍感に美を求める傍観者でしかない。「左右が逆転した間違った世界」に来てしまったと悟る瀬戸際まで、まやかしを信じるしかない我々は。
Posted by 
父と母のモチーフと19世紀ヨーロッパ、アウシュビッツのすべての記憶が、目眩がするように繋がっていく、持続の最中にいるアウステルリッツを眺める私、を読み進める……
Posted by 



