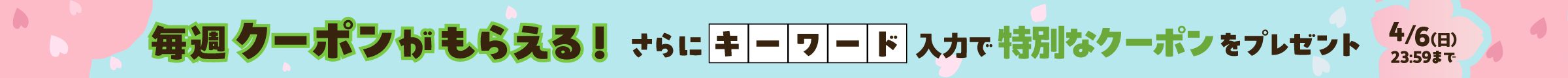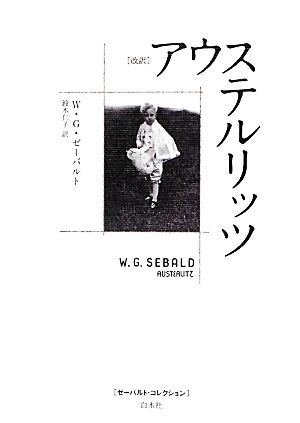改訳 アウステルリッツ の商品レビュー
主人公は商用の旅で、印象的な人物に偶然出会う。 何十年か後に、その人に再び偶然出会い、交流の中で彼の物語を聞く。 アウステルリッツという彼は子供の頃牧師館に預けられ、すぐ寄宿舎のある学校へ行く。その後大学で働いて、今は早期退職している。 最初は今していること、駅や建築など関心があ...
主人公は商用の旅で、印象的な人物に偶然出会う。 何十年か後に、その人に再び偶然出会い、交流の中で彼の物語を聞く。 アウステルリッツという彼は子供の頃牧師館に預けられ、すぐ寄宿舎のある学校へ行く。その後大学で働いて、今は早期退職している。 最初は今していること、駅や建築など関心があることの話をしている。話がどこに向かうのけわからないが、その話を聞くことで読者もアウステルリッツという人物に寄り添うことになる。が、だんだん過去の話になる。 そして、牧師館の前にはどこにいたのかというルーツの話へ。 牧師館では別の名前を付けられていたが、本当はチェコにいたユダヤ人夫婦の子だということが判明。子供だけでもとイギリスに養子に出すことで逃がされたことを知り、プラハへ向かい、子供時代を知る人に再会する。 アウステルリッツの語りは彼の内面の声であり、聞き手の主人公は彼を客観視する目線となり、アウステルリッツという人と、彼を通して当時のヨーロッパの変遷が浮かび上がる。読者はアウステルリッツの目線で世界を見る。他人の目で世界を眺める、が叶う作品。
Posted by
1960年代、ベルギー旅行中にアントワープ中央駅で出会った青年アウステルリッツと「私」は建築史を通じて親しくなり、その後もヨーロッパで何度も再会するが、75年に「私」が生まれ故郷のドイツへ帰国すると連絡が途絶えてしまった。その20年後、またも奇妙な偶然によって再会を果たすと、アウ...
1960年代、ベルギー旅行中にアントワープ中央駅で出会った青年アウステルリッツと「私」は建築史を通じて親しくなり、その後もヨーロッパで何度も再会するが、75年に「私」が生まれ故郷のドイツへ帰国すると連絡が途絶えてしまった。その20年後、またも奇妙な偶然によって再会を果たすと、アウステルリッツは自らの生い立ちと隠されたルーツを「私」に語りはじめる。育った家庭に対する違和感、寄宿学校での少年時代、過去から目を背け続けた日々、突如蘇ったプラハの記憶。「まやかしの間違った人生」を生きたのではないかと苦悩する男の目を通して、豊かなディティールと共に描かれる芳醇な悲しみの物語。 「私」が旅先で知り合ったミステリアスな年長者の生に隠された秘密を知る、という構成は、どうしても『こころ』を連想せずにいられない(解説で多和田葉子も言っている!)が、先生と違ってアウステルリッツは自死を選ばない。生死のわからない父と、かつての恋人マリーを探し求めながら生きることを選択する。読後のこの圧倒的な寂寥感たるや。 悲しみ一辺倒では勿論なく、この人特有のユーモアが本作にも全篇に渡って散りばめられている。地獄を生き生き語って町の人を震えあがらせるのが大好きな説教師だった養父のイライアスも変な人だし、そんな家に馴染めず、昔水没した村のアルバムを眺めて妄想を膨らませるアウステルリッツに、不思議な話を聞かせてくれる靴屋のイヴァンなど、バラの町での幼少期はキャラの濃い歴史小説のような趣き。 続く寄宿学校でのパートでは、『トーマの心臓』のエーリクに似た甘えん坊のジェラルドが登場。世話係の下級生だったジェラルドとその母アデラと過ごした日々は、アウステルリッツ自身が「あそこで時を止めるべきだった」と言うとおり、本作で最も多幸感に満ち満ちている。アデラが住む博物標本だらけの海辺の別荘の描写も含め、ここはきらきらした昔の少女漫画風のタッチ。そして学校卒業時から、本当の自分の名前を知ったアウステルリッツの魂の彷徨がはじまる。 たとえばこの物語をノンフィクションとして差しだされていたら、私はアウステルリッツともっと距離をとってこの小説を読んだだろう。ナチスによるユダヤ人の強制労働と虐殺というシリアスな現実を受け止めるとき、自然に心が距離を取ろうとしてしまうのは防衛本能のようなものだと思う。そんな心の壁を「フィクション」はたやすく超え、深いシンパシーにいざなってしまう。それは物語の功であり罪でもある。 本書における虚構性の取り扱いはとても繊細だ。語り手の「私」を通して、「…とアウステルリッツは語った」という一文が繰り返し挿入される。それはカギ括弧を伴わないアウステルリッツの語りが量的に「私」の地の語りを圧倒するなかで、「私」という聞き手の存在を読者に思いださせる唯一のよすがでもあるのだ。アウステルリッツが他者の言葉を引用すると、「…とヴェラは言うのでした、とアウステルリッツは語った」と間接話法の螺旋階段が発生し、のめり込んで聞いていた話が急速に「過去」という絵に収まっていくのを見ている気分になる。「私」を通すことでアウステルリッツの語りに没頭しきれず醒めてしまうとも、〈本当らしさ〉が高められているとも言える。『移民たち』と同じく、添付された写真たちも事実と虚構の境を攪拌していく。 アウステルリッツという人は、言うなれば〈忘却されたものたちの擬人化〉なのだと思う。波打つ金髪はジークフリートに喩えられ、「私」の10歳年上にも10歳年下にも見える〈暗い美青年(ボオ・テネブル)〉。戦争によって過去と現在を失った彼は、時間から追放されてしまった孤独な吸血鬼だ。彼は自分が血を吸うかわりに、人類が血を流し殺しあってきた歴史を建築に見る。石造りのヨーロッパの街に刻まれた傷跡が人のかたちをとったもの、それがアウステルリッツなのだろう。 アウステルリッツの語りは美しい。語るものことごとくが失われているがゆえの美しさである。作中、ジェラルドのおじは、私たちの胸を深く揺さぶるのは「現実に存在していない現象」であり「光の効果」だと語る。アウステルリッツの道程に美しさを見いだす我々読者は、ある意味で破滅にすら鈍感に美を求める傍観者でしかない。「左右が逆転した間違った世界」に来てしまったと悟る瀬戸際まで、まやかしを信じるしかない我々は。
Posted by
父と母のモチーフと19世紀ヨーロッパ、アウシュビッツのすべての記憶が、目眩がするように繋がっていく、持続の最中にいるアウステルリッツを眺める私、を読み進める……
Posted by
改行のない文章が綴る、渦を成す言葉の洪水は、物語の核心をはぐらかす重要な演出。一方、本編中に挿し挟まれる気がかりなモノクロ写真群は、物語の核心を遠回しに指し示す。この絶妙のバランスが印象的な小説。 特に前半、アウステルリッツの出生の謎がほのめかされるまでは、言葉の洪水は方向性を伴...
改行のない文章が綴る、渦を成す言葉の洪水は、物語の核心をはぐらかす重要な演出。一方、本編中に挿し挟まれる気がかりなモノクロ写真群は、物語の核心を遠回しに指し示す。この絶妙のバランスが印象的な小説。 特に前半、アウステルリッツの出生の謎がほのめかされるまでは、言葉の洪水は方向性を伴わず幻惑的だが、ある地点から指し示すべき方向に言葉が揃う、砂鉄のように言葉の並びに生が宿る。この小説技術は唸らされる。 ストーリー(と言える形があるのかも疑問だが)は、ドイツが第二次世界大戦で背負った宿業を巡る。しかしながら本書を読むことは、悲劇を読むという安易な行為ではなく、言葉の分厚い皮をしつこくむしり取りながら何ものかをこじ開ける、能動的な行為に近い。非常に得がたい体験。
Posted by
空間と時間、生と死を独特の見方で受け止める。生と死の垣根を取り払う視点を提示する作品としてはずせない。 作品の冒頭に、動物園の夜間獣館の動物たちの描写がある。射るようなまなざしや、アライグマがしきりに繰り返す洗う動作。不安な状況、間違った世界に置かれたものの神経症的な行動を象...
空間と時間、生と死を独特の見方で受け止める。生と死の垣根を取り払う視点を提示する作品としてはずせない。 作品の冒頭に、動物園の夜間獣館の動物たちの描写がある。射るようなまなざしや、アライグマがしきりに繰り返す洗う動作。不安な状況、間違った世界に置かれたものの神経症的な行動を象徴する出だしだ。ホロコーストについての作品だという予感がする。 アウステルリッツは、アントワープで出会った「私」にあふれるように語りだす。その話から垣間見えるアウステルリッツの時間、空間の見方が、じつに独特でおもしろい。 「時間などというものはない。あるのはたださまざまなより高い立体幾何学にもとづいて入れ子になった空間だけだ。そして、生者と死者とは、そのときどきの思いのありようにしたがって、そこを出たり入ったりできるのだ。・・・いまだ生の側にいる私たちは、死者の眼にとっては非現実的な、光と大気の加減によってたまさか見えるのみの存在なのではないか」(p.177) 時間と空間、生と死のとらえ方が独特。不幸が飽和点を超えてしまった人間が、人間的に生きるための一つの方法が入れ子空間で死者と交流することだったのではないかと思った。 アウステルリッツの専門は建築史で、「資本主義時代の建築様式」を研究しているという設定。「巨大な建造物は人間の不安の写し」という表現も示唆的だ。要塞は戦争のために先端の技術を駆使したはずなのに、実際の戦争には何の役にも立なかったことを、ベルギーのメヘレン近郊にあるブーレンドンク要塞を例に詳説する。この要塞は第二次大戦中に収容所として使用され、ジャン・アメリー*が拷問を受けた場所でもある。 * ジャン・アメリー 『さまざまな場所 死の影の都市をめぐる』 池内紀訳 法政大学出版 1983 アメリーのこの作品を思い出し、なんとなく意識しながら読み進んでいたら、いきなりアメリーの名前が出てきて驚いた。調べてみたら、ゼーバルトは『空襲と文学』でアメリー論も書いている。
Posted by
改行のない文章を読むのはこんなかんじなのか、と途中なんども果てしなく居場所を見失う。 過去の地点に遠近感がなく、50年前も昨日も同じ面の上にあり、今との距離が変わらない。時間を扱う話として、意識的にそうされているのだろう。 途中に挿入されている写真だけが、リアルに、アウステルリ...
改行のない文章を読むのはこんなかんじなのか、と途中なんども果てしなく居場所を見失う。 過去の地点に遠近感がなく、50年前も昨日も同じ面の上にあり、今との距離が変わらない。時間を扱う話として、意識的にそうされているのだろう。 途中に挿入されている写真だけが、リアルに、アウステルリッツの日常を追体験できるものになっていた。同じ世界を生きているようで同じ世界を生きていない人たち。見えているものは違うけれど、見ているものは同じなのだ。 秋の初めにこの本を読めて良かったと思った。 終わりのシーンが関節的であることに、この本らしさが詰まっている気がした。 すべて、〜とアウステルリッツは言った。とフィルターを1枚入れるスタイルで通しきったわけだし。 <読書中の連思> アブサロム、アブサロム!(過去との距離感、語り方 オレンジだけが果実じゃない(イギリスの曇ったかんじ エターナルサンシャイン(記憶との葛藤 夜と霧・ライフイズビューティフル(主題 <イメージ> 落ち葉・影・石畳・秋 <印象的な部分の引用> P12 旅をするとわかるように、空間と時間の関係には、今日にいたるまでどこか幻術めいたもの、幻覚めいたものがあります。外国から戻るたびに、自分が本当に遠くまで行ってきたのかどうか、覚束なさをぬぐい切れないのはそのためです。 P23 われわれが記憶しておけるものがいかに僅かであることか、ひとつ生命が消え去るたびにいかに多くのものが忘れ去られていくことか、それ自体は思い起こす力をもたない無数の場所と事物に付着していた種々の歴史が、誰の耳にも入らず、どんな記憶にも残されず、語り継がれてもいかないがゆえに、世界がいわば自動的に空になってしまうかを思えば、闇はいっそう濃くなるばかりだった。 P36 私は山あいの地の冬のはじまりを、森閑とした静けさを思った。そして幼いころいつも、雪がなにもかも埋めてしまえばいいのに、村じゅう、山のてっぺんまで、と思っていたこと、春になって雪が溶け、自分たちが氷の中からでてくるとしたら、それはどんな感じだろうと想像していたことが脳裡に甦ってきた。アルプスに積もる雪、吹きだまりになった寝室の窓ガラス、玄関に張り出す雪塵、電柱の○子にかぶさった白い雪帽子、ときには何ケ月も凍てついたままの水飲み場の桶 …そんなものを思い出しているうちに、いちばん好きな詩のひとつの出だしの数行が浮かんできた。<……私は雪にあこがれる ロンドンの低い丘に吹ぶく雪……>。深まっていく夕闇のなか、まぶたに外の景色が浮き上がってくるようだった。 P235〜のマリーの腕にすがって退院した時の光景が、一番身体的に読了後残った。きっとこれは秋だと思う。 感情を、嬉しいも悲しいも知らない人が、感情に押し流されそうになったとき、このわき出る方向性を持ったエネルギーは何だろうと思うのだろうな。 多和田葉子さんの解説「異文化のメランコリー」とても良かった。 言語間のほんの少しのズレで心理を表す。言語の人格。 ハワイの抽象的な形にかこまれて読んだこの本は、ヒダの多くディティールにとんでおり、その影の濃さをよりいっそう際だたせていた。
Posted by
人間らしい温かみのない養家で育った少年ダヴィーズ・イライアス。大学進学前に養父母が亡くなり、校長先生から伝えられたのが本当の名前、ジャック・アウステルリッツ。 建築史の研究者となったアウステルリッツは、ヨーロッパ各地を研究のために訪れる。 しかし…。 ずっと気づかなかった振り...
人間らしい温かみのない養家で育った少年ダヴィーズ・イライアス。大学進学前に養父母が亡くなり、校長先生から伝えられたのが本当の名前、ジャック・アウステルリッツ。 建築史の研究者となったアウステルリッツは、ヨーロッパ各地を研究のために訪れる。 しかし…。 ずっと気づかなかった振りをしていた、気づいてはいけないと思っていた自分の過去。 アウステルリッツという名前が持つ隠された意味とは。 壮年となり、ようやく自分の過去と向かい合う覚悟ができたアウステルリッツ。 ダヴィーズ・イライアスとしてイギリスのウェールズ地方の田舎で過ごす以前の自分はどこから来たのか。なぜそこに来ることになったのか。 薄々想像できるそれを、考えないようにしてきた自分を責めるアウステルリッツ。 ドイツの厳しさだなあと思う。 ナチスがやった事を忘れない。忘れてはいけない。 その姿勢を生真面目に貫き続ける。 場所を変え、時間を越えて、アウステルリッツは、自分の過去への旅を私に語り続ける。 アントワープで、ロンドンで、プラハで、テレージエンシュタットで、マリーエンバートで、ニュルンベルクで、そしてパリで。 ほぼひとつながりの文章。 本を開くと文字がみっしりと書き込まれていて、改行がない。 なめらかに語られる文章はとても美しいが、その心地よさに流されていると、いつの間にか場面が変わっていて、話に置いてきぼりにされてしまうこともしばしば。 慌てて読みなおそうにも、改行のない文章のどこまで戻ればよいのか。 そんな行きつ戻りつの読書であったが、駅舎や要塞、病院や監獄や図書館などの建物についての描写、該博な知識を越えて立ち昇ってくる都市の気配などに圧倒される。 気配のその向こうに、歴史に消えてしまった町の佇まいが透けて見えるのだ。 そして少年時代のアウステルリッツを知っていた、ヴェラとの再会。 急激に時が遡るように、次々に思い出される子供時代の思い出。 何十年も思い出さなかったのに、知っているということすら知らなかった事柄がするするとこぼれ出てくる。 ユダヤ人である彼は、彼の両親は、子どもだけでも助かるように彼を国外へ送り出したのだ。 棄てられたわけではなかった。愛されていた。 本当の自分。本来あるべき自分。失われた過去。喪失の大きさ。 どう言葉にしたらいいのかわからない。 読書というよりは映画を観ているような感じでした。 ゼーバルトの作品は、写真がさし絵のように使われていて、それが一層映画のようでした。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
1960年代の後半、ベルギー・アントワープ駅の待合室で建築史家のアウステルリッツと出会った私は、その建築や歴史への造詣の深さに強く打たれ、30年以上にわたり親交を続けることになる。その途上で、アウステルリッツの両親がユダヤ人迫害に遭い、その結果彼もまた、本名すらわからない自分の過去を探りながら、亡霊のように寄る辺ない人生を送ってきたことを知る。 切れ切れに語られるアウステルリッツの回想は、常にそこに在った建造物の記憶と、その細部にわたる構造とともに物語られる。個人の歴史(悲劇)と西洋建築(史)とがわかちがたく結びつき、それが20世紀という時代の、そしてさらにはアウシュビッツの墓標ともなっている、ヨーロッパ文学の秀作。
Posted by
自分の過去を求め、 寄る辺なくさまよう男のモノクロの記憶。 灰色の情景描写の中でフラッシュバックするかのような読書体験。 彼が、いつか心から安らげることを祈って。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
ストーリーそれ自体に、それほど重きをおいていないような「なんてことのない日常のちょっとした話」のような口調だが、ものすごく引き込まれる。 感情移入し、物語に入り込んでしまう、その一歩手前で出てくる「…とアウステルリッツは語った」の一行。 たった一行が、瞬時に現実に引き戻す。このタイミングが絶妙すぎて癖になり、逆にのめり込む。 「イキそうでイケなかった」みたいな(笑) 今更ながらこんな読書感覚が味わえるとは。 ぎっしりと改行なしで文字がつまっているので、見た目で敬遠するかも? この手法がまた、密度の濃さを出していて、感情移入と現実世界のあいだをたゆたう揺らぎをアップさせていて良いのだが。
Posted by
- 1
- 2