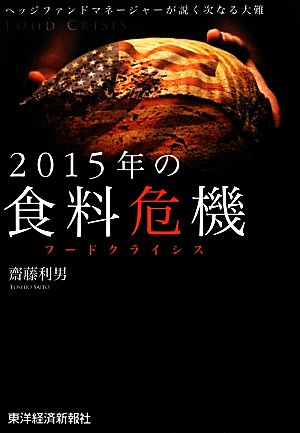
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 書籍
2015年の食料危機 フードクライシス
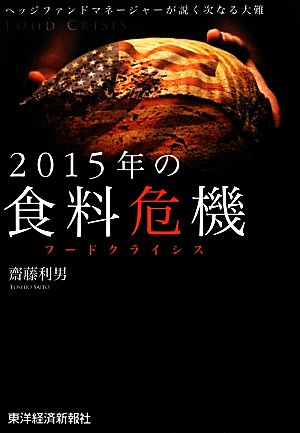
定価 ¥1,760
220円 定価より1,540円(87%)おトク
獲得ポイント2P
残り1点 ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
2/8(土)~2/13(木)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 東洋経済新報社 |
| 発売年月日 | 2012/06/11 |
| JAN | 9784492223215 |


店舗受取サービス
対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
さらにお買い物で使えるポイントがたまる
店舗到着予定
2/8(土)~2/13(木)
- 書籍
- 書籍
2015年の食料危機
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
2015年の食料危機
¥220
残り1点
ご注文はお早めに
商品レビュー
3.9
9件のお客様レビュー
FOOD CRISIS - http://store.toyokeizai.net/books/9784492223215/
Posted by 
2015年の食料危機 / 齋藤利男 / 2012.9.30(44/123) 世界支配の近道は、世界の人々の胃袋を支配すること。米国農務長官 米は日本への食料援助を通して、日本の食生活を変え、日本の農業を弱体化して、将来の米国農産物の一大輸出先にしようと計画。 GHQに...
2015年の食料危機 / 齋藤利男 / 2012.9.30(44/123) 世界支配の近道は、世界の人々の胃袋を支配すること。米国農務長官 米は日本への食料援助を通して、日本の食生活を変え、日本の農業を弱体化して、将来の米国農産物の一大輸出先にしようと計画。 GHQによって行われた農地解放も問題。持ち主がばらばらなので、大規模化、効率化が働きにくい。 農業資源:土地、水、肥料が不足しつつある。米国はほぼ限界。 牛肉1KGつくるのに、穀物が11KG必要。豚肉は7KG、鶏肉は4KG トウモロコシ由来のバイオエタノール=トウモロコシより得られるエネルギーよりも、トウモロコシを生産する為に費やされる石油などのエネルギーのほうが大きい。 農業は米国の覇権維持の手段。 映画:キングコーン 食料問題=中国最大の弱点。 穀物は投資マネーが好む投資商品:日本株式とそん色のない規模(100億ドル)、ボラが大きい、流動性がある、穀物には代替がない、金もそうだが、穀物はそれなしに生きていけない、国内消費を優先させている、輸出が小さい、 日本の債務問題の根深さ=政治家に危機感も覚悟もないために政治が財政を再建するために本当に必要な政策を打ち出すことができない。政治に対する信頼の崩壊が問題を阻む最大の要因。 対外純資産は250兆=あと5-6年で日本人だけで消化することのできるリミット(毎年40兆円の国債発行) ハイパーインフレで借金をチャラにする。 円高=海外で稼いだ金を円に変えるために生じる。 映画:フード・インク 食料危機=食料の量が確保できないのではなく、価格が高騰すること、或いは食の安全が脅かされる可能性が高い。 守護食の会
Posted by 
この本、大学生の一般教養の教科書として使うべきではないか!? 身近な食の問題(量、価格)に始まり、世界人口、アメリカの戦略、中国の躍進、日本の負債、食が投機の対象になっている世界経済と、いろいろ知ることができる。 書いているのが、経済畑の人であり、東洋経済から出版されていること...
この本、大学生の一般教養の教科書として使うべきではないか!? 身近な食の問題(量、価格)に始まり、世界人口、アメリカの戦略、中国の躍進、日本の負債、食が投機の対象になっている世界経済と、いろいろ知ることができる。 書いているのが、経済畑の人であり、東洋経済から出版されていることも信頼に足る。また、文中でのデータの出展も一般的に誰でも見ることのできるもの。 つまり、怪しげな本ではない。極めて冷静に世界を観ている本だと思う。 そして、読後は怖くなる。アメリカが世界を支配していることは周知の事実としても、いかに日本が無策でゆで蛙状態なのかがわかった。そして、近い将来の食糧危機を思うと、今なにをなすべきか考えてしまった。 なにより驚いたデータは日本のエンゲル係数が23%というもの。とても先進国だと思えない。日本人はどれだけ長時間働き、どれだけ高い食費を払っているのか。そしてその食費は世界から見れば高いという。つまり、日本の物価は世界的に見て奇妙。国のあり方(経済)が奇形なのだと思う。 筆者のTPPやACTAに対する意見も知りたくなった。
Posted by 


