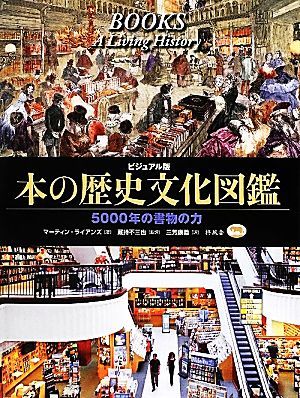
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1206-01-01
ビジュアル版 本の歴史文化図鑑 5000年の書物の力
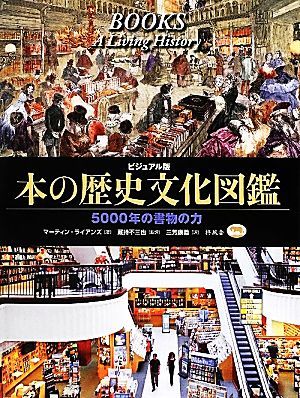
定価 ¥10,450
4,840円 定価より5,610円(53%)おトク
獲得ポイント44P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 柊風舎 |
| 発売年月日 | 2012/05/01 |
| JAN | 9784903530598 |
- 書籍
- 書籍
ビジュアル版 本の歴史文化図鑑
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
ビジュアル版 本の歴史文化図鑑
¥4,840
在庫なし
商品レビュー
5
2件のお客様レビュー
5800 19世紀に図書館が出来始めた時は利用は週に2.3時間に制限されてたらしい。今の状況に現代人が感謝しないのが有り得ない 【著者】 マーティン・ライアンズ(Martyn Lyons) 1946年ロンドン生まれ。オックスフォード大学で博士学位を取得。現在シドニーのニュー・...
5800 19世紀に図書館が出来始めた時は利用は週に2.3時間に制限されてたらしい。今の状況に現代人が感謝しないのが有り得ない 【著者】 マーティン・ライアンズ(Martyn Lyons) 1946年ロンドン生まれ。オックスフォード大学で博士学位を取得。現在シドニーのニュー・サウス・ウェールズ大学教授(歴史·哲学)。 本は電池を必要としないし、ウィルス感染もない。根っからの愛書家たちはたえずそう主張する。本を閉じてもデータを失うことはないので、「データ保存」 する必要はまったくない。書物とは、つねに便利な小道具以上のものだった。ほかの道具と比べても、書物は教育の道具であり、宗教的な霊感を与える源になり、芸術作品にもなり得るのだ。 第2の変革は、文字を声に出して読むことから黙読へのゆっくりとした移り変わりである。歴史家たちが確信しているところによれば、古代世界では訓練を受けた朗読家たちが本を声に出して読むか、聴衆に向かって朗していたという。文字を読むことはまさにひとつのパフォーマンスであった。しかし、中世ヨーロッパでは、聖職者たちが次第に黙読の訓練を信仰の形として取り入れた。 最後の変革は、電子革命である。コデックス以来、最大の変化ともいうべきこの支持されてきた素材、すなわち紙を簡単にやめることによって、本の物質的な形を変えたのである。こうした電子化による情報伝達の革命は、500年以上前に印刷術明に出会った人々と同じような反応を生じさせ、同様の恐怖心を引き起こした。 グーテンベルク〔1400頃一68〕 は1440年代に印刷術を考案したが、それは、アルキメデスが風呂に入っていたときに、突然「エウレカ(分かった、これだ)!」と叫んだような一瞬の天啓ではなく、試行錯誤を積み重ねてきた技術革新の過程の結果であった。ある印刷所の一員だったグーンベルクは、書物の高まる需要に応えて自らの印刷術を発展させ長期にわたって投資家たちに支えられてもいたのだ。 グーテンベルクとして広く知られるヨハネス・ゲンスフライシュ・ツーア・ラディン・ツム・グーテンベルクは、何ほどか謎に包まれた人物である。1430年代、彼に対して契約違反の訴訟事件が起こされたことを除いては、どのような人生を送ったかはほとんど分からない。それでも、印刷術だけは、1440年代のある時期、ドイツの都市マインツで彼が発明したことだけは確かである。たとえ彼がこの町に移り住んだ正確な時期がはっきりしなくても、である。それ以前、彼はストラスブールで10年以上印刷の仕事をしており、印刷の仕事の厳しさを主張してもいる。 そんななかにあって、公共図書館は再生を模索していた。19世紀の社会改革者たちによって業務が引き継がれるまで、過去の宝物を維持するために存在してきたこの施設は、学者や学識のある素人だけを受け入れ、利用時間も週に2、3時間に制限していた。
Posted by 
帯文:"過去から現在、そして未来へと永続する書物の力を解き明かす!" "粘土板に刻まれた文字から電子ブックまでの軌跡と社会的・時代的背景" 目次:序文 書籍の力と魔力、第1章 古代と中世の世界、第2章 新たな印刷文化、第3章 啓蒙思想と...
帯文:"過去から現在、そして未来へと永続する書物の力を解き明かす!" "粘土板に刻まれた文字から電子ブックまでの軌跡と社会的・時代的背景" 目次:序文 書籍の力と魔力、第1章 古代と中世の世界、第2章 新たな印刷文化、第3章 啓蒙思想と大衆、第4章 出版者の登場、第5章 万人のための知識、結論 書物の新時代、用語解説、参考文献、図版出典、索引、訳者あとがき
Posted by 



