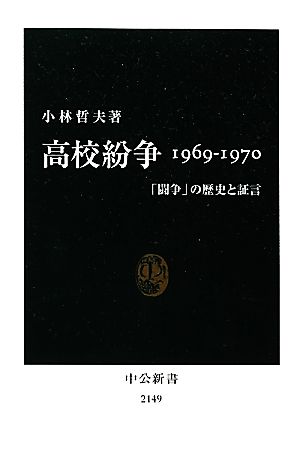
- 中古
- 書籍
- 新書
高校紛争1969-1970 「闘争」の歴史と証言 中公新書
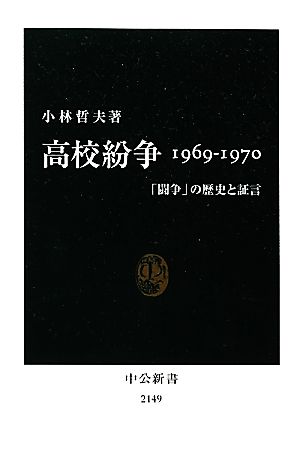
定価 ¥946
220円 定価より726円(76%)おトク
獲得ポイント2P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 中央公論新社 |
| 発売年月日 | 2012/02/25 |
| JAN | 9784121021496 |
- 書籍
- 新書
高校紛争1969-1970
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
高校紛争1969-1970
¥220
在庫なし
商品レビュー
3.5
16件のお客様レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
2012年刊。著者は教育ジャーナリスト。 過日読破した「安田講堂」や小熊英二著「1968」で叙述されるように、騒擾の時代であった1969年。それは、ベトナム戦争激化の中、世界各地での現象だが、この時代の熱量が、大学生に増して親の脛齧りでしかない日本の高校生をも突き動かしたのだろうか。 本書は、高校での学生運動に関して、当時の記録・証言録あるいは個々の学校史、学生と対決する側の教師・校長らの証言、そしてバリケードを作る側にいた学生ら(小池真理子の如き著名人や活動家のみならず、足を洗った人達を含む)の証言。これらを複合させることで、高校生による学生運動の内実とそれが残したもの、変わらなかったものを解明しようとする書である。 本筋でないが、この約20年後に私の過ごした高校・大学の雰囲気が「騒擾の時代」と隔絶していることは、経験的に首肯できる。 なのに、本作から匂い立つノスタルジー感。それは、騒擾の時代に学生が目指した学びと、自らの学びの省察とに共通項を想起させるからだ。 そもそも「学び」とは天から情報を付与してもらうものでない。教師の言を即座に鵜吞みにするのでもなく、自分の頭で汗をかき、自らの力と工夫で切り開くこと。これが「学び」だということなのだ。 しかも、これを自覚させてくれたのが、私の自己形成期に教師であった者たち。あの騒擾の時代を自ら経てきた若手・中堅教師たちなのだ。 また、本書で僅かに言及される母校の空気感が、騒擾の時代の獲得財・遺産と見得る点もノスタルジーを感じる所以かもしれない。 例えば、頭髪規制なし、制服指定なし。文化祭やクラブ活動に対する学校側の干渉の少なさ。進学指導すら干渉と捉える風潮、大学送付の調査書の記載を学生と共同作業とする点、そして一風変わった卒業式。 勿論これら全てが遺産というわけではない。が、騒擾の時代の体験から生まれ出た雰囲気の中、自らの学生時代を過ごしたことも関わっていよう。 さて、①下宿を許可なく家宅捜索する教師、②官憲・機動隊に殴られているのを笑ってみている教師、③告知・聴聞・弁明の機会を与えることなく退学などの処分に付し、あるいは一方的な誓約書を書くことを退学処分回避・撤回の条件とする教師。 高校紛争に際して見られたかような教師は、流石に現代では許容されないだろう。これも「騒擾の時代」の貴重な遺産とも読める。 ところで、大阪府立市岡(東の九段,西の市岡)、同大手前高校(羽田闘争で死亡した京大生の母校)。同清水谷、天王寺や高津、四条畷や生野といった見聞きすることの多い各高校の状況のみならず、全国の高校での高校紛争の実情が挙げられる。 その中でも、愛知県立旭丘高校と東京の私立麻布高校の例が強く印象付けられる。 また、昨今、原発問題等に関して、様々な発言をし、あるいは具体的な行動に移す著名人がいるが、彼らが高校紛争の体現者であったという事実も同様に強く印象に残る。
Posted by 
著者とほぼ同世代としてこの本に横溢するちょっと上の先輩たちに対する隠しきれないシンパシーにシンクロして一気読みしました。制服斗争(闘争じゃないんだよね…)という言葉に眩しさを感じたことを思い出します。第二次世界大戦やベトナム戦争という戦争からの距離感、新制高校という制度の歴史、そ...
著者とほぼ同世代としてこの本に横溢するちょっと上の先輩たちに対する隠しきれないシンパシーにシンクロして一気読みしました。制服斗争(闘争じゃないんだよね…)という言葉に眩しさを感じたことを思い出します。第二次世界大戦やベトナム戦争という戦争からの距離感、新制高校という制度の歴史、そして高度経済成長の実感、そういう時代的な状況と十代の多感という不変な季節が重なることで生まれた1969-1970という一瞬。大学紛争の縮小版とは違う歴史なのだと知りました。それは終戦時、アメリカに子供と言われた日本社会自身が青春に突入した瞬間なのかもしれません。
Posted by 
1960年代後半に起きた学生紛争に派生した高校紛争を多くの資料と証言から解き明かす。今では学校現場にその見る影もないが、高校生の主体性の欠如という状況を見るたび、学生紛争の時代の高校生の姿に興味がわいた。 キャリア教育の課題として、主体的に進路を見つめ、選択させるといったことが挙...
1960年代後半に起きた学生紛争に派生した高校紛争を多くの資料と証言から解き明かす。今では学校現場にその見る影もないが、高校生の主体性の欠如という状況を見るたび、学生紛争の時代の高校生の姿に興味がわいた。 キャリア教育の課題として、主体的に進路を見つめ、選択させるといったことが挙げられるが、その手段として、学生運動に従事した高校生とそれに対峙した教員たちの姿というのが参考になるのではないかと思われる。 さらに詳しい記録が待ち遠しい。
Posted by 



