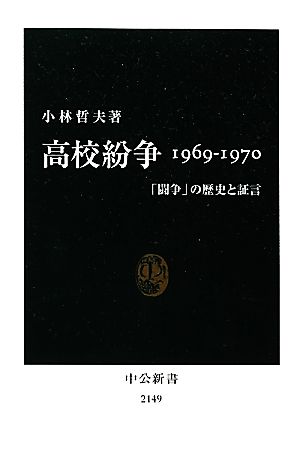高校紛争1969-1970 の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
2012年刊。著者は教育ジャーナリスト。 過日読破した「安田講堂」や小熊英二著「1968」で叙述されるように、騒擾の時代であった1969年。それは、ベトナム戦争激化の中、世界各地での現象だが、この時代の熱量が、大学生に増して親の脛齧りでしかない日本の高校生をも突き動かしたのだろうか。 本書は、高校での学生運動に関して、当時の記録・証言録あるいは個々の学校史、学生と対決する側の教師・校長らの証言、そしてバリケードを作る側にいた学生ら(小池真理子の如き著名人や活動家のみならず、足を洗った人達を含む)の証言。これらを複合させることで、高校生による学生運動の内実とそれが残したもの、変わらなかったものを解明しようとする書である。 本筋でないが、この約20年後に私の過ごした高校・大学の雰囲気が「騒擾の時代」と隔絶していることは、経験的に首肯できる。 なのに、本作から匂い立つノスタルジー感。それは、騒擾の時代に学生が目指した学びと、自らの学びの省察とに共通項を想起させるからだ。 そもそも「学び」とは天から情報を付与してもらうものでない。教師の言を即座に鵜吞みにするのでもなく、自分の頭で汗をかき、自らの力と工夫で切り開くこと。これが「学び」だということなのだ。 しかも、これを自覚させてくれたのが、私の自己形成期に教師であった者たち。あの騒擾の時代を自ら経てきた若手・中堅教師たちなのだ。 また、本書で僅かに言及される母校の空気感が、騒擾の時代の獲得財・遺産と見得る点もノスタルジーを感じる所以かもしれない。 例えば、頭髪規制なし、制服指定なし。文化祭やクラブ活動に対する学校側の干渉の少なさ。進学指導すら干渉と捉える風潮、大学送付の調査書の記載を学生と共同作業とする点、そして一風変わった卒業式。 勿論これら全てが遺産というわけではない。が、騒擾の時代の体験から生まれ出た雰囲気の中、自らの学生時代を過ごしたことも関わっていよう。 さて、①下宿を許可なく家宅捜索する教師、②官憲・機動隊に殴られているのを笑ってみている教師、③告知・聴聞・弁明の機会を与えることなく退学などの処分に付し、あるいは一方的な誓約書を書くことを退学処分回避・撤回の条件とする教師。 高校紛争に際して見られたかような教師は、流石に現代では許容されないだろう。これも「騒擾の時代」の貴重な遺産とも読める。 ところで、大阪府立市岡(東の九段,西の市岡)、同大手前高校(羽田闘争で死亡した京大生の母校)。同清水谷、天王寺や高津、四条畷や生野といった見聞きすることの多い各高校の状況のみならず、全国の高校での高校紛争の実情が挙げられる。 その中でも、愛知県立旭丘高校と東京の私立麻布高校の例が強く印象付けられる。 また、昨今、原発問題等に関して、様々な発言をし、あるいは具体的な行動に移す著名人がいるが、彼らが高校紛争の体現者であったという事実も同様に強く印象に残る。
Posted by
著者とほぼ同世代としてこの本に横溢するちょっと上の先輩たちに対する隠しきれないシンパシーにシンクロして一気読みしました。制服斗争(闘争じゃないんだよね…)という言葉に眩しさを感じたことを思い出します。第二次世界大戦やベトナム戦争という戦争からの距離感、新制高校という制度の歴史、そ...
著者とほぼ同世代としてこの本に横溢するちょっと上の先輩たちに対する隠しきれないシンパシーにシンクロして一気読みしました。制服斗争(闘争じゃないんだよね…)という言葉に眩しさを感じたことを思い出します。第二次世界大戦やベトナム戦争という戦争からの距離感、新制高校という制度の歴史、そして高度経済成長の実感、そういう時代的な状況と十代の多感という不変な季節が重なることで生まれた1969-1970という一瞬。大学紛争の縮小版とは違う歴史なのだと知りました。それは終戦時、アメリカに子供と言われた日本社会自身が青春に突入した瞬間なのかもしれません。
Posted by
1960年代後半に起きた学生紛争に派生した高校紛争を多くの資料と証言から解き明かす。今では学校現場にその見る影もないが、高校生の主体性の欠如という状況を見るたび、学生紛争の時代の高校生の姿に興味がわいた。 キャリア教育の課題として、主体的に進路を見つめ、選択させるといったことが挙...
1960年代後半に起きた学生紛争に派生した高校紛争を多くの資料と証言から解き明かす。今では学校現場にその見る影もないが、高校生の主体性の欠如という状況を見るたび、学生紛争の時代の高校生の姿に興味がわいた。 キャリア教育の課題として、主体的に進路を見つめ、選択させるといったことが挙げられるが、その手段として、学生運動に従事した高校生とそれに対峙した教員たちの姿というのが参考になるのではないかと思われる。 さらに詳しい記録が待ち遠しい。
Posted by
私は高校紛争世代の後の世代。服装の自由選択権、学内での言論の自由(検閲の拒否)、殆どの校則の撤廃、受験対策学習の廃止という遺産のおかげで、人生で最高の時間を満喫できた。歴史の記録としては内容のバランスはよいが、現在でも重要な課題として、高校生の政治活動の是非、高校の学習内容はどう...
私は高校紛争世代の後の世代。服装の自由選択権、学内での言論の自由(検閲の拒否)、殆どの校則の撤廃、受験対策学習の廃止という遺産のおかげで、人生で最高の時間を満喫できた。歴史の記録としては内容のバランスはよいが、現在でも重要な課題として、高校生の政治活動の是非、高校の学習内容はどうあるべきか、という二点については、その後の高校の歴史も踏まえて論じて欲しかった。コスタリカの教育を紹介した本「平和をつくる教育」では、お祭りノリでの小学生からの政治活動教育?が。日本はこの点では1969年から全く進歩していない。
Posted by
親世代が彼らの後輩だった世代なので、当時の空気を吸っている訳でもなく、どこか不思議な時代だったように思われるのみである。 本書を読む限り、高校紛争はやはり大学での紛争のミニチュア版であったようだ。昨今の高校の状況ならばいざ知らず、当時の高校の様子、さらに紛争が話題にのぼる前の様子...
親世代が彼らの後輩だった世代なので、当時の空気を吸っている訳でもなく、どこか不思議な時代だったように思われるのみである。 本書を読む限り、高校紛争はやはり大学での紛争のミニチュア版であったようだ。昨今の高校の状況ならばいざ知らず、当時の高校の様子、さらに紛争が話題にのぼる前の様子を知らないので、なんとも言えないが。
Posted by
高校生の学生運動について書かれた本。 村上龍や三田誠広は直撃世代で、「69」や「高校時代」はそのときの思い出をもとにした作品。 ただ暴れたいだけの高校生もいれば、受験教育に疑問を持ち人間として成長できる授業をしてほしいと要求する高校生もいるし、過激派にとりこまれている高校生も...
高校生の学生運動について書かれた本。 村上龍や三田誠広は直撃世代で、「69」や「高校時代」はそのときの思い出をもとにした作品。 ただ暴れたいだけの高校生もいれば、受験教育に疑問を持ち人間として成長できる授業をしてほしいと要求する高校生もいるし、過激派にとりこまれている高校生もいる。 学校側の対処も様々で、問答無用で退学や警察の介入をする学校がある一方で、生徒の政治活動を自主性の尊重として認める学校もある。学校側が教育の仕方を自省する機会になったこともある。 このとき運動に参加していた高校生が大人になってマルクス主義経済学の学者になっていたりして、むしろまだ卒業していなかったのかと驚く。
Posted by
赤松英一氏のお勧めで読んで見た。 1969年頃の都内の高校生活動家と紛争高校の発端から終息迄を纏めた書物。大手前高校も掲載されている。それなりに当時の高校の状況や活動家のことがわかる。しかし、当然ではあるが当時のコアは全共闘運動と新左翼諸セクトの動向であり、高校紛争はそのミニチ...
赤松英一氏のお勧めで読んで見た。 1969年頃の都内の高校生活動家と紛争高校の発端から終息迄を纏めた書物。大手前高校も掲載されている。それなりに当時の高校の状況や活動家のことがわかる。しかし、当然ではあるが当時のコアは全共闘運動と新左翼諸セクトの動向であり、高校紛争はそのミニチュア版にしか過ぎない為、隔靴掻痒の感有り。記録としてもソコソコである。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
小林哲夫『高校紛争 1969-1970 「闘争」の歴史と証言』中公新書、読了。歴史の影に隠れがちな高校生たちの闘争に光を当てる一冊。詳しくは本書に譲りますが、何らかの党派的指導で拡散・動員されたことに驚いた。自分で考え行動した足跡を丹念に取材した本書は「時代の記録」といえよう。
Posted by
「高校生は政治活動をしてはいけません」。本書を読むまでそんな 文部省通達があったことさえ知らぬ世代である。 制服の廃止、生徒心得の廃止、受験対策授業への反発。そして 巷に蔓延していた政治的関心の大きさは、高校生にも波及した。 しかし、高校紛争は大学紛争のように長期化しなかった...
「高校生は政治活動をしてはいけません」。本書を読むまでそんな 文部省通達があったことさえ知らぬ世代である。 制服の廃止、生徒心得の廃止、受験対策授業への反発。そして 巷に蔓延していた政治的関心の大きさは、高校生にも波及した。 しかし、高校紛争は大学紛争のように長期化しなかった。何故か。 活動に熱心だった学年が卒業することで終焉に向かった学校も あった。機動隊の導入という実力行使で鎮静化された学校も あった。 また、過激化する活動や大学生同様の内ゲバの発生で一般生徒の 共感を得られなかった学校もあった。 それが高校紛争が歴史の影になってしまった要因なのだろう。 本書はそんな埋もれた歴史を、当時の関係者への聞き取りや 各高校の学校史、多くの資料に当たって掘り起こした良書だ。 当時を知らぬ者から見れば、紛争が頻発していたのはエリート校に 多いので「頭でっかちがお祭りごっこをしていただけではないのか」 との感想を抱いてしまう。 実際、「バリケードを築いたりするのが楽しかった」との回想もある。 そして彼らが無意識のうちに持っていたであろう特権意識と、実業 高校を見下したような思想には嫌悪感さえ与える。 同じ時期、日本返還前の沖縄の高校でも紛争があった。だが、それは 「当事者」としての紛争であり、本土の高校生が熱病に罹患したように 反戦や安保のデモに参加したことは趣を異にしている。 以前、東大安田講堂に立て籠もって機動隊と対峙した当事者の 回顧録を読んだ。その時、「これは「戦争ごっこ」をしていたことを 美化していないか?」と思った。 大学生が「戦争ごっこ」なら、高校生は「お祭り気分」だったのだの だろうか。 自治を求めて学校側に要求を突きつける気持ちは分かる。実際、 私も高校時代に同じような要求を掲げたことがあった。だが、それが ゲバ棒・ヘルメットで武装し、火炎瓶や石を機動隊に投げつけると なると話は違う。 「反戦」を叫んでデモをする一方で、武装闘争する矛盾に気付く ことはなかったのか。機動隊は権力の象徴かもしれないが、 隊員ひとりひとりは誰かの子であり、被搾取階級の出身なのだ。 さて、高校紛争は学校教育に一石を投じられたのか。結果は 「何も変わらない」ではなかったのだろうか。
Posted by
大学紛争の激しかった69-70年に、高校でも紛争があった。首都圏や大都市の高校に多かったが、北海道から当時占領下にあった沖縄まで、ほぼ全国的に紛争はあった。日本の大学入学事情に詳しい著者が、全国の高校百年史などを丹念にあたり、まとめた。 大学紛争についての本は多いが、高校紛争につ...
大学紛争の激しかった69-70年に、高校でも紛争があった。首都圏や大都市の高校に多かったが、北海道から当時占領下にあった沖縄まで、ほぼ全国的に紛争はあった。日本の大学入学事情に詳しい著者が、全国の高校百年史などを丹念にあたり、まとめた。 大学紛争についての本は多いが、高校紛争についてまとめて書かれた本は少ないのでは。 自分の出た都立高校でも、高校紛争があったという話は、当時を知っている教師から聞いたことはあったが、この本の中に自分の出身校の名を見つけた時、その教師の事を思い出した。当時の高校生が、勝ち取った制服の自由化などは、昨今の制服ブームでなくなりつつある。制服が無いことが魅力の一つと感じていた私としては、残念な風潮です。
Posted by
- 1
- 2