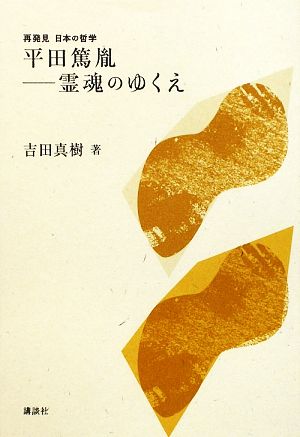
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1215-02-04
平田篤胤 霊魂のゆくえ 再発見 日本の哲学
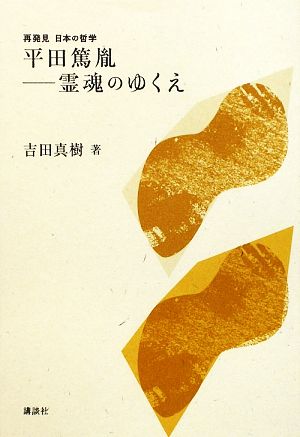
定価 ¥1,650
990円 定価より660円(40%)おトク
獲得ポイント9P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 講談社 |
| 発売年月日 | 2009/01/29 |
| JAN | 9784062787581 |
- 書籍
- 書籍
平田篤胤
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
平田篤胤
¥990
在庫なし
商品レビュー
5
2件のお客様レビュー
[ 内容 ] 篤胤において死の問題は、死後の存在としての霊魂の問題となり、さらには霊魂の行き場所の問題となる。 もし人が死後に霊魂となることが確実であり、霊魂の行き着く場所が特定されるのであれば、先に現在の私たちに即して述べたような死の問題は、「解決」されるに違いない。 篤胤はま...
[ 内容 ] 篤胤において死の問題は、死後の存在としての霊魂の問題となり、さらには霊魂の行き場所の問題となる。 もし人が死後に霊魂となることが確実であり、霊魂の行き着く場所が特定されるのであれば、先に現在の私たちに即して述べたような死の問題は、「解決」されるに違いない。 篤胤はまさにそのことを『霊の真柱』において試み、「幽冥界」という観念を提示することになる。 [ 目次 ] 第1章 篤胤の抱えた問い―自己 第2章 神へ―問いの具体化 第3章 『新鬼神論』―死んだら霊魂となる 第4章 近世庶民仏教と『出定笑語』 第5章 『霊の真柱』―霊魂のゆくえ 終章 近代へ [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
Posted by 
現在、平田篤胤の著書の中でもっとも目に触れやすい書物と言えば「霊能真柱(=霊の真柱)」でしょう。本書はこの書物を中心に、篤胤の「霊魂論」へと至る思考プロセスを描きだしています。 著者はまず、篤胤の成育歴に注目します。なぞの多い彼の前半生を、本人の書簡などわずかな手掛かりを元に推測...
現在、平田篤胤の著書の中でもっとも目に触れやすい書物と言えば「霊能真柱(=霊の真柱)」でしょう。本書はこの書物を中心に、篤胤の「霊魂論」へと至る思考プロセスを描きだしています。 著者はまず、篤胤の成育歴に注目します。なぞの多い彼の前半生を、本人の書簡などわずかな手掛かりを元に推測し、篤胤のとても辛く苦しかった幼年・少年時代の様子を浮かび上がらせます。篤胤が親や養子先から受けたのは虐待というほかない仕打ちであり、その中で彼は、「自分はなぜ生まれ、生きているのか」という根源的な問いを抱くに至ります。篤胤の形成する「霊魂論」は、人間の存在そのものを問う、高度に形而上学的な背景を持っている。その一方で、それはどこまでも自己の根底から生ずるものであり、哲学的なバックボーンとは裏腹な、具象に徹した論理構築を貫かざるをえない。そう考えると、なぜあの「霊の真柱」に書かれた魂の行方に「みずみずしさ」が備わっているように感じられたのか、その理由が分かるような気がします。と同時に、かの書物への私の読み込みの浅かったことを、思い知らされるようでした。 宣長の著作との運命的な出会いから、「呵妄書」「新鬼神論」をへて「霊の真柱」に至る道を、篤胤の思想は、自己への存在論的な問いに突き動かされるように進んでいきます。復古神道の大成者として、尊王攘夷の思想的支柱として、そしてまた戦前日本の政治的思想の源流として、描写されることの多い篤胤。しかし本書から明らかになるのは、自身の、そしてすべての人間の魂は産霊神(むすひのかみ)から分与されたものであり絶対的な尊厳を有すると考えた、真摯な思想家の姿です。それは「われらは何処より来りて、何処に在りて、何処へ行くや」という、まるでゴーギャンの絵の題名のような大きすぎる問いにさいなまれ続ける中で、何度か彼に訪れた「神に導かれる」体験からの、当然の帰結と見ることができるでしょう。 それにしても、その篤胤でさえも、「霊のゆくへの安定(しずまり)」を完全に突き止めえなかったという事実は、この命題がどれほど底の知れぬものであるかを私たちに教えてくれます。そして、篤胤が仏教思想を苛烈に排除しようとした姿勢の根底にあったものが、彼の抱えた「業」であったというのは、なんとも皮肉な話です。このことは、神道史上もっとも長い間支配的であった「神仏習合」が、どれほど重要な現象であったかを示すと同時に、これから神道が進むべき道を暗示しているようにも思われるのです。 (2009年3月入手・6月読了)
Posted by 



