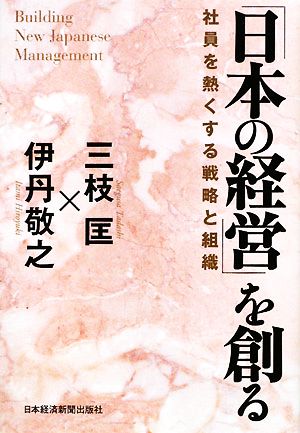
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 書籍
「日本の経営」を創る 社員を熱くする戦略と組織
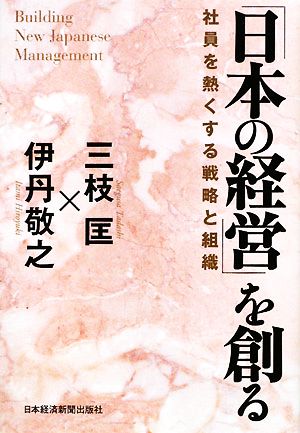
定価 ¥2,090
220円 定価より1,870円(89%)おトク
獲得ポイント2P
在庫わずか ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
11/26(火)~12/1(日)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 日本経済新聞出版社 |
| 発売年月日 | 2008/11/22 |
| JAN | 9784532314224 |


店舗受取サービス
対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
さらにお買い物で使えるポイントがたまる
店舗到着予定
11/26(火)~12/1(日)
- 書籍
- 書籍
「日本の経営」を創る
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
お客様宅への発送や電話でのお取り置き・お取り寄せは行っておりません
「日本の経営」を創る
¥220
在庫わずか
ご注文はお早めに
商品レビュー
4.3
32件のお客様レビュー
ー ここから先は少し抽象的な話になりますが、企業をモノとして見る見方と、企業をヒトとして見る見方のトータルピクチャー、トータルバランスの論理というのがキーポイントだと私は思います。会社法の論理というのは、基本的に企業をモノ、財産の固まりとして見ています。財産の処分権を誰が持つかと...
ー ここから先は少し抽象的な話になりますが、企業をモノとして見る見方と、企業をヒトとして見る見方のトータルピクチャー、トータルバランスの論理というのがキーポイントだと私は思います。会社法の論理というのは、基本的に企業をモノ、財産の固まりとして見ています。財産の処分権を誰が持つかという議論をしているのが会社法なんです。ですから、基本的に財産の処分権を株主というエクイティーを出した人が持って、議決権はこういうルールで決めますよというふうにできています。これはもう単純に処分の論理ですから、突き詰めていくと、金をもっとよこせというスタンスに必ず行くんですよ。 一方、企業をヒトとして見ると、人が働いて、人が学習をして、人が蓄積をして、さらに発展するための努力をこの人たちがしますという見方になります。そういう組織体として、継続的に存在し続けるために、どんなことが必要かを経営者は考えます。ここには処分の論理、モノの論理はまったくないんです。しかし、両方の論理が存在しないと、企業という実体は存在し得ないんです。間違いなく財産の固まりという側面もあるわけですから。その折衷なんですね。私もいつも困っているんです。 ー 三枝匡さんと伊丹敬之さんの対談。 12年以上前の作品だけど本質的な議論なので古く感じなくて面白い。
Posted by 
2020年4月再読 バブル崩壊以降、日本の経済の、従って、日本企業の世界の中でのプレゼンスは低下の一途である。国全体の生産性の相対的な位置づけが、どんどん下がっている。 それは、日本の企業がグローバルな競争に勝てていないということでもある。 ただ、だからと言って、アメリカ企業の...
2020年4月再読 バブル崩壊以降、日本の経済の、従って、日本企業の世界の中でのプレゼンスは低下の一途である。国全体の生産性の相対的な位置づけが、どんどん下がっている。 それは、日本の企業がグローバルな競争に勝てていないということでもある。 ただ、だからと言って、アメリカ企業のマネをすれば良いというものではなく、日本企業は日本企業なりの経営のあり方を確立すべき、という内容の対談をベースとした本。 とても示唆に富む。
Posted by 
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
アメリカの鉄鋼業界が弱体化したのは、日米貿易協定が原因 ・日本の鉄鋼製品の価格が米国内で高く維持され、米国鉄鋼業界の危機感が下がった ・すると、投資をやめて設備更新を遅らせたため、設備老朽化によりコスト高が進む悪循環 ・R&Dにも投資せず、新分野にも出遅れ アメリカ流経営の弱味 ①安易な多角化 ②高すぎる配当性向 ③短期リターン志向 ④組織の非連続性 ⑤品質より目先の利益追求 ⑥ものづくりの弱さ ⑦インスタント成金主義 ⑧社員の低コミットメント ・日本は所属、アメリカは参加 ⑨所得配分の過度の偏り 日本的経営劣化 Ⅰ.年齢構成 ・管理職比率が高まった ・人口変化に合わせて人事のやり方を変えられなかった Ⅱ.潤沢なキャッシュによる驕り高ぶり ・使い道がわからず、シナジーのない多角化 Ⅲ.経営者人材の枯渇 ・成長した企業では、ある世代の経験が、前の世代より劣る構造 ・優秀な人を選別して育成できない人事制度 ・優秀なひとは転職する風潮の高まり 優れた日系企業では、年功序列の形のなかで、若い実力者にどうやって実質的な権限を渡すかという隠れた努力をしてきた。 いまも昔も、共同体としての職場社会の人間的安定と、経済的に合理性の高い意思決定を行う仕組みの両立が課題。 大きくなりすぎた組織は、適切なサイズまで分けることで事業活性を高める。分けられた組織を戦略的に俯瞰し、競争原理を働かせたり、潰すところは潰すことが重要。効率がある程度落ちても、そこにいる人間が面白いと感じて頑張るエネルギーの方が大事だと割りきる。 改革の疲れを乗り切るために、アーリーウィンを意図して計画に入れ込んでおく。アーリーウィンについてもメンバーに共有しておく。
Posted by 


