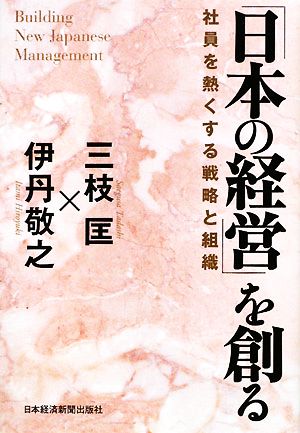- 書籍
- 書籍
「日本の経営」を創る
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
「日本の経営」を創る
¥2,090
在庫あり
商品レビュー
4.3
33件のお客様レビュー
ミスミグループ本社の会長兼CEOとして、同社の業績を大きく伸ばしたことで知られる三枝氏だが、『ザ・会社改造』の本が面白かったので、同氏の本をもっと読みたいと思って手に取った本。対話相手の伊丹敬之氏は、経営戦略論や組織論などを武器とした学者である。この二人が、日本的経営や米国型経営...
ミスミグループ本社の会長兼CEOとして、同社の業績を大きく伸ばしたことで知られる三枝氏だが、『ザ・会社改造』の本が面白かったので、同氏の本をもっと読みたいと思って手に取った本。対話相手の伊丹敬之氏は、経営戦略論や組織論などを武器とした学者である。この二人が、日本的経営や米国型経営を分析しながら、「日本流経営」において必要な戦略と組織論について会話した内容。これは面白そうだ、という感じだったのだが、2008年のもので、古くて既知の内容も多かったのが少し残念。 ー 日本の輸出脅威を防ぐための日米貿易協定が、アメリカ企業を弱くしているという結論に至ったんです。その理由が面白かった。貿易協定が結ばれて、日本の鉄鋼製品の価格がアメリカ国内で人為的に高く維持される構造になった途端に、アメリカの鉄鋼会社は安心してしまい、投資をやめて設備更新を遅らせていると。そのため生産設備の老化がさらに進み、コスト高のためにさらに競争力を失う、という悪循環になっているというのです。R&D(研究開発)にもお金を使わず、日本の鉄鋼メーカーのように薄い自動車用鋼板を開発するといったことでは出遅れ、結局、自分の国の産業を守ろうとした政治的協定が、実は米国の産業を弱めているという結論でした。 この辺の分析は、自国の産業保護が却って国際競争力を失するというありがちな内容。だからといって、野放図に競争下に晒すのが良いとも思わない。こうした分析は結果論では言えるのだが、やはり「適正な保護とは何か」が論じられないと意味をなさないような気もする。日本の自動車産業は戦後の基幹産業としての保護政策もあって競争力を獲得してきたのだから。 ー 何らかの理由で業績が落ち込んだ組織体が健康を回復するメカニズムにはどのようなものがあるのか。そうした極めて基本的な問題が、ハーシュマンという経済学者が一九七〇年に出した本での問いの中核であった。組織体とは、企業でもいいし、政府でもいいし、あるいは国家でもいい。彼は、それを「退出」と「告発」という二つのメカニズムのミックスとしてとらえようとする。 本書でも紹介されるハーシュマンだが、至近の日本ではようやく、こうした観点での流動性が上がってきたと感じる。弱い企業や従業員は退出する事で、より強い企業に飲み込まれ、次第に社会は強化されていく。告発も同様に、企業不正を明かすことで体質改善が図られていくのである。日本の企業はお互いに甘かった。だからと言って、海外企業に負けないようにしなければならない。そのために、何ができるかが、「日本の経営」に問われることで、古い本とは書いたが、今でも現役の課題である。共感できる内容だった。
Posted by 
ー ここから先は少し抽象的な話になりますが、企業をモノとして見る見方と、企業をヒトとして見る見方のトータルピクチャー、トータルバランスの論理というのがキーポイントだと私は思います。会社法の論理というのは、基本的に企業をモノ、財産の固まりとして見ています。財産の処分権を誰が持つかと...
ー ここから先は少し抽象的な話になりますが、企業をモノとして見る見方と、企業をヒトとして見る見方のトータルピクチャー、トータルバランスの論理というのがキーポイントだと私は思います。会社法の論理というのは、基本的に企業をモノ、財産の固まりとして見ています。財産の処分権を誰が持つかという議論をしているのが会社法なんです。ですから、基本的に財産の処分権を株主というエクイティーを出した人が持って、議決権はこういうルールで決めますよというふうにできています。これはもう単純に処分の論理ですから、突き詰めていくと、金をもっとよこせというスタンスに必ず行くんですよ。 一方、企業をヒトとして見ると、人が働いて、人が学習をして、人が蓄積をして、さらに発展するための努力をこの人たちがしますという見方になります。そういう組織体として、継続的に存在し続けるために、どんなことが必要かを経営者は考えます。ここには処分の論理、モノの論理はまったくないんです。しかし、両方の論理が存在しないと、企業という実体は存在し得ないんです。間違いなく財産の固まりという側面もあるわけですから。その折衷なんですね。私もいつも困っているんです。 ー 三枝匡さんと伊丹敬之さんの対談。 12年以上前の作品だけど本質的な議論なので古く感じなくて面白い。
Posted by 
2020年4月再読 バブル崩壊以降、日本の経済の、従って、日本企業の世界の中でのプレゼンスは低下の一途である。国全体の生産性の相対的な位置づけが、どんどん下がっている。 それは、日本の企業がグローバルな競争に勝てていないということでもある。 ただ、だからと言って、アメリカ企業の...
2020年4月再読 バブル崩壊以降、日本の経済の、従って、日本企業の世界の中でのプレゼンスは低下の一途である。国全体の生産性の相対的な位置づけが、どんどん下がっている。 それは、日本の企業がグローバルな競争に勝てていないということでもある。 ただ、だからと言って、アメリカ企業のマネをすれば良いというものではなく、日本企業は日本企業なりの経営のあり方を確立すべき、という内容の対談をベースとした本。 とても示唆に富む。
Posted by