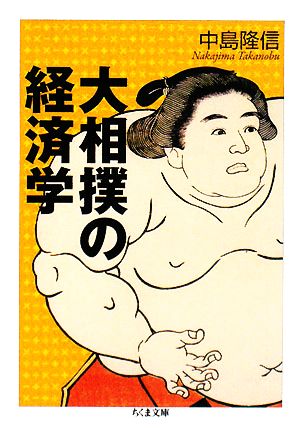
- 中古
- 書籍
- 文庫
- 1224-10-12
大相撲の経済学 ちくま文庫
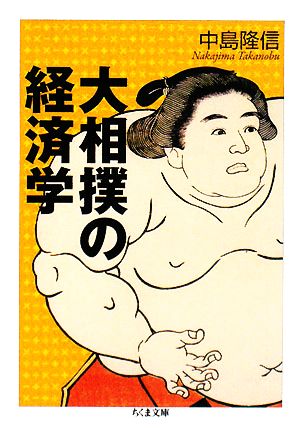
定価 ¥748
220円 定価より528円(70%)おトク
獲得ポイント2P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 筑摩書房 |
| 発売年月日 | 2008/03/12 |
| JAN | 9784480424280 |
- 書籍
- 文庫
大相撲の経済学
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
大相撲の経済学
¥220
在庫なし
商品レビュー
3.9
9件のお客様レビュー
大相撲という特殊な世界を経済学の観点から理解することを試みようという一冊。 年寄株、部屋、番付、横綱審議委員会…等々、一般人にはなかなか理解しづらい相撲界の特殊な仕組みを経済学の概念を用いて読み解くとともに、そういった独特の仕組みの中で個々の力士や親方はどのような行動をとることに...
大相撲という特殊な世界を経済学の観点から理解することを試みようという一冊。 年寄株、部屋、番付、横綱審議委員会…等々、一般人にはなかなか理解しづらい相撲界の特殊な仕組みを経済学の概念を用いて読み解くとともに、そういった独特の仕組みの中で個々の力士や親方はどのような行動をとることに合理性があるのか、またそれゆえにどのような問題が起こり、どのような対応策が採られているのか、について論じられています。 もともとは2003年に単行本として発刊された本で、今回、朝青龍問題や時津風部屋問題などの直近の話題を捕捉した最終章を追加して新たに文庫化されたもの。 個人的に経済学の観点で様々なものを見てみるということが大好きで、しかも、なぜか幼稚園児の頃から相撲に興味を持ち、元理事長の北の湖が全盛期だった頃から相撲を見続けてきた者としては、非常に興味深く読むことができました。 年寄株についてなど、これまで通り一遍の知識しかなかった話題についても理解を深めることができたし、特に一代年寄にはその栄誉と裏腹にデメリットも少なくないということを知ることができたのはなかなか新鮮でした。 昨今様々な問題が噴出する相撲界に対して、その閉鎖性を批判する論調が高まりを見せています。 著者は相撲界という閉鎖社会が世の中の変化についていけずに綻びを見せ始めていることを認めた上で、大相撲が純粋な「スポーツ」ではなく古来の「伝統」を継承するという目的をもっていることを重視する立場をとっています。 すなわち、単にグローバル・スタンダードの観点で相撲界に批判を加えるだけでは、伝統の継承という相撲界の存在意義を無視することになってしまう、という意見です。 例えば八百長問題にしても、それをモラルの低下として単純に批判・断罪するだけでは解決に近づくことはない。 実際に八百長が行われているか否かとは切り離して、力士が八百長を行うことへのインセンティブは昔から存在しており、また、純粋な「スポーツ」ではない大相撲においては八百長が「伝統の継承」という組織目標の観点からは合理的となるケースもありうるという構造を理解する必要がある、といったことです(だからといって著者が八百長を肯定しているというわけではありません)。 相撲界のような特殊世界が、どこまで一般社会の常識を取り入れるか、どこまでその特殊性を維持するか、その線引きは非常に難しい問題ですが、マスコミの浅薄なバッシングに踊らされずに、変えるべきところは変え、変えるべきでないところは変えないという見極めを心がけながら眺めてみようという気になりました。 著者には、本書の他「お寺の経済学」「障害者の経済学」「オバサンの経済学」といった一連の著作もあるようなので機会があればぜひ読んでみたいと思います。
Posted by 
力士の給与体系、相撲部屋の収支、チケットの販売制度など相撲の仕組みそのものを丁寧に説き明かしてゆく良著。経済学の知識がなくても十分読める。 どの章をとっても読みごたえ十分なんだが、ワタシにいちばんヒットしたのは『第6章 いわゆる「八百長」について』と『第11章 角界の構造改革』。...
力士の給与体系、相撲部屋の収支、チケットの販売制度など相撲の仕組みそのものを丁寧に説き明かしてゆく良著。経済学の知識がなくても十分読める。 どの章をとっても読みごたえ十分なんだが、ワタシにいちばんヒットしたのは『第6章 いわゆる「八百長」について』と『第11章 角界の構造改革』。なぜならば、そこには「相撲」と「八百長」に関するワタシの考えとほぼ同じことが書かれていたから。 かつて、村松友視がプロレスを「他に比類なきジャンル」と称したが、ワタシは相撲もこれにあたると思っている。つまり、相撲はスポーツではない。スポーツでないのだから、そもそも「八百長」の有無について騒ぐのはほとんど意味がない。著者も「相撲はスポーツか?」という見出しをたてて論じている通り、相撲をスポーツと見立ててその競技性を高めていったらどうなるかということを考えると、相撲の本質が見えてくる。 「大相撲の強みは文化性であって競技性ではない。」と指摘し、相撲は「営利を求めるのではなく、相撲文化の継承を使命」とした「公益法人に徹すべきだ」という著者の提言は的を得ている。
Posted by 
八百長、年寄り制度、横審、茶屋制度といった相撲独特のシステムを経済学という切り口から考察 した本。一見不合理に見える伝統的システムでも、角界という閉ざされた特殊な世界で伝統を保っ ていくにはもっとも合理的だったりするという面白さを理解できる。制度を作るときにターゲット やゴールが...
八百長、年寄り制度、横審、茶屋制度といった相撲独特のシステムを経済学という切り口から考察 した本。一見不合理に見える伝統的システムでも、角界という閉ざされた特殊な世界で伝統を保っ ていくにはもっとも合理的だったりするという面白さを理解できる。制度を作るときにターゲット やゴールが如何に重要か考えさせられる一冊。
Posted by 



