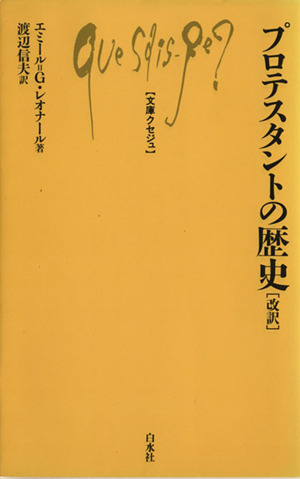
- 中古
- 書籍
- 新書
- 1226-29-02
プロテスタントの歴史 文庫クセジュ114
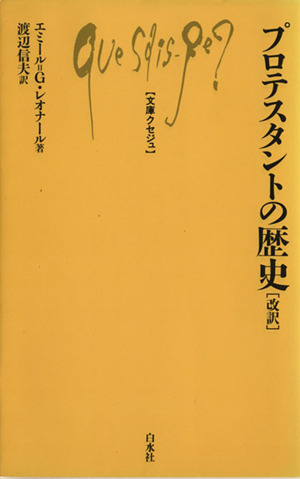
定価 ¥1,155
220円 定価より935円(80%)おトク
獲得ポイント2P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 白水社 |
| 発売年月日 | 1968/12/01 |
| JAN | 9784560051146 |
- 書籍
- 新書
プロテスタントの歴史
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
プロテスタントの歴史
¥220
在庫なし
商品レビュー
5
4件のお客様レビュー
高校世界史でもルターやカルヴァンなどで大きく取り上げられるプロテスタントについて、その歴史や信仰・儀礼上の特徴について概説した本。同文庫の『カトリックの歴史』と同様、ルネサンスを大きな転機と見なす一方で人間中心主義を批判している点が興味深い。 オススメ度: ★★★☆☆ 故郷は...
高校世界史でもルターやカルヴァンなどで大きく取り上げられるプロテスタントについて、その歴史や信仰・儀礼上の特徴について概説した本。同文庫の『カトリックの歴史』と同様、ルネサンスを大きな転機と見なす一方で人間中心主義を批判している点が興味深い。 オススメ度: ★★★☆☆ 故郷は群馬(図書館職員) 所蔵情報: 品川図書館 198/L55
Posted by 
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
エミール・G・レオナール(渡辺信夫訳)『プロテスタントの歴史』白水社、文庫クセジュ(1968):ルターから20世紀までのプロテスタントの歴史を経済や政治などに転化せず、信仰の問題を中心に編んだ歴史である。コンパクトであるが、内容自体が複雑なのであろうが、人名が多く、割り注も多くて読みにくい本である。最初に信仰の内在的原理で宗教改革を説明する立場を説明している。百年戦争(1337-1453)で荒廃した西欧には教会も聖職者も十分ではなかった、教皇庁もイタリア諸国家との抗争、アヴィニョン亡命(1309-77)、大離散(1378-1415)、教皇を掣肘しようとする公会議主義など危機にあり、こうしたなか信仰は家庭礼拝で守られていたが、これはプロテスタンティズムの「万人祭司」や、聖書や祈りで神と直接つながる思想をうけいれる土壌になった。聖書も中世をつうじて普及がはかられており、俗語訳もあった。宗教改革の時代まで、決して民衆は聖書の言葉から隔絶されていたわけではなかったと指摘がある。これは一般的な宗教改革の説明とは異なるが、重要な指摘であろう。ルターは敬虔を主として、罪を免れないことについて絶望すべきであるとし、この絶望のなかから、ただ信仰のみで救いに至るという信仰義認がでてくる。しかし、ルターは伝統主義者として多数者の教会を考え、カトリック教会を愛していた。95箇条提題とその後の論争によって教会と決別するが、秩序を維持する国家への期待はのこり、急進派がドイツ農民戦争を起こすと、王や貴族に弾圧を依頼する。このように国家との関係は国家教会の制度へとつながっていく。カルヴァン(1509-1564)はフランス人で、教会の給費をうけて、聖職にも任じられており、ヒューマニストでもあった。1533年、ルターの提題に好意的な講演をパリ大学のコップにさせたところ、避難がまき起こり、逃亡することになる。一時パリにもどったが、檄文事件で再び逃亡、バーゼルに逃亡し、ここで『キリスト教綱要』(1536)を出版した。晩年はジュネーブの教会規則・信仰問答・信仰告白などを起草し、プロテスタントの社会問題にかかわった。カルヴァンはルターの悲観主義的人間観に近いが、罪・苦悩、救済もルターほどに重要ではなく、「神に奉仕すること」を重視した。救済を追及したルターが人間中心的であったのに対して、神の栄光と神への奉仕を重視するカルヴァンは神中心的で社会性をもった信仰となった。ここから、「予定論」(救済される人間は定まっていて変えられず知り得ない)や「天職」の概念がでてきて、ウェーバーのいうように「世俗内的転換」を生み、資本主義の精神を生む。17世紀になるとカトリック改革で巻き返され、プロテスタントは弾圧され、衰退するが、長い戦いのはてに信仰の自由を勝ちとっていく。18世紀の理性の時代になると、合理主義からプロテスタントの信仰も微温的になっていく。しかし、17世紀から敬虔主義によってプロテスタント内部でも改革があり、メンノー派、バプテスト(洗礼派、全身を水に浸す方式で洗礼を行う。他の教派では頭に水を少し注ぐだけ)、クェーカー(神と直接つながろうとする見神派、祈りながら震えるのでクェーカーという)、メソジストなどの分派も生じた。メソジストはイギリスが発祥で、ジョン・ウェズリーの改革がもとになっている。かれは「わざ」の宗教のむなしさを知り、「大衆の使徒」として、敬虔の集いや相互の告白などの形式で活動した。意味は「きちょうめん派」である。現在、プロテスタントは全世界で2億6000万人ほどいて、アメリカが最大、ブラジルなどのカソリック圏にも改宗にいき、150万人の教会がある。ルター派が7200万人、バブテスト5000万人、メソジスト4100万人などである。布教方法は青年活動と聖書の配布である。プロテスタントは基本的にあまり信仰に熱心ではなく、むしろ世俗の内部でがんばっているというイメージが強かったが、プロテスタント自身もいろいろな派があり、救済の問題を重視したり、神への奉仕を重視したり、ふつうの人間が安心を得られるように、いろいろと自己改革をしていたのだなと再認識した。ルソーの思想の背後に、彼の故郷で活躍したカルヴァンの思想があり、マリ・ユベールというプロテスタントの敬虔派出身の自然宗教の徒の思想の影響をうけているそうである。
Posted by 
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
ルター以前のカトリック内における聖書の読まれ方が意外に民衆に開放されていたということに始まり、ルター、ツヴィングリ、カルヴァン派(改革派として成長していく歴史)、アルメニウス派、バプテスト派、メノー派、再洗礼派、英国国教会、メソジスト派、救世軍などの歴史が詳細に書かれており、頭の中の整理が出来ます。ルター派に所属している自分としては、敬虔主義に傾き、社会との接点が薄く、また国王、領主の指示によってドイツ、北欧諸国に広まっていったその歴史の記述を読み、改革派に比べ中途半端な点がやや寂しい思いがします
Posted by 



