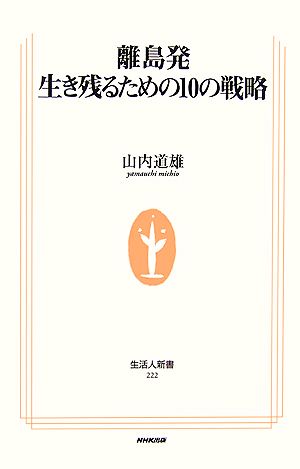
- 中古
- 書籍
- 新書
- 1226-15-02
離島発 生き残るための10の戦略 生活人新書
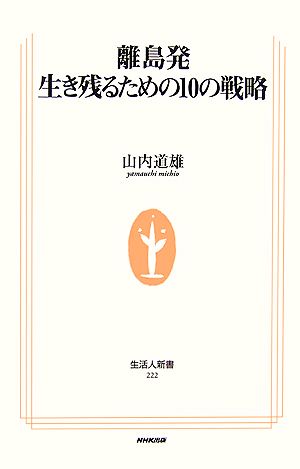
定価 ¥770
220円 定価より550円(71%)おトク
獲得ポイント2P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 日本放送出版協会/日本放送出版協会 |
| 発売年月日 | 2007/06/08 |
| JAN | 9784140882221 |
- 書籍
- 新書
離島発 生き残るための10の戦略
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
離島発 生き残るための10の戦略
¥220
在庫なし
商品レビュー
3.8
15件のお客様レビュー
人口2500人の海士町(あまちょう)の生き残り策を町長自身がつづった本。 読みやすい。 p20の人口ピラミッドが衝撃的。 これほどいびつな超高齢化と超少子化の図はこれまでみたことがない。 これが離島や山村地域の現実で、日本の他のまちもこれからこうなっていくわけである。 続くp...
人口2500人の海士町(あまちょう)の生き残り策を町長自身がつづった本。 読みやすい。 p20の人口ピラミッドが衝撃的。 これほどいびつな超高齢化と超少子化の図はこれまでみたことがない。 これが離島や山村地域の現実で、日本の他のまちもこれからこうなっていくわけである。 続くp22の農業従事者の年齢分布もすごい。 とんでもない表である。 こうした悪条件にかかわらず、数々の改革と新規事業にいどむ海士町長の筆致はなぜか明るく希望に満ちている。 前向きなチャレンジの姿勢はすばらしい。 そうでないと人はついてこないんだろうな。 海士町を応援したくなる本。
Posted by 
地方創生時代の未来を走る島 島根県海士町は、メディアで地方創生のさきがけ事例として報道されていることから、その取組について学ぶために本書を購入。 地方創生が叫ばれる10年前から、国の方針とは違う方向で、国の政策変更に負けずと、町を率いた町長に興味があったためだ。 本書は、地方が変...
地方創生時代の未来を走る島 島根県海士町は、メディアで地方創生のさきがけ事例として報道されていることから、その取組について学ぶために本書を購入。 地方創生が叫ばれる10年前から、国の方針とは違う方向で、国の政策変更に負けずと、町を率いた町長に興味があったためだ。 本書は、地方が変わるためのヒントにあふれていて、それが10の戦略として分かりやすくまとめられている。 特に、いいなと思った部分は、「其の3 意思は言葉ではなく行動で示す」である。 海士町長のすごいところは、スローガンの明確さと、それを実現するための組織づくり、そして自ら身を切る姿勢だろう。 このような町長のもとでは、職員の能力もいかんなく発揮されるだろう。 本書が書かれてからも、海士町では、沢山のIターン者が面白い取組をしているところであり、続編が書かれることを期待したい。
Posted by 
(1) 島根半島の沖合60キロの日本海に、隠岐諸島という島々が浮かんでおり、大小おおよそ180の島からなっています。このうち人が住んでいるのは西ノ島、中ノ島、知夫里島、島後島の4島です。その中の中ノ島全体を町域としているのが、海士町です。 著者である山中道雄さんは海士町生まれで...
(1) 島根半島の沖合60キロの日本海に、隠岐諸島という島々が浮かんでおり、大小おおよそ180の島からなっています。このうち人が住んでいるのは西ノ島、中ノ島、知夫里島、島後島の4島です。その中の中ノ島全体を町域としているのが、海士町です。 著者である山中道雄さんは海士町生まれで、2002年に海士町長に初当選しています。海士町は、財政破綻を目の前にしており、島がなくなってしまうかもしれないという状況にまで陥っています。そんな海士町の生き残りをかけて、山中道雄さんを中心とし、様々な人たちと協力して様々な活動を行っているという内容となっています。 (2) 山中道雄さんは海士町が生き残るためのキーワードは外貨獲得であると考えました。しかし、島に企業を誘致することは難しく、公共事業にも頼ることはできないということでした。 そうすると、島の外からお金を持ってくるということは、島の宝を島の外の人たちに売ることを意味します。この島にあるものにどれだけの価値を見いだし、あるいはどれだけの価値を付加して、島の外の人たちに買ってもらうか、ということになりました。 この島は半農半漁の島なので、島にあるものといえば自然と農産物、海産物ということになります。そこで、山中道雄さんや島の人たち目指したのは、個別の商品を売るだけではなく、島をまるごと売ろう、島をまるごとブランドにしよう、ということでした。 最終的には、海士町をひとつの総合デパートにするのが、皆さんの目標となっていました。その第一歩となった商品が、具にサザエを使ったレトルトパックのカレーでした。その後も様々な海士町の海産物などが商品化されたそうです。 海士町に多くの人を呼び込むためにも、海士町の魅力を伝えなくてはいけないので、島で採れた食材を使った商品開発はとても大事だと思ったので、良い提案だと思いました。 (3) 今回この本を読んで初めて海士町という場所を知りました。読み進めていくにつれて、海士町に住む人たちの大変さというものがわかりました。 山中道雄さんがどれだけ海士町のことを大切にしているかということも伝わり、とても良い町長さんだなと感じました。とても遠い場所ではありますが、ぜひ一度訪れてみたいと思いました。(Erii 20150105)
Posted by 



