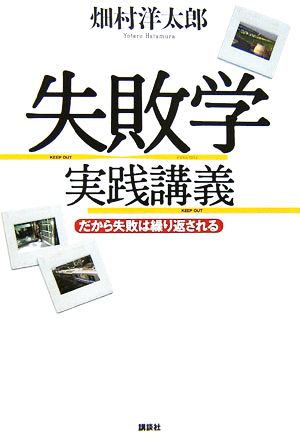
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 書籍
- 1206-03-19
失敗学実践講義 だから失敗は繰り返される
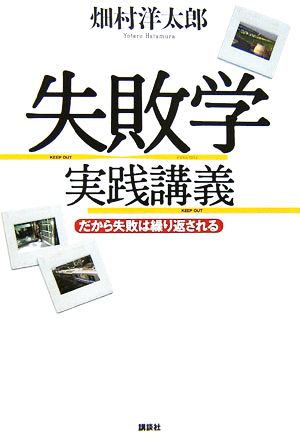
定価 ¥1,760
220円 定価より1,540円(87%)おトク
獲得ポイント2P
在庫あり
発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
2/21(金)~2/26(水)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 講談社/講談社 |
| 発売年月日 | 2006/10/01 |
| JAN | 9784062135931 |


店舗受取サービス
対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
さらにお買い物で使えるポイントがたまる
店舗到着予定
2/21(金)~2/26(水)
- 書籍
- 書籍
失敗学実践講義
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
失敗学実践講義
¥220
在庫あり
商品レビュー
4
10件のお客様レビュー
失敗学 実践講座 東京大学名誉教授で失敗学の第一人者 畑村洋太郎 氏の著書です。 過去に起きた事故事例9件を例にそこから学ぶべき内容を論じています。 【本書で学べること・考えること】 - 失敗まんだら(失敗の要因分析ツール) - 全ての失敗はヒューマンエラーから起こる -...
失敗学 実践講座 東京大学名誉教授で失敗学の第一人者 畑村洋太郎 氏の著書です。 過去に起きた事故事例9件を例にそこから学ぶべき内容を論じています。 【本書で学べること・考えること】 - 失敗まんだら(失敗の要因分析ツール) - 全ての失敗はヒューマンエラーから起こる - 「30年の法則」 - 「ハインリッヒの法則」 - 制御安全はあくまで補助 - 安全技術の伝達の途切れに注意 - 想定されることは起こる前提で取り組む - 人間の注意力には限界がある(優先順位が必要) - マニュアルは形骸化しやすい - 縦割り組織は隙間領域に注意 - 企業文化は短時間では醸成できない - トラブルは優先順位の低い些細な場所で起こる - DRも形骸化しやすい - 事後の対応が大事 - 効率化と手抜き - 「現地」「現物」「現人」が理解の基本 - 事故を社会の共有財産に 読んでみての感想です。 良書で、一読の価値があると思います。 失敗はつきものですが、過去の失敗に学び、今後に備える重要性を学ぶことができます。危機は色々と形を変えてやってくるので、この本が書かれた後に起こった事故にも同様のことが言えると思います。 自分が仕事で失敗した時は、前から変えていない場所をチェックしていなかったら、図面の不備で変わっていたことに気がつかず、不具合を起こしたことですね。 前と同じ、変えていないは危険だと痛感しました。
Posted by 
●同じ失敗が繰り返される「30年の法則」 ●「本質安全」の確保 事故を起こさないための努力を続けながら、それでも事故が起こることを前提にして「最悪の事態」だけは「絶対に」避ける備えをする。「制御安全」はあくまで補助的なもの ●確認作業は「パッシブ」型でなく「アクティブ」型であ...
●同じ失敗が繰り返される「30年の法則」 ●「本質安全」の確保 事故を起こさないための努力を続けながら、それでも事故が起こることを前提にして「最悪の事態」だけは「絶対に」避ける備えをする。「制御安全」はあくまで補助的なもの ●確認作業は「パッシブ」型でなく「アクティブ」型であるべき パッシブ型では、頭の中の単純知識群(メモリ)が増えるだけなのに対し、アクティブ型では、メモリから取り出した知識を使って、頭の中のCPUで実際に演算し、さらにその結果を検証する作業を通じて、その知識に関する思考回路を自分の頭の中に確立することができる。 使える知識が増えるというのは、つまり自分自身で頭の中に思考回路を作るということ。 ●”ヤイノヤイノ”に対しては、わかりましたと返事だけきちんとしながらも、注意されたことに全力で取り組まず、本当に大事なことをおろそかにしないよう気をつけながらも、“要求されたことに適度に対応する”のが正しい対処 ●中間管理層の活動の多くは内部向け ●確認すらしないで印だけ付ける →ペケペケペケ ペケペケペケが起こりやすい形骸化したマニュアルは見直す。 マニュアルは守るためにある、されどマニュアルは変えるためにある。 ●縦割り組織に横串をさす 若い組織:両方が自分の仕事と思う領域が重なり、オレがオレが・自分がやって当たり前 成熟した組織・年老いた組織:分担の間に隙間が生じ「遠慮の塊」が発生し、向こうがやるだろう・誰かがやるだろうという領域ができる 腐った組織:主張は「オレがオレが」実行は「向こうがやるだろう」 ●甘い共存策 三行合併で、新しいシステムを作るはずが、途中から「3つを合わせればできる」になってしまった。状況が大きく変化したときには、新しく要求される機能や新しい制約条件、安全性などをトータルで見ながら、全くゼロから全体を組み立てなおすしかない。 「トータル設計」一度全部捨ててから、本当にいるものを拾いなおす 人間の性癖として「今あるものの中から、どれがいらないか」を考えることが苦手なものである。だから、結局、あるものを生かすというつもりが、いらないものまで残ってしまいがち。いったん全部捨ててゼロから組み立てなおすほうがよい。
Posted by 
5年ぶりにもう一度読んでみました。 原発の事故が起きる前から存在する本ですが、中にJCOの事故が取り上げられていることが暗示的です。 失敗や危険を許容しない世の中で、失敗はそれでも起きます。「あってはならない」と目をつぶるだけでは、同じことが起きるだけだと読み手を説得するだけの事...
5年ぶりにもう一度読んでみました。 原発の事故が起きる前から存在する本ですが、中にJCOの事故が取り上げられていることが暗示的です。 失敗や危険を許容しない世の中で、失敗はそれでも起きます。「あってはならない」と目をつぶるだけでは、同じことが起きるだけだと読み手を説得するだけの事実がこの本には提示されています。 二度と同じことを起こさないための教訓、それは、世の中の共有財産として失敗を位置づけられるかどうかにかかっていることがよくわかるはずです。 実際、一度得られた失敗分析の数々は、何年たってもそこから学ぶべきことの気づきの宝庫になっています。
Posted by 


