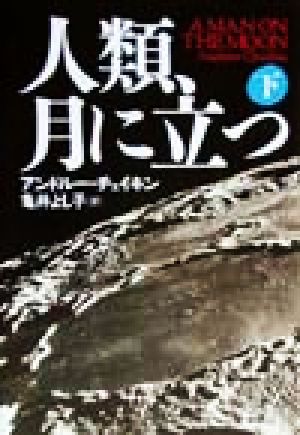
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1213-01-13
人類、月に立つ(下)
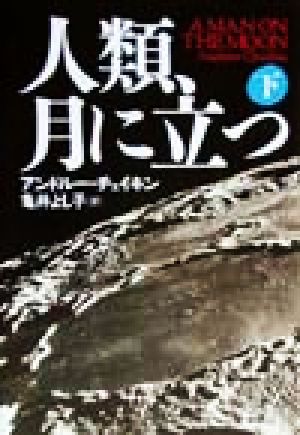
定価 ¥2,530
1,595円 定価より935円(36%)おトク
獲得ポイント14P
在庫わずか ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 日本放送出版協会 |
| 発売年月日 | 1999/08/23 |
| JAN | 9784140804452 |
- 書籍
- 書籍
人類、月に立つ(下)
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
人類、月に立つ(下)
¥1,595
在庫わずか
ご注文はお早めに
商品レビュー
4
5件のお客様レビュー
アポロ計画といえばNASAが実施した人類歴史上唯一の地球以外の星に人類が足跡を残した宇宙開発計画だ。 この本はそのアポロ計画を丹念に追い、アポロ計画に携わった人々を描き出している。 アポロ計画といえば、やはり11号の月面に始めて降り立った偉業があるが、この本のクライマックスはそこ...
アポロ計画といえばNASAが実施した人類歴史上唯一の地球以外の星に人類が足跡を残した宇宙開発計画だ。 この本はそのアポロ計画を丹念に追い、アポロ計画に携わった人々を描き出している。 アポロ計画といえば、やはり11号の月面に始めて降り立った偉業があるが、この本のクライマックスはそこではない。 実際、上下巻の上巻で11号の話はさらりと終わる。 この本のクライマックスは11号以降にあるように思える。 11号の成功によってアポロ計画は大きな危機を迎える。アポロ計画では20号まで打ち上げられるはずだった。しかし、月面着陸という目標を達成してしまったあと、「何故莫大な予算を投じて続ける必要があるのか?」という世論の方が大きくなったからだ。 では何のために? それは月という衛星の歴史を知るための天文学的、地質学的な調査、つまり科学調査のために続ける必要があったのだ。 初めの頃、宇宙飛行士になる前の職は軍人やテストパイロットという人々ばかりだった。 しかしそれは徐々に変わり、科学的調査を行うために、地質学者、物理学者が宇宙飛行士になるケースも増えてきていた。 訓練の中に、外に出て地質学者について、フィールドワークを行い、地質学的資料、情報の収集方法を学ぶ時間も取られるようになった。 月には降りず、司令船に残って月を周回する司令船パイロットの予定者たちは、訓練の中で小型機に乗って空から地形を眺めて、情報を収集するスキルを身につけることも重要視されるようになった。 11号で月に到達する事が出来るようになった時点で、アポロのミッションは月に行くことから、月の上で何をするか?という事に変わっていったのだ。 下巻はそういうアポロの科学研究的目的の面に話の重きが置かれる一方で、それらが一時の熱狂が冷めたアメリカ国内で賛同を得られず、予算の削減、計画の縮小、変更という事に、アポロ計画の終焉について語られる。 アポロ計画はケネディのムーン・スピーチという有名な演説で命を得て、60年代の夢を語る歴史になったが、同じ時期、同じ国がヴェトナム戦争という暗い歴史にもう片方の足を突っ込んでいた。そんな中で、今の家庭用ゲーム機にも及ばない低性能のコンピューターと何万人という人の力が集まって月に行く事ができた。 16号で月に行った宇宙飛行士 ケン・マッティングリーが、アポロをあの時代にしかできなかった事、今のNASAやアメリカにはあんな大事業を行う力がない、と答えているのもなんだか象徴的だ。 ちなみに、「アポロ13」という映画でジム・ラヴェルを演じたトム・ハンクスは、映画のすぐあとにこの本をベースにテレビドラマを製作した。 日本でもNHKが「人類、月に立つ」というタイトルで放送した。 その中ではこの本の中でもあまり触れられていない話も取り上げてドラマ化している。 僕は特に月着陸船の考案と開発に携わった人々を描いた回が好きだ。(そのエピソードはこの本の中にはほとんど出てこない)
Posted by 
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
本のタイトル通り、「人類が月に立つ」という歴史的事実がドキュメンタリー調に綴られている。この下巻では、アポロ13号~アポロ17号までのアポロ計画の実行模様が詳細に綴られていた。 初めて月を周回してきた8号、初めてアームストロングが月面に第一歩の足跡を記した11号、などのドラマが綴られた上巻も感動の要素が多く含まれていたが、下巻にもまた上巻とはちがう感動の要素が多く込められていた。 ケネディの時代に始まり、ニクソンの時代に終わったと言われる米アポロ計画。あの8号の周回成功からなんと24人もの宇宙飛行士が、月へ行くことに成功していた。 正直のところ、あのアームストロング船長の月面歩行の映像以外で、後続の計画での模様については、ほとんど知らなかった。1970年の大阪万博で、月の石を展示したアメリカ館に長蛇の列ができたことくらいが、このアポロ計画と接点となるニュースだろうか。 アポロ計画は、その莫大なコストやリスク、その実行目的などから、ニクソンの時代に入ってその注目度が低下してきたようだ。ついには、19号、20号の計画も中止となり、本書で最後に記されている17号が最後のプロジェクトとなった。 「西暦1972年12月、人類はここで、月への第一期の探査を完了した、われわれは平和の精神のうちにこの地を訪れた。同じ精神が全人類の人生に反映されんことを」 下巻の中では、やはり13号の奇跡の生還のドラマに胸を打たれた。片道38万キロあるという月までの行程の地球から32万キロ地点(上空)で、機械船のタンクが爆発し、その時点でパイロットたちが生きて生還できる確率は10%だと言われた。そこから、3人のパイロット達の生還するまでの戦いと、NASAのメンバーの総力で、彼らを生きて帰すために行った英知のチームワークのドラマが綴られている。 8号の成功が未知への挑戦のドラマであるならば、この13号のドラマは人類の英知の不可能への挑戦のドラマであったように思う。これは読むだけでは満足できなくなり、Amazonプライムで映画「apollo13号」を探さずにはおれなかった。映画は、本書の内容を忠実に再現されていたように思う。 17号では、月へ到達するという目標から、月の正体を追究するという目標へ変わっている。14号~16号と月への到達についての技術は安定し、ロケット内での生活環境も向上し、プロジェクトの目標が地質学的な研究へと移行してきた。 また、それぞれのプロジェクトは次のプロジェクトへの布石を打つというスタイルに変わり、例えば17号では15号でとられた写真などから、どのポイントの地質を調査するかなどの目標設定がなされ、調査自体が非常に効率的に進められたという感じがする。 月のクレーターは「衝突によってできたもの」か、それとも「火山爆発によるもの」か?月の地質を調査することにより、月の正体をあばいていく、、、それを最も効率的に的確に行うのは、地質学者が現地へ行くということだ。17号は最後のプロジェクトということもあり、地質学の博士号をもつハリソン・シュミットが宇宙飛行士として月へ向かったが、そのサンプル採集の模様は、地質学者の執念のようなものが感じられた。 月面作業には、様々な制約から時間的な制限が設けられるが、彼の採集活動は、命よりも研究優先と思わせるほどに学者魂を感じさせる場面もあった。 本書の初版は1999年の発行であり、それから約20年近くたった人類の宇宙開発事業や技術はどれほど進んでいるのだろうか?先の「月への第一期の探査を完了した」の言葉に呼応する「月への第二期の探査」は近い時期に到来するのだろうか?
Posted by 
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
なんといっても13号。映画にもなったのでこのドラマは一番有名です。14号では最初の7名の一人シェパードの搭乗。13号の失敗を受け、緊張です。15号では約40億年前の創世記の石との出会い、そしてアーウインがそこで感じた神の臨在。16号では更に長距離を踏破、月の新しい顔を発見。地震観測計の設置。アポロ最後の17号はもう今世紀中は月に来られないという惜別の思いそして最後に地質学者が搭乗して大きな成果。火山活動の証拠。アポロは月に行くだけでなく、月、そして地球の起源を探る旅だったことを改めて思い知りました。そのときから約20年。11号以外はあまり関心を持たなかったその背景にいろんな感動があったのですね。
Posted by 



