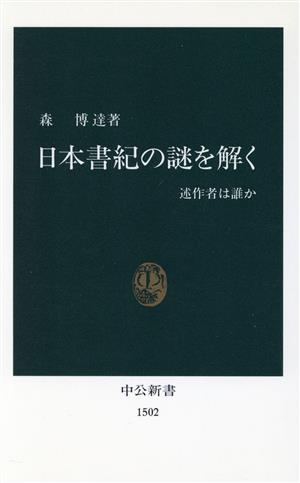
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 新書
日本書紀の謎を解く 述作者は誰か 中公新書
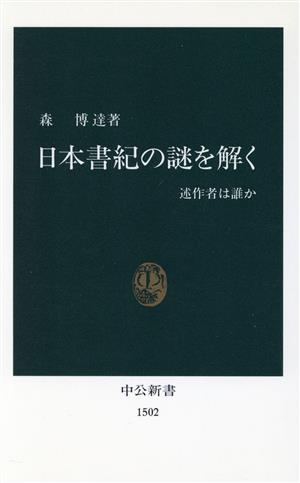
定価 ¥924
220円 定価より704円(76%)おトク
獲得ポイント2P
残り1点 ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
2/6(木)~2/11(火)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 中央公論新社 |
| 発売年月日 | 1999/10/25 |
| JAN | 9784121015020 |


店舗受取サービス
対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
さらにお買い物で使えるポイントがたまる
店舗到着予定
2/6(木)~2/11(火)
- 書籍
- 新書
日本書紀の謎を解く
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
日本書紀の謎を解く
¥220
残り1点
ご注文はお早めに
商品レビュー
4.2
10件のお客様レビュー
かなり難しい本です。…
かなり難しい本です。この辺のことに興味がある人でないとこの本の価値はわからないでしょうし、面白くも何ともないでしょう。古代史に興味があり、一度は日本書紀を読んだ方なら、是非お薦めです。
文庫OFF
中国の實錄や史書といった書物も、基になる史料があってそれを編纂したものなので、『日本書紀』にも原典があるというのはよくよく考えてみれば当たり前なのに、何故か新鮮だった。『日本書紀』の場合は『隋書』や『漢書』など歴史の授業でも聞くような有名どころから、素人は耳慣れない書物まで色々あ...
中国の實錄や史書といった書物も、基になる史料があってそれを編纂したものなので、『日本書紀』にも原典があるというのはよくよく考えてみれば当たり前なのに、何故か新鮮だった。『日本書紀』の場合は『隋書』や『漢書』など歴史の授業でも聞くような有名どころから、素人は耳慣れない書物まで色々あり、そういった種々の原典から文章を抜き出して、単語を入れ替え、言い回しを必要に応じて変え、潤色に使ったらしい。 思えば、役所仕事や法律文と似ていて、あくまでも作文ではなく、過去の編纂物からの引用や応用が基礎になっている。そういえば、役所や法律を引き合いに出さずとも、和歌や漢詩も言ってしまえば踏襲と引用の連続。それゆえに典故などを知っていないと理解できない。『日本書紀』も読む人が読めば「あー、あの文章からの引用か」とわかるようなものだったのだろうか。本書でもいくつか、これはここから、あれはあそこからの引用、というように紹介がなされている。 『日本書紀』は巻に因って編者が違い、大きく二分され(α群とβ群)、本書に拠れば巻14系のα群が当時の中国語ネイティブ、巻1系のβ群が日本語ネイティブによって編纂されているらしい (さらには巻30を第三分類として扱っている)。α群はさらに雄略朝と大化改新とで二つに画期されるらしい。その区分をつきとめる為に言語学や音声学、文献学など本当に幅ひろい知識が総動員されているが、著者は漢文の知識があり、それを基に研究を進めたらしい。その為、本書では『日本書紀』中にみられる「似非漢文」の紹介と、本来の正しい漢文ではどう書くべきなのかという説明もなされていて、加地伸行(二畳庵主人)『漢文法基礎』(講談社学術文庫) なんかを読むよりよっぽど為になる。 一番興味深かったのは聖徳太子が編んだと歴史の教科書に書かれている憲法十七条も、実は「似非漢文」だったということ。あんまり似非っぷりがすごいために、憲法十七条自体が「創作」なのではないかという説すらあるらしい。 本書は本当にいろんな知識を総動員しているので、日本語の変遷史や中国語の音韻など、知らないと何を言っているのかチンプンカンプンになるところも多少はあるかも知れない。逆をいえば、そういう知識があると、読んでいて一層たのしめると思う。
Posted by 
日本書紀三十巻の漢文記述の違いから、実際の著者が誰であったのかを追及する。 和風漢文と中国風の正格漢文、万葉仮名に対応する漢字の音の違いなどの多寡を分析し、構成の謎を解く。他説への言及も適切。 読み下しはついているものの、漢文の実例の提示が多いのでやや読み飛ばしつつですが、興味深...
日本書紀三十巻の漢文記述の違いから、実際の著者が誰であったのかを追及する。 和風漢文と中国風の正格漢文、万葉仮名に対応する漢字の音の違いなどの多寡を分析し、構成の謎を解く。他説への言及も適切。 読み下しはついているものの、漢文の実例の提示が多いのでやや読み飛ばしつつですが、興味深く。後年の続編もあるようなので、そちらもまた。
Posted by 


