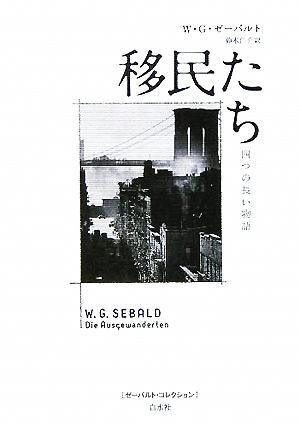
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1222-01-03
移民たち 四つの長い物語 ゼーバルト・コレクション
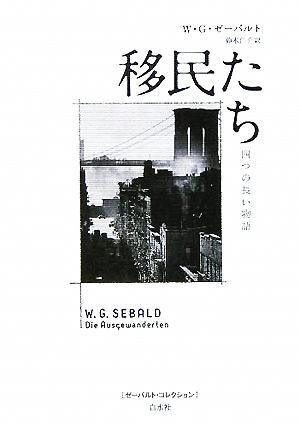
定価 ¥2,640
2,475円 定価より165円(6%)おトク
獲得ポイント22P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 白水社/ |
| 発売年月日 | 2005/09/30 |
| JAN | 9784560027295 |
- 書籍
- 書籍
移民たち
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
移民たち
¥2,475
在庫なし
商品レビュー
4.3
10件のお客様レビュー
「私」がかつて出会い、不意に記憶のなかから浮かび上がってくる人たちの奇妙な人生。写真と新聞記事の切り抜き、手記などの断片が巧みに嵌め込まれ、真実と思えないほど不思議な話が作り事と思えないほど生々しく語られていく。 7歳のときにリトアニアから家族でニューヨークに移住するつもりが...
「私」がかつて出会い、不意に記憶のなかから浮かび上がってくる人たちの奇妙な人生。写真と新聞記事の切り抜き、手記などの断片が巧みに嵌め込まれ、真実と思えないほど不思議な話が作り事と思えないほど生々しく語られていく。 7歳のときにリトアニアから家族でニューヨークに移住するつもりがロンドンで船から降ろされ、それから名前も英国風に改めて妻にも出自を伏せていた元開業医のドクター・セルウィン。両親が百貨店を営む地元の町に馴染めず、恋した女性を強制収容所で亡くすという悲しみを抱えながら教師という天職に就いたものの、74歳になって自死を選んだパウル。ドイツからアメリカに移住しホテルのボーイから富豪の息子の付き人になったが、主人が精神病院で亡くなってからは少しずつ狂っていき、ついにショック療法の被験体となって記憶を失うことを自ら望んだアンブロース。子ども時代に両親をナチに殺され、自分だけがイギリスに渡り生き延びたという過去をずっと胸に秘めていた画家のアウラッハ。「私」が見聞する四人の物語の裏には、ユダヤ人の歴史が陰画のように貼り付いている。 まるで来歴不明のアルバムやスクラップ帳があって、それを何年も眺めながら被写体の人生を妄想して書いたかのようだ。写真を使って本当らしく見せる手法について、作中でアウラッハの叔父が「新聞に載った記念写真は偽造なんだ。この記録が偽造だということは(略)おなじようにほかのものも偽造なんだよ、なにもかもはじめから」と語る場面がある。これはナチの焚書についての話なのだが、本作の構造に自己言及したセリフでもあると思う。たとえば、アンブロース叔父さんの章に日本人なら必ず知っている建造物の写真がでてくるのだが、その説明がとんでもないことになっていて笑ってしまった。国を追われた人びとの悲劇を描いた小説とだけ思っていたら足元を掬われるような虚構のうねりが、濁流のように物語を進行させていく。 本書を読みながら感動したのはまさにそういう歴史の被害者として一絡げにされる人たちの細部に対する、偏執的とも思えるほどの凝視だ。集合写真を見ていたはずがそのうちの一人のアップになって、古いはずの写真がその人の身につけている指輪やなんかまでくっきりと見えてくるような感覚を、文字を通して体験させられる。アウラッハの母、ルイーザが遺した手記のパートでは彼女が幼少期を過ごした村での幸福な記憶がいきいきと語られる。戦争がなければ書き残すこともなかったようなこまごました事柄が、本当の意味で人の生きた証になるのだ。 ゼーバルトを読むのは初めて。こんなにも好みにぴったり合って、こんなにも豊かなものを書く作家に出会えて嬉しい。主題をこれと一つに定められるような作品ではないので、いくつも気になったことがある。まずはやはり〈蝶男〉というモチーフ。セルウィンの章の網を持ったナボコフの写真、パウルとマダム・ランダウが知り合うきっかけが「ナボコフの自伝」なのも蝶男の変奏であり、移民というテーマにもかかっているのだろう。また、同性愛のほのめかしも繰り返される。セルウィンからネーゲリへの(妻への思いと比べられるほど)強い憧憬、アンブロースとコシモの閉じた関係、ウィトゲンシュタインへの度重なる言及。 それから帯には「四人の男たちの生と死」とあるが、彼らの人生の語り部はマダム・ランダウだったりフィーニ叔母さんだったりして、文章から女性の声が聞こえてくる小説だということ。アウラッハの章では後半のほとんどをルイーザの手記が占め、エピローグで「私」が今度はゲットーで働いていた若い女性たちの写真を凝視しながら〈造りだした記憶〉の世界に再び入り込んでいく最後の一文で、これは著者の意図する読み方だと確信が持てた。本作は語る女性たちの小説でもあり、語られなかった女性たちにも思いを馳せる人の手になる物語なのだと。 解説は堀江敏幸。だからというわけじゃないが、本書のはじめのほうは堀江さんにそっくりだなと思いながら読んでいた。かと思えば、ドクター・エイブラムスキーが語る恐怖のショック療法とアンブロースの最後の姿は、アンナ・カヴァンのように冷たい幻想性を帯びる。「私」がアンブロースとコシモの食事を眺める夢や、アウラッハが母の昔の恋人に出会う夢のシーンにも、白黒映画のようにしんと底冷えした陶酔感があり美しい。 彼らは初めから失われるために生みだされ、再び消えていった"キャラクター"なのだが、それにしては本作を読み終えたあと、空の手のなかに質量のある実在感が残りすぎる。はたしてそれは初めから何もなかったのと同じなのだろうか。
Posted by 
ゼーバルトは実に愚直な作家だな、と思う。器用に虚実を混交させて書いているようで、実は彼自身の実存を賭けてこうした「偽史」に取り組んでいるのだ、と思ったのだ。故に彼の書くユダヤ人迫害の歴史も少年時代の甘美な記憶も、現実を超えてより生々しく感じられる。書き続ける内に文章が単なる事実の...
ゼーバルトは実に愚直な作家だな、と思う。器用に虚実を混交させて書いているようで、実は彼自身の実存を賭けてこうした「偽史」に取り組んでいるのだ、と思ったのだ。故に彼の書くユダヤ人迫害の歴史も少年時代の甘美な記憶も、現実を超えてより生々しく感じられる。書き続ける内に文章が単なる事実の記述を超えて生々しい細部の描写や肥大化する記憶へと至るあたり、一般的にはむしろ「蛇足」と言われそうなところがゼーバルトの場合は美味しい贅肉/果肉として結実しているように感じられる。読みやすい作家ではない。晦渋だが、確かな力を感じる
Posted by 
ユダヤ人の移民の物語。4篇。一筋縄ではない。 ①元医師の物語。山岳ガイドの凍死体が72年を経て見つかる。 ②教師の話。鉄道が死のメタファー。ある意味わかりやすい。 ③大富豪の執事の話。精神病院への足取りが壮絶。 ④マンチェスターの芸術家とその母の手紙。最後も痛めつけられる。
Posted by 



