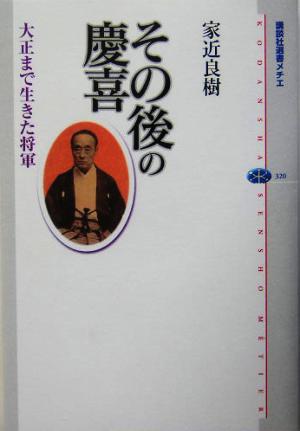
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 書籍
- 1216-01-09
その後の慶喜 大正まで生きた将軍 講談社選書メチエ320
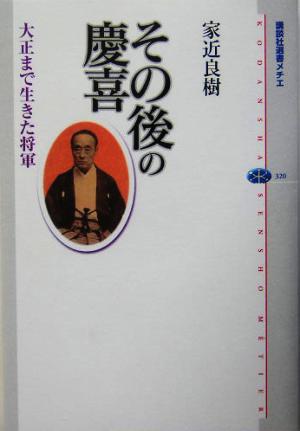
定価 ¥1,650
550円 定価より1,100円(66%)おトク
獲得ポイント5P
在庫あり
発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
2/21(金)~2/26(水)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 講談社/ |
| 発売年月日 | 2005/01/10 |
| JAN | 9784062583206 |


店舗受取サービス
対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
さらにお買い物で使えるポイントがたまる
店舗到着予定
2/21(金)~2/26(水)
- 書籍
- 書籍
その後の慶喜
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
その後の慶喜
¥550
在庫あり
商品レビュー
3.1
10件のお客様レビュー
「家扶日記」などをもとに明治期の慶喜を読み解く。 これは明治5年1月から大正元年12月までの、徳川慶喜家に仕えた家扶や家従が書いた、慶喜や家族の日常生活を記したもの。これは松戸戸定歴史館が所蔵し閲覧が可能になったのは1997年から。 鳥羽伏見から江戸、水戸、静岡、東京と慶喜の動...
「家扶日記」などをもとに明治期の慶喜を読み解く。 これは明治5年1月から大正元年12月までの、徳川慶喜家に仕えた家扶や家従が書いた、慶喜や家族の日常生活を記したもの。これは松戸戸定歴史館が所蔵し閲覧が可能になったのは1997年から。 鳥羽伏見から江戸、水戸、静岡、東京と慶喜の動きの内情が分かり興味深かった。江戸にもどり慶喜が自身の助命運動をさかんに行ったというのを別な本で読んでおり、その時はなにか腑に落ちなかったが、これを読むと、大政奉還もし、図らずも朝敵となってしまい、自身には朝敵との意識は無かったからなのだろう、と思った。 いままでの慶喜観に関しては、鳥羽伏見から江戸に逃げ帰り、大政奉還したにもかかわらず、朝敵となり明治期は薩長、朝延に恨みを抱いて、失意のなか生きたとするもの。これは幕末期の慶喜の評価と密接につながるとする。幕末期の慶喜は幕府権力の維持発展をはかることに務めた、とされているが、氏は大政奉還後、王政復古のクーデターの3日前にその動きを知りながら阻止しなかったことで、最終段階期には、幕府の復活はもはやあり得ないとの諦観を抱いていた、とする。 また、慶喜は明治30年代に復権を果たすまで、常に自身を朝敵としての立場を意識しつづけ、幕臣らの自分に押した卑怯者との烙印に耐え続け、その間の事情は一切説明しなかった。 慶喜が帰府後、静寛院宮に語ったところによると、鳥羽伏見後あわてて江戸に逃げ帰ったのは、錦旗をあげて大阪城にある官軍に敵対すれば、即朝敵となることを恐れたため。だが、その思いとは裏腹に、配下が鳥羽伏見で錦旗に発砲したとして、「朝敵」の本家本元になったと。 が、「朝敵の汚名」を晴らせないまま水戸へ向かう。だが水戸では派閥争いが続いており、勝海舟らが新政府に静岡移住願いを出し許可される。 明治期になっては徳川宗家、慶喜に対しては勝海舟が目を光らせており、慶喜には勝、大久保一翁、山岡鉄太郎らが、慶喜に自重を求めていた。それは勝らが、慶喜の名誉回復運動をしたことで、幕臣からの風当たりも強かったためもあるという。それが静岡に30年もいたことにつながるという。 <妻美賀子> 妻美賀子とは、明治2年から静岡で暮らす。「家扶日記」をみる限りでは、共に釣りにでかけたりと関係は好転し、明治10年代は平穏であったとする。明治19年には、不仲の元ともいわれる慶喜の義祖母・徳信院が静岡に来て、慶喜夫婦で院をもてなしている。美賀子は釣りを好んだようで、共ひとりを連れ清水湊へ釣りに行っている。また明治24年の7月7日に田安家と一橋家に嫁いだ鏡子と鉄子が里帰りした際にも彼女らと慶喜と美賀子が汽車で清水湊に釣りに行っている。 <慶喜の主な収入源> 明治35年6月3日、慶喜に公爵が授与され、徳川慶喜家を興すことが許される。それまでは宗家の義父扱いで、宗家からお金が来ていたが、家扶日記には、明治35年9月3日の「本月御定例金持参」を最後に記述は無くなる。 では新たな収入源はというと「家扶日記」では、第一、第十五、第三十五の各国立銀行、日本鉄道会社、朝のセメント会社、日本郵船会社、大日本人造肥料会社(これらの多くは渋沢栄一が関係)の株式投信の配当金がかなりの額にのぼったことが伺える。日露戦争の国庫債券も買ったようだ。株式は他の華族らも購入しており、渋沢が援助したというより、購入は渋沢栄一の事務所を通して株式を購入して、そこからの配当金を主な収入源にしていた、と考えられる、とする。 2005.1.10第1刷 図書館
Posted by 
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
江戸時代最後の将軍徳川慶喜については、大政奉還・江戸城無血開城以後の動向はあまり知られていない。普通、このような歴史上の人物は、亡くなるまでのことが詳しく語られていてもおかしくないのに……。 それ以後の慶喜については、慶喜の孫にあたる榊原喜佐子さんが書いた『徳川慶喜家の子ども部屋』を読んで、多少の知識はあった。日本国の支配者だった人物が、若くしてその地位から退き、その後の半生を一体どのように過ごしたのか、興味があった。 将軍の座を退いた慶喜はとにかく趣味人であったようだ。もともと好奇心旺盛な性格で、「思いついたらとにかく行動」の人だったのかもしれないけれど、意図的に政治の世界から離れるという思惑も多分にあったのだろう。 ずっと疑問に思っていたことがあった。それは、慶喜が将軍になってから、あまりにもあっさり大政奉還をしてしまったことだ。たしかに、当時はそうしないと日本を二分する内乱になっていただろう。大局を見極めていたということだが、それにしてもあっさりしすぎだ。 この本を読んで、なんとなく感じたのは、慶喜は徳川武士というより、自分のルーツを皇族に近いものと感じていたのではないだろうか。実母が有栖川宮家の出であること。正妻が今出川家長女で、一条家の養女として嫁いできたこと、実父の徳川斉昭が、ガチガチの尊皇攘夷の烈公だったこと。他の将軍と違って、天皇をはじめとする皇族に、親しみや尊敬の念を抱いていたのではないだろうか。晩年に公爵を授かり、朝敵の汚名を清算できたとき、すぐに京都へ向かい、孝明天皇陵をはじめとする歴代天皇陵を参拝している。そういう慶喜だからこそ、スムーズに政権が移行できたのだろう。 たしかに、『その後の慶喜』では大河ドラマはできない。でも、『その後の慶喜』のほうが、心の深い奥底を探ると面白いと思う。
Posted by 
徳川慶喜の幕府瓦解以降に絞った評伝。「敗者」としての失意や近代天皇制に対する抵抗感を強調する先行研究に否定的で、徳川宗家の従属的「隠居」扱いという身分上の弱さや、勝海舟らによる行動抑制方針が結果として国家からの距離を生んだとみなす。史料の制約もあって推測も少なくなく、別のアプロ...
徳川慶喜の幕府瓦解以降に絞った評伝。「敗者」としての失意や近代天皇制に対する抵抗感を強調する先行研究に否定的で、徳川宗家の従属的「隠居」扱いという身分上の弱さや、勝海舟らによる行動抑制方針が結果として国家からの距離を生んだとみなす。史料の制約もあって推測も少なくなく、別のアプローチによる研究が欲しいところ。
Posted by 
