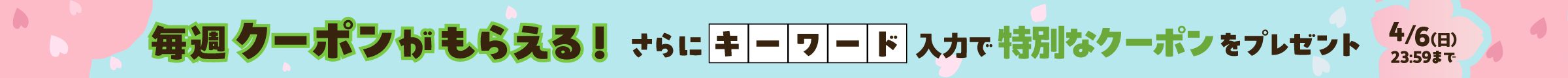- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 書籍
- 1222-01-08
黄色い雨

定価 ¥1,870
715円 定価より1,155円(61%)おトク
獲得ポイント6P
残り1点 ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
4/1(火)~4/6(日)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | ソニーマガジンズ/ |
| 発売年月日 | 2005/09/10 |
| JAN | 9784789725125 |
- 書籍
- 書籍
黄色い雨
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
黄色い雨
¥715
残り1点
ご注文はお早めに
商品レビュー
3.9
40件のお客様レビュー
意識の偏在を感じる作品。生きてる時も死んだ後も、自分が生きてきた場所そこかしこに意識の断片が存在していて、自分の死が近づくにつれて、すでに死んでしまった家族の意識の断片(亡霊)に馴染んでいく。その過程では、死を受け入れられてはいないけど、受け入れざるを得ない状況で、自分の気持ちも...
意識の偏在を感じる作品。生きてる時も死んだ後も、自分が生きてきた場所そこかしこに意識の断片が存在していて、自分の死が近づくにつれて、すでに死んでしまった家族の意識の断片(亡霊)に馴染んでいく。その過程では、死を受け入れられてはいないけど、受け入れざるを得ない状況で、自分の気持ちも矛盾する中、死へと向かう揺れ動く様が描写されている。 死を象徴する黄色い雨がどこか綺麗で、悲しい物語なのに読後は鬱々としない不思議な作品。
Posted by 
20世紀、スペイン。険しい山の斜面にへばりつくアイニェーリェ村で最後の住人になった男は、妻が首を括った縄を腰に結びつけ、窶れた犬と共に山と畑を行き来するだけの孤独な日々を送る。在りし日の村の記憶と突如現れては消えていく亡霊たちに男の思考は侵食され、ポプラの木から降り注ぐ〈黄色い雨...
20世紀、スペイン。険しい山の斜面にへばりつくアイニェーリェ村で最後の住人になった男は、妻が首を括った縄を腰に結びつけ、窶れた犬と共に山と畑を行き来するだけの孤独な日々を送る。在りし日の村の記憶と突如現れては消えていく亡霊たちに男の思考は侵食され、ポプラの木から降り注ぐ〈黄色い雨〉によって緩慢に腐敗していく村で死を待ち続ける。生と死が完全に重なり合う滅びの風景を描いた長篇小説。 これは死についての思弁小説だ。語り手はまず自らの死体が発見される場面を予告編のように語り始める。この時点で彼が生きているのか死んでいるのか、この小説の語り手は死者なのかという問いに最後まで答えはでない。私としてはむしろ、彼は自分の死を知った人びとの顔を繰り返し夢想しながら、生死の境界が溶け去った世界で生きながらえていると思いたい。いずれにせよ、朽ちていく村全体がすでに男の墓なのだ。 滅びのヴィジョンとして、降り注ぐ黄色いポプラの葉に覆われていく世界というイメージは美しく思える。それは長い時間をかけて人工物すらも腐葉土に変えてしまう力を秘めているだろう。光の腐敗、死の液体。 同じように死が「緑色のつぶやき」と表現されるのも、人間の営みに対する自然の優位性を強調している。男が夢想する自分の亡骸は苔に覆われている。いずれは村があった痕跡すら植物に覆われ、そこで生きた証は何も残らないだろうと男は予言する。黄色い雨のあとに緑色の死がやってくるのだ。 語り手は村をでると決めた息子を勘当していて、最後まで胸の内で責め続ける。この頑なさが妻をも追い詰めたに違いないのだが、自らの不寛容を反省することのない彼が、飢えても変わらず自分に付き従う犬のために最後の銃弾を使って死なせてやる場面はとても痛ましかった。 独居老人の心理小説として直近で読んだフィオナ・マクファーレンの『夜が来ると』と共通する点が多く、どちらも記憶や認識能力が混濁していくさまを詩的に捉えた文章表現が卓越していた。また、過疎化を題材にしたリアリズム小説でありながら、読み心地はコーマック・マッカーシーの『ザ・ロード』やデイヴィッド・マークソンの『ウィトゲンシュタインの愛人』のようなポストアポカリプス小説に限りなく近い。特に『ウィトゲンシュタインの愛人』とは、まだ生きながらえているということ、まだ世界が続くということへの乾いた絶望感が共通していて、鏡のような関係の作品だと思った。
Posted by 
死者たちが孤独な男の下を訪れる。死が生の領域を侵蝕し始める。精一杯生き延びて、崩壊と対峙しようとする努力が挫折しててゆく。 しかし、いつしかそうではない、逆なのだと感じてくる。男は生きながら内側に死を育んでゆく。 ある日突然に死が迎えにきて生を絶つのではない。死は最初から私の中...
死者たちが孤独な男の下を訪れる。死が生の領域を侵蝕し始める。精一杯生き延びて、崩壊と対峙しようとする努力が挫折しててゆく。 しかし、いつしかそうではない、逆なのだと感じてくる。男は生きながら内側に死を育んでゆく。 ある日突然に死が迎えにきて生を絶つのではない。死は最初から私の中にあり、それを認めて少しづつ解き放っていくのが生きるということ。 生きつづけることは、死につづけること。 そして、ふと思う。 もはや生者と死者の間に違いなどない。両者共にただ朽ちていくだけだ。 “死が私の記憶と目を奪いとっても、何一つ変わりはしないだろう。そうなっても私の記憶と目は夜と肉体を超えて、過去を思い出し、ものを見つづけるだろう。いつか誰かがここへやってきて、私の記憶と目を死の呪縛から永遠に解き放ってくれるまで、この二つのものはいつまでも死に続けるだろう” “おそらく今生きているこの夜は、自分が既に死んでいて、そのせいで眠れないだのだということに気づいたあの夜と同じ夜なのだろう。しかしそんなことはもうどうでもいい。 五日だろうが五ヵ月、五年だろうが同じことだ。時があっという間に過ぎ去っていったので、どんなふうに過ぎてゆくのかを見届けることもできなかった。逆に、今夜があの午後以来果てしなく続いている。暗い夜だとしたら、時間など存在しないわけだから、それを、私の心臓の上に振り注ぐ砂のような時間を思い起こす必要などないのだ” 死の床にて追憶と共に自らの肉体が滅んだ先を予言する、その語りに呪縛されたかのように本を置くことができずに一気に読む。 私が主語の独り語りなのに三人称かのような透徹した文章の美しさに引き込まれる。 ポプラを散らし秋の終わりを告げる黄色い雨が、村の街路を、犬の影を、私自身を染めあげていく。そのイメージが喚起する幻視に心が掴まれて、離れない。
Posted by