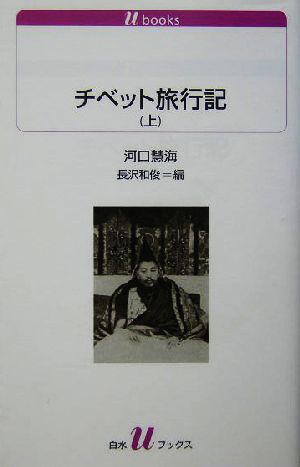
- 中古
- 書籍
- 新書
- 1226-06-04
チベット旅行記(上) 白水Uブックス1072
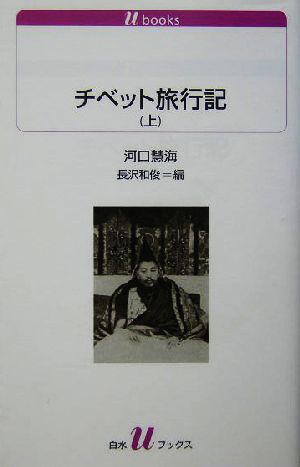
定価 ¥1,045
825円 定価より220円(21%)おトク
獲得ポイント7P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 白水社/ |
| 発売年月日 | 2004/08/11 |
| JAN | 9784560073728 |
- 書籍
- 新書
チベット旅行記(上)
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
チベット旅行記(上)
¥825
在庫なし
商品レビュー
3.6
9件のお客様レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
明治30年、チベットに仏法を学ぶため、単身海を渡った河口慧海の旅行記。旅行記というには壮絶というか、出会いと別れと艱難辛苦を乗り越えながら一歩ずつ進む様が現実とは思えないほどドラマチックで、普通の人だったらこの上巻の間に7回くらい死んでると思う。 チベットに入ろうとする外国人は殺される時代、事前に言葉を習得し、その土地土地の有力な僧侶や遊牧民に助けられつつ、時にはシナ人であると嘘をつきつつ、大迂回路をとってチベットに向かっている。彼が仏教の教えを愚直なまでに守るさまが、貫徹し過ぎていてむしろユーモアにさえ感じる。お話のお礼とか餞とかに、物をもらう代わりにその人の禁酒を乞うて、その人の魂を救ったと満足したり。何日も水がない中を彷徨いあるいて、やっと見つけた水たまりの水には虫が湧いていたので、虫を殺すわけにはいかないと躊躇したり。どんな窮地に陥っても愚直に仏教の教えを守る彼には、不思議と天の助けが与えられる。この時代に、何十キロもの荷物を持ってヒマラヤ越えするとか、そのエネルギーがチベットで仏法を学んで衆生を済度するため、とか、すごすぎる。折々に詠む旅の和歌も良き。彼が説教した人が皆感嘆して回心していくから、とても話の上手い人だったんだろうな。そしてそれを、数年学んだだけのチベット語でやってのけるってすごい。キリスト教の、使徒たちの宣教みたいなもの?言語を超越した何か。
Posted by 
G.W.にゆっくり読もうと、図書館から借りてきたら、むちゃくちゃ面白く、あっという間に上巻を読んでしまった。 河口慧海は明治時代の僧侶で、仏典の勉強をするため今から120年前に鎖国していたチベットに入った最初の日本人なのだ。それも密入国なのだがこれはその旅行記なのである。 仏教...
G.W.にゆっくり読もうと、図書館から借りてきたら、むちゃくちゃ面白く、あっという間に上巻を読んでしまった。 河口慧海は明治時代の僧侶で、仏典の勉強をするため今から120年前に鎖国していたチベットに入った最初の日本人なのだ。それも密入国なのだがこれはその旅行記なのである。 仏教的な話はほとんど出てこない。言葉もできない。ツテもない。ネパールからヒマラヤを越えて行く。チベットはほとんど標高5,000m級の高地にある。そこを獣や山賊に襲われながら、巡礼者や土地の人に助けられながら日本人であることを隠して密入国するのだ。その逞しさ、運の強さ、全部ひっくるめてとにかく痛快。 本当の意味での探検であり小説より面白い。冒険小説でいえばハガードの「ソロモン王の洞窟」を思い出してしまった。ノンフィクションであることを考慮すればアラン・クオーターメンを凌駕する。 現代は探検する場所がなくなってしまった。どこの景色も以前ネットかテレビかどこかで見たような景色だし、世界中の人は文明に触れていて、すべてが想定内のような気がする。だから未知なるものへの興味がオカルトに向いてしまうのかもしれないけれど、まだ知らない土地があった時代の本当の冒険! さあ、いよいよGW!下巻を楽しもう!
Posted by 
色んな人からの推薦本だったから、いつかは読もうと思いながら、どうもタイトルや装丁の詰まらなさそうな雰囲気から、手が遠のいていた。その事は素直に反省しなければならない。時代は明治。仏教徒の旅行記、しかも場所はチベット。このキーワードをどう感じるかは様々だろうが、私が思っていた読みに...
色んな人からの推薦本だったから、いつかは読もうと思いながら、どうもタイトルや装丁の詰まらなさそうな雰囲気から、手が遠のいていた。その事は素直に反省しなければならない。時代は明治。仏教徒の旅行記、しかも場所はチベット。このキーワードをどう感じるかは様々だろうが、私が思っていた読みにくさは微塵も無い。寧ろ、現代のバックパッカーにおける日記のようだ。あるいは、遭難者の手記だろうか、とにかく読みやすい。そして仏教観が世界を広げ、時のチベットの汚穢さは臭いすら経験させてくれるようだ。 志し。シャカムニ如来は王位も富貴も捨て、乞食として出家し一切の衆生のために、身を削り修行した。筆者も安穏と地位を捨て、覚悟を決めたのだ。そんな生き様からは、宗教を超え、学ぶ事は多い。
Posted by 



