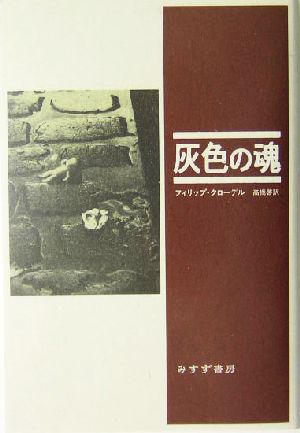
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 書籍
- 1222-02-02
灰色の魂
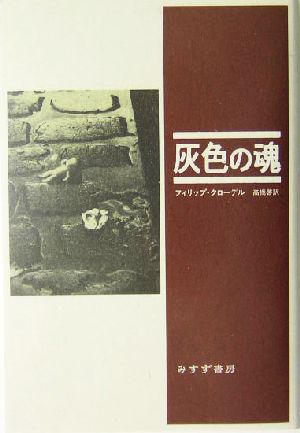
定価 ¥2,420
550円 定価より1,870円(77%)おトク
獲得ポイント5P
残り1点 ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
2/20(木)~2/25(火)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | みすず書房/ |
| 発売年月日 | 2004/10/22 |
| JAN | 9784622071143 |


店舗受取サービス
対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
さらにお買い物で使えるポイントがたまる
店舗到着予定
2/20(木)~2/25(火)
- 書籍
- 書籍
灰色の魂
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
灰色の魂
¥550
残り1点
ご注文はお早めに
商品レビュー
4.7
7件のお客様レビュー
第一次大戦の頃、前線にほど近いフランスの田舎町。1917年12月のある朝、この町の川から、少女の死体が上がった。犯人は誰なのか。小さな町にすむ人々に訪れる悲しみ。全てが過ぎ去った今、語り手である「私」は、過去と現在を行きつ戻りつしながら、苦しみに引き裂かれ喘ぐ魂の物語を書き残す。
Posted by 
時は1917年12月の最初の月曜日、所はフランスの一寒村。居酒屋の看板娘で、その美しさから「昼顔」と呼ばれていた十歳の少女が殺された。現場は村人が「城(シャトー)」と呼ぶ宏大な屋敷近くの岸辺。首を絞められた後で川に投げ込まれたらしい。「城」の当主は近くの市の検察官を務めるピエール...
時は1917年12月の最初の月曜日、所はフランスの一寒村。居酒屋の看板娘で、その美しさから「昼顔」と呼ばれていた十歳の少女が殺された。現場は村人が「城(シャトー)」と呼ぶ宏大な屋敷近くの岸辺。首を絞められた後で川に投げ込まれたらしい。「城」の当主は近くの市の検察官を務めるピエール=アンジュ・デスティナ。早くに妻を亡くして広い屋敷に僅かな使用人と暮らしている。感情を表に出さず、人付き合いもよくはないが村人には一目置かれていた。 独仏国境近くにある村には、長引く戦争で傷ついた傷病兵が大量に流れ込んでいる。少女殺害の犯人として逮捕されたのは二人の脱走兵だった。一人は自殺し、もう一人は拷問の末に自白。これで解決と考えられたが、実は事件当日「昼顔」と親しげに話をしているデスティナを見た人物がいた。 こう書いてくると、いかにも推理小説めいて聞こえるかも知れない。事実、物語は少女殺害の真犯人をめぐる謎を追う形で展開し、中盤に差し掛かったあたりで、語り手である「私」は刑事であったことが分かってくる。しかし、話者の語りに引き込まれるように読み進めながら感じるのは、謎解き小説を読んでいる時とはまるで異なった感興である。その印象を一言で言えば、いかにも重苦しく暗い。 ついこの間書かれたばかりのはずなのに、まるで19世紀の小説を読んでいるような気がしてくる。それではそれが嫌か、と聞かれるとそれはちがう。近頃ではあまり流行らないらしいが、人生というものの持つ重さや、人と人の出会いの不思議さ、人間の数奇な運命などという一昔前の主題群が、対比を駆使した典型的な人物造型、卓抜な譬喩、陰影を帯びた人生観を感じさせる警句、そして何よりも「民衆的な、時には卑俗とも言える文体と、詩的かつ叙情的な文体の混淆」に支えられて重厚な輝きを帯びて迫ってくるのだ。 小説は、事件の関係者であった元刑事の回想録とも手記ともいえる体裁で展開される。しかし、年老いた男の回想は記憶の小路を彷徨うように往々にして横道に逸れ、時間を遡行し、行きつ戻りつを繰り返し、なかなか謎の解決にはたどり着かない。しかも、男は事件の最中に最愛の妻を死なせるという悔恨を背負ってもいる。人生の終わりに近づいた人間がこれだけは語っておかなければ従容として死の床につくことができない、その謎とは何か。事件に関係する二人の男やもめと、検察官の敷地内の館に住まうことになる美しい女教師の関係はどうなるのか。女教師のモロッコ革の手帖に書かれていた秘密とは。近頃、こんなに読む愉しみを堪能させてくれる小説を読んだことがない。一気に読まされてしまった。 「ろくでなしだろうが、聖人だろうが、そんなのは見たことがないよ。真っ黒だとか、真っ白なものなんてありゃしない、この世にはびこるのは灰色さ。人間も、その魂も同じことさ…」。「泣ける」という触れ込みの本や映画が流行る昨今だが、自分の魂の色も知らずして、手放しで泣いていられるほど、この世界も人間も単純ではない。全編をおおう戦争の影、愛する者を喪失した人間の魂の悲哀を描いて近頃稀に見る力作。人の営みの愛しさが読後にしみじみとした余韻を残す。
Posted by 
陰鬱な小説である。 文体も決して読みやすいとは言えず、属性がくどいほど精緻過ぎたり、さほど重要でない人物の名前や風貌の描写も時として割りこんでくる。 しかし、読み進むうち、作者が綿密に計算した用意周到なプロットの罠に陥ちたことに気づくのはそう遅くはない。 この小説には語り手...
陰鬱な小説である。 文体も決して読みやすいとは言えず、属性がくどいほど精緻過ぎたり、さほど重要でない人物の名前や風貌の描写も時として割りこんでくる。 しかし、読み進むうち、作者が綿密に計算した用意周到なプロットの罠に陥ちたことに気づくのはそう遅くはない。 この小説には語り手が存在する。 「私」の素性ははっきりしない。 まるで、バルザックの『サラジーヌ』の語り手のように、一見第三者的だが、『サラジーヌ』の語り手よりもその情報は多く「私」はその事件の時や人々と絡み合っている。 第一次世界大戦の前後、フランスの田舍町で、10歳の少女が川で発見された。 少女は大聖堂の向かいにある食堂の末娘で、可愛らしく、店でも人気者だった。 この田舍の町には城があり、その城の城主は検察官であったが、少々変わり者で手伝いの者はいたが一人暮らしをしている。 彼は妻を亡くし、孤独であったが、威厳のある紳士であり城主であった。 やがて、その町の学校に、前任者が狂人になったため、後任として若い女性の教師がやってくる。 彼女は検察官の城内にある家に住むことになったが、暫くのちに突然死んでしまう。 そして、私の妻もはじめての子の出産で命を落とし、それから時は流れて検察官も死に、また時が流れ、誰も居なくなった城で、私はモロッコ革で覆われた赤い手帳を見つける。 時代、町、人々、殺人事件、戦争、愛憎、不信、悔恨、煩悶、これらが私の回想のなかで絡まり合い決してほどけることはない。それらは読者の心に一種のわだかまりを残し、謎解きのため、少女が沈められていた川の岸辺に、検察官の城に引き寄せられる。 赤い手帳は読者の謎をすべて解くことができるのだろうか。
Posted by 


