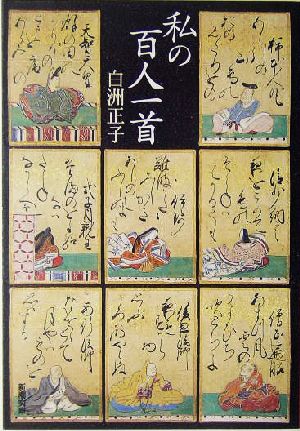
- 中古
- 書籍
- 文庫
私の百人一首 新潮文庫
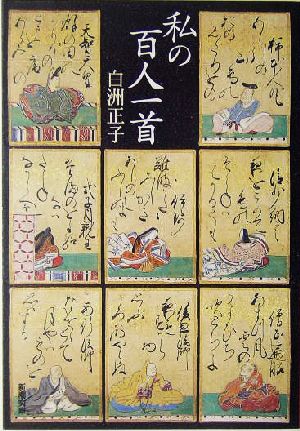
定価 ¥649
220円 定価より429円(66%)おトク
獲得ポイント2P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 新潮社/ |
| 発売年月日 | 2004/12/22 |
| JAN | 9784101379098 |
- 書籍
- 文庫
私の百人一首
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
お客様宅への発送や電話でのお取り置き・お取り寄せは行っておりません
私の百人一首
¥220
在庫なし
商品レビュー
4
32件のお客様レビュー
白洲さんのエレガンス…
白洲さんのエレガンスかつクレバーな日本語で解説された「百人一首」の読み方。歌の意味はもちろん、作者の横顔とか背景とかも丁寧に書かれている。
文庫OFF
百人一首をモチーフに…
百人一首をモチーフにしたエッセイ。日本文化入門としても。
文庫OFF
白州正子さんが若い時に好きだった百人一首について書いたもの。 百人一首について改めて知ったことがいくつか。 ・百人一首の成立にはいくつか説があるが有力なのは(この本が書かれた時点で)、藤原定家が親類の別荘の障子を飾るために自ら歌を選んで色紙に書いて送ったという説。定家は「新古...
白州正子さんが若い時に好きだった百人一首について書いたもの。 百人一首について改めて知ったことがいくつか。 ・百人一首の成立にはいくつか説があるが有力なのは(この本が書かれた時点で)、藤原定家が親類の別荘の障子を飾るために自ら歌を選んで色紙に書いて送ったという説。定家は「新古今和歌集」の選者の一人でもあったが、勅撰集であった新古今集と異なり、楽しみながら選んだといえる。 ・百人一首の歌は読人として名前の上がっている人一人の作とは言えないものも多い。古い歌を「本歌取り」してアレンジした歌や古くから有名な歌が少しずつ変わり、実際には誰の歌か分からなくなっているものもある。 ・読人の中には実在したかどうか、本当にその人の作か分からないのもある。柿本人麻呂、蝉丸、小野小町など。 ・百人一首は番号の古いものほど時代が古く(1番は天智天皇)、番号の若いものほど時代が新しい(新古今集の時代)。古い歌のほうが素朴である分、魂がこもっていて、新しい歌は万葉集の歌などを本歌取りして技巧でアレンジしたものが多い。 ・歌の並べ方は時代だけではなく、ライバルといえる歌人の歌を続けて並べたり、同じモチーフの歌を続くようにして比較できるように並べられている。 ・平安時代の「歌合」は文台や硯箱や紙にも宝石や金銀を散りばめた華やかな社交の場であった。つまり、歌とは単に詩心だけのものではなくアートの一つであった。 白州さんの解説を読んで、「この歌は好きだ」と思えたものをいくつか。 ・天智天皇 秋の田のかりほの庵のとまをあらみ わがころも手は露にぬれつつ 実った稲を鳥獣から守るために、仮の小屋を作り、その屋根を葺いた苫が粗末なので、衣が露に濡れて悲しいと言う労働歌。かりほは刈ると仮に、露は涙にかけてある。万葉集に詠み人知らずの原歌があり、天智天皇の作とは考えにくい。 ・持統天皇 春すぎて夏来にけらし白妙の 衣ほすてふあまのかぐ山 香久山は古代から信仰された神山、白妙(白い衣)は巫女の衣装。神聖な山を象徴する白と言葉には表れていない夏の若葉の緑が背景になってすがすがしい。 ・柿本人丸(人麻呂) あしびきの山鳥の尾のしだり尾のなかながし夜をひとりかもねむ 単に山鳥の尾の長さと一人寝の夜の長さを掛けただけではない。山鳥というのは雌雄谷間を隔てて寝る習性があるので、昔の人は「山鳥」と聞いただけで、直感的に答えるものがあった。 ・中納言家持 かささぎの渡せる橋におく霜の 白きをみれば夜ぞふけにける 七夕の「男女を取り持つ橋」を象徴する鵲と「霜」。季節は真逆であるが、「夜も更けたから女のもとに行きたい」というそこはかとない願望が秘められているようにも感じられる。 ・紀友則 ひさかたの光のどけき春の日に しず心なく花の散るらむ 「ひさかたの」と「しず」の響きが美しい。美しいのどかな春の日に「しず心なく」で爛熟した王朝文化にひたひたと忍びよる影が感じられる。 ・西行法師 なげけとて月やはものを思わする かこち顔なるわが涙かな 「かこち顔」は良くわからないが、心の中で泣いている様子が痛いほど分かる。 ・権中納言定家 来ぬ人をまつほの浦の夕なぎに やくやもしおの身もこがれつつ 「松帆の浦」に「待つ」をかけ、海女の塩焼く煙に身を焦がす思いをかけている。 「訳してしまうのは面白くない」とすべての言葉を解釈しつくさず、白州さんなりの自由な解釈をされていた。確かに掛け言葉で意味が幾重にも取れる和歌をわざわざ現代語訳してしまうのは野暮なことだろう。一つ一つの歌について関連のある原歌や読人の背景など詳しく書かれており面白かった。読人の中には「光源氏」のモデルになった人も三人くらいいて(源融、在原業平、在原行平など)、リアル源氏の世界にも少し触れて楽しかった。
Posted by 



