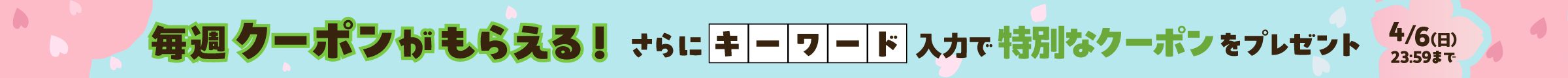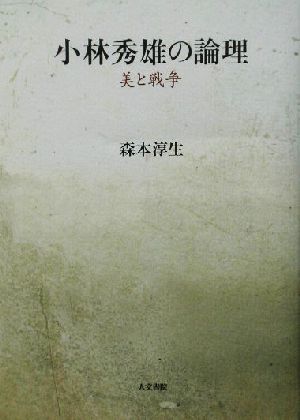
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1215-02-04
小林秀雄の論理 美と戦争
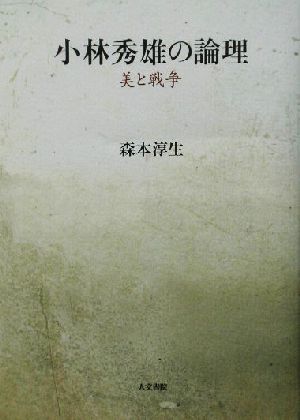
定価 ¥3,190
990円 定価より2,200円(68%)おトク
獲得ポイント9P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 人文書院/ |
| 発売年月日 | 2002/07/10 |
| JAN | 9784409160831 |
- 書籍
- 書籍
小林秀雄の論理
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
小林秀雄の論理
¥990
在庫なし
商品レビュー
4
2件のお客様レビュー
ヴァレリー研究者による本格的な小林研究である。小林の戦争中の発言を小林の批評と切り離して政治的文脈から批判するのではなく、その批評原理を内在的に読み解き、それが戦争の美化へと至る必然的道筋を明らかにしようとする。一貫した方法論と緻密なテクスト分析による労作であり学ぶところは多い。...
ヴァレリー研究者による本格的な小林研究である。小林の戦争中の発言を小林の批評と切り離して政治的文脈から批判するのではなく、その批評原理を内在的に読み解き、それが戦争の美化へと至る必然的道筋を明らかにしようとする。一貫した方法論と緻密なテクスト分析による労作であり学ぶところは多い。だが表現や批評に対するかなり偏頗な、と言って悪ければ、狭隘な理解に囚われているのは残念だ。 小林の批評が「他者の抹殺」だと言ったのは江藤淳だが、小林にとって対象は自己の「鏡像」に過ぎず、真の「他者」でも自意識の「外部」でもないとは小林批判の常套である。本書も「内面化される批評」をキーワードに従来の小林批判を反復する。だがそもそも内部/外部という二元論は果たして自明なのか。自分を写す鏡というが、鏡は曇ってもいれば歪みもある。そこに何がしかの「外部」が顔を覗かせる。「外部」としての他者とて、自己と出会うからにはそこに接点があるはずで、自ずと「内部」が滲み出る。純粋な「内部」としての自閉的モノローグに対して絶対的な「外部」に開かれた批評などという区別自体が抽象の産物なのだ。少なくとも極めて曖昧で不確かな区別である。せいぜい傾向ないし比重の差に過ぎず、言ってしまえば好みの問題だ。ある意味では実存的決断でもあって、批評の優劣とは別次元の問題だろう。ましてや戦争の美化とは何の関係もない。仮にあったとしたところで何が問題か?批評や文学が戦争を美化してはならぬと誰が決めたのか? 小林が傾斜していった「形」への理解も底が浅い。著者によれば「形」としての「作品」は「表現行為」の結果であり、その「影」に過ぎない。「表現行為」の本質は「出来事」性にあり、意図せざる多様性や偶然に晒され、決して予定調和的に「作品」に収斂するものではない。だから「影」としての「作品」を絶対化し、そこから遡行して「作者」を捏造してはならぬという。なるほど一理ある。「作品」からこぼれ落ちた多様性と偶然に満ちた「出来事としての批評」があってよい。だがそれが批評の本質だと言うなら話は違う。「形」は「影」でもあるが「影」に過ぎないものではない。「形」は「形」として顕在化しない多様性や偶然を内に含んでいる。であればこそ「形」に「美」が宿る。もちろん切り捨てることも、捏造してしまうこともあるかも知れない。だがそれは「出来事としての批評」とて同じだ。常識的にはむしろ「出来事」の方が恣意性は高い。その「出来事」が批評の特権性を僭称するのは傲慢というものだ。 著者には釈迦に説法だろうが、表現とは、そして言葉とは、無限の陰影を孕んだ多様性を固定化するものだ。その意味で抽象を免れない。だが人は言葉によって多様性を対象化し、定着させることで心に統一と安定を得る。それは仮りそめの統一かも知れない。だが仮りそめであれ何であれ、統一があればこそ多様性への憧憬も生まれる。統一なき多様性は錯乱でしかない。時に錯乱は魅惑的である。とりわけ青年にとって。だが人は青年であり続けることはできないし、それを望みもしない。小林の批評は確かに曖昧で両義的である。しかしそれが人間ではなかろうか。
Posted by 
「はじめに」を含めると全6章。小さな活字で本文がびっしり378ページという力作。著者はヴァレリーの研究者で、小林の出発期から戦時期までのテクストを論じる。 いったいに小林秀雄論は、どこか小林的な〈深遠さ〉〈曰く言いがたいものの手触り〉を強調しがちになるものだが、著者はあく...
「はじめに」を含めると全6章。小さな活字で本文がびっしり378ページという力作。著者はヴァレリーの研究者で、小林の出発期から戦時期までのテクストを論じる。 いったいに小林秀雄論は、どこか小林的な〈深遠さ〉〈曰く言いがたいものの手触り〉を強調しがちになるものだが、著者はあくまで論理的に、かつ内在的に小林批評の思想性と問題性を記述しようとしている。いままで読んだ小林論の中では、個人的に最も得心のいった1冊。 著者の議論のおおまかな要点は、以下の3点。?出発期から小林は、近代の分析的・実証的な合理主義の徹底がもたらした自意識の混乱と混濁の中で「表現」に向け苦闘する作家の精神に注目していた。 ?その延長戦上で小林は、すでに書かれた作品から出発しなければならない批評というジャンルの限界(特質)を一方で見つめつつも、同時に、「表現」の摸索という点で、創作と批評をほぼ同列同根のものと考えていた。 ?しかし、こうした小林の批評的な関心それ自体に、戦時下の小林が手放しで「民衆」に随従し、極端に現状追認的な戦争認識を記すことになる萌芽が存在していた。 とくに問題となるのは、3番目の論点だろう。著者によれば、小林は戦争における兵士たちのありようを、作家の「表現」行為と類比的に捉えている。その意味で、彼の戦時下のテクストは、初期批評からの論理的な帰結だと言える。だから戦後になってもかれは「反省しない」。反省することは、彼自身の批評一切を否定することになってしまうからである。 たしかに本書は、小林のテクストに対する内在的な読解として重要な達成といえるが、関連する論点として、同時代の書き手、とくに初期の保田與重郎の議論との関係は、興味深い論点となるかもしれない。初期保田のキーワードも、作家の「表現」をコトバの「表情」から読み抜くことだった。また、小林の文学批評が社会時評へとずれていく契機にかかわる論点も銘記しておきたい。小林の社会時評は、果たして当時、いかほどの影響力があったのか。文学者としての彼の発言に、どのぐらいの重きが置かれていたのか。ちょっと気になるところである。
Posted by