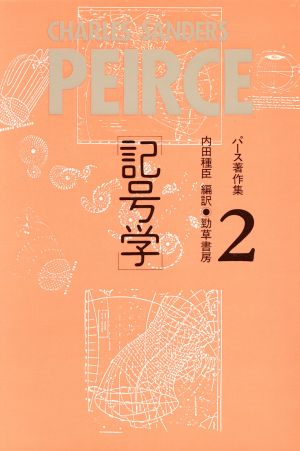
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1215-02-11
記号学 Peirce 1839-1914 パース著作集2
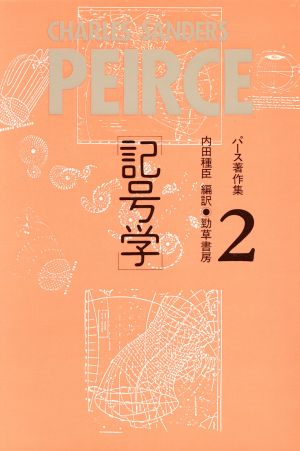
定価 ¥3,300
3,135円 定価より165円(5%)おトク
獲得ポイント28P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 勁草書房 |
| 発売年月日 | 1986/09/01 |
| JAN | 9784326198924 |
- 書籍
- 書籍
記号学
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
記号学
¥3,135
在庫なし
商品レビュー
2
2件のお客様レビュー
ようやく読むことが出来ました。 この上ない難解な文章! しかし、この上ない執拗な記号へのアプローチ! 多分、事前準備なく読むと 「ハー、なんじゃこりゃあーーーー(T_T)!!!!」 と、おもうこと間違いなし。 しかし、19世紀に生まれて、記号に対して激しいアプローチをした...
ようやく読むことが出来ました。 この上ない難解な文章! しかし、この上ない執拗な記号へのアプローチ! 多分、事前準備なく読むと 「ハー、なんじゃこりゃあーーーー(T_T)!!!!」 と、おもうこと間違いなし。 しかし、19世紀に生まれて、記号に対して激しいアプローチをした 唯一無二の鉄人ということはできるでしょう、 チャールズ・サンダース・パース!! まあ、この人も凄い貧乏だったらしいんですけどね。 マルクスも貧乏だったらしいけど・・・・・。 先駆的すぎる哲学者は大変ね。 じっさい、理解できたかというと40パーセントくらいだとおもいますが、 パースが原著で何を書いて、どういうふうにあがいていたのかが わかっただけでもめっけもんでしょう。 19世紀ということで今ひとつ歴史的背景がわからないので、理解しにくい ところはある。 しかし、結局、記号が何なのか、より込み入らない、図式化された 説明が必要なのであろうとおもいました。 ほんとに、言葉を言葉で説明してもわかんないです。 何が重要だったのかは、いろいろ言い表しにくい面がおおいいんですが、 二つの点だけ言えば 1.記号ってなんや? 2.記号を分類せよ! という二点でしょうか? 分類はパース自身も死ぬまで迷ったみたいで、 死ぬ前の分類では3の10乗とおりというわけのわからん量にまで分類していしまいました。 実際的なのは3個のサブカテゴリからなる10個の分類かな?
Posted by 
記号学の祖としてのパースの考えを読みたくて買った本。 しかしこれは特殊なアンソロジーである。訳者が、Collected Papers of Charles Sanders Peirceという文献(要するにパース全集か?)から「記号学」に関する文を抜き出して編んだものなのだ。この原...
記号学の祖としてのパースの考えを読みたくて買った本。 しかしこれは特殊なアンソロジーである。訳者が、Collected Papers of Charles Sanders Peirceという文献(要するにパース全集か?)から「記号学」に関する文を抜き出して編んだものなのだ。この原典の何巻の何ページ、という表記はあるが、それは一体パースの何という論文から採ったものなのか、あるいは草稿の一部なのか、といった情報はまるで記載されていない。 しかし読んでいると明らかに文章が連続している数章があって、これは1個の論文を含んでいるんじゃないかという気もしたが、確認しようがない。これなら、パースの論文集を普通に読んでみたかった。 さてパースの記号学、この本を見る限り、どうもまとまりのない思考の集積であるが、いずれにせよソシュールに由来する一連のフランス記号論とはまるで異なったものであり、人間が学問を開始するときにまずそうするように、「とりあえず」記号の「分類」をしている。(そう考えるとフロイトは違う。あれはやはり異能の人だった。) この分類はちょっとおぼつかなくて、パースは結局論理学をやりたかったのかなという風にも感じる。 なんとも言えない態の本だった。パースの全集を読んだ研究者には、便利なアンソロジーかもしれないが。
Posted by 



