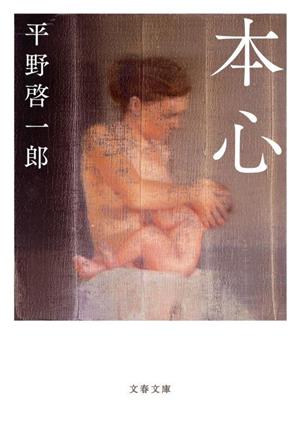本心 の商品レビュー
おもしろくて先が気になり一気読み。 亡くなった母親のバーチャルフィギア を作って、これからどうなっていくの?? と、思っていたけれど 新たな友人との出会いや母親との会話から 自分自身の本心を つかみ取ろうともがく主人公に 好意的になってきた。 死生観も問われる一冊だったな、 ...
おもしろくて先が気になり一気読み。 亡くなった母親のバーチャルフィギア を作って、これからどうなっていくの?? と、思っていたけれど 新たな友人との出会いや母親との会話から 自分自身の本心を つかみ取ろうともがく主人公に 好意的になってきた。 死生観も問われる一冊だったな、 「もう、十分」という、母親の気持ちも わからなくはない、正解かどうかわからないけど。 なんかこの年齢まで生きてきて もういいかな、と思う時がある、 あれしたいこれしたい、というのもなく かと言って現実に落胆して悲観的になってる わけでもない。 なんだろ、「もう十分」という気持ち。 十分やってきた、十分足りてる、十分生きた、 その後に言葉を繋げると、どれもなんか ぴんとこないけど。 VFは実際に中国でもビジネスになってるという、 亡くなった人が復活する。それは復活なの? 膨大なデータ、写真、メールなどから その人らしさを装ってるだけのVF。 とはいえ、もし義父や祖母が現れたら、、、 多分懐かしさや愛おしさなど色々な感情が 入り混じって泣いてしまうかも。 それができるよ、と言われてもやらないけど。 これはキッパリそう言える。 人の肉体の死は、魂の死とは違う、と思う、 人は必ず老いて、もしくは色々な理由で亡くなる、 それでも、世界は変わらずあり続けるし 自分のいない世界も想像しうる。 亡くなった後に自分のVFができたら、、、 それも絶対に嫌だ。現実の中で仮想としてまで 生きていたくない。 そもそもこの現実だってどこまでホンモノなんだか。 この本は社会の格差とか、人の本音、本心、 人との繋がり、家族の捉え方、 色んな方向から味わうことができる一冊だな。 最初はどんどん読み進めちゃったけど またしばらくしてからじっくり読んでみてもいいな。 映画は絶対いくー!!!
Posted by
「自由死」が合法化された近未来の日本でバーチャル空間内で生前そっくりの母を作り、自由死を望んだ母の、「本心」を探ろうとする。 というのが本筋だが、現代社会に訪れるであろう仄暗い部分を描写し、そこに向き合い、自己対話をしながら成長する主人公を見るのは、とても良い経験となった。
Posted by
亡くした母親のアバターを製作し、自身もアバターとして仕事をして生計を立て、同居することになった母親の友人女性との出会いのきっかけもアバター。 そんな未来社会という設定ながら、現在社会の延長線上にある「リアリティ」感に溢れた物語。 とにかく文体が美しく、哲学的でもあるのにスッと...
亡くした母親のアバターを製作し、自身もアバターとして仕事をして生計を立て、同居することになった母親の友人女性との出会いのきっかけもアバター。 そんな未来社会という設定ながら、現在社会の延長線上にある「リアリティ」感に溢れた物語。 とにかく文体が美しく、哲学的でもあるのにスッと心に入ってくる。村上春樹とは異なる、作品への没入感は同等だった。 人生の意味や対人関係、死生観など深く考える人にはとても魅力的な作品。
Posted by
題材も面白く本文も悪くない、のわりに終わりが薄い。最近いいものを広げたものの落とし所が浅い作品がおおい。映画化されるなら田中裕子の芝居が楽しみだなあという程度。AIモノでいうと、クララとお日様を超えれてない
Posted by
平野啓一郎氏の「ある男」を読了後、「分かるよ分かるよ」と理解者であろうとする自分と「いやいやそれでも」と正しさを振りかざす自分との間を行きつ戻りつ、私は何を信じて何を思えば良いのだろうと、心が迷子になる思いがした。 「本心」では、読みながらにして思うことが多すぎて、どうまとめた...
平野啓一郎氏の「ある男」を読了後、「分かるよ分かるよ」と理解者であろうとする自分と「いやいやそれでも」と正しさを振りかざす自分との間を行きつ戻りつ、私は何を信じて何を思えば良いのだろうと、心が迷子になる思いがした。 「本心」では、読みながらにして思うことが多すぎて、どうまとめたら良いのだろうかと迷う。 だけど、どちらにも共通して感じたことは、結局、生きてゆく中で誰かが思うこと、考えること、選択することを他者が〝いい〟〝悪い〟とジャッジすることはできない、できる人はいないと言うこと。誰も自分以外の誰かの心に責任を持つことはできない。 今より少し先の未来。 生活格差が今よりも顕著になった世界。AI、技術の進歩により人が担う仕事、人が働ける場所が激減した世界。仮想空間というVRの中を誰もが自由に出入りできる世界。 2040年。 おそらくこのまま進むとそれは夢物語でも机上の空論でもない私たちが迎えようとしている現実。 朔也(さくや)はVR(バーチャル・リアリティ)を使い、リアル・アバターとして足の不自由な人の代わりに旅行に行ったり、散歩をしたりという、近い将来、本当に出現するであろう職業についている。 報酬は決して多くはなく、利用者の〝評価〟により仕事量やご贔屓さんが決まる。 父を知らない朔也は、苦しい生活の中で、母と寄り添いながら静かに暮らしていた。 しかし、事故という突然の別れにより、母という唯一無二である心の拠り所を失ってしまう。 この世にひとりぼっちとなった朔也は、母のVF(バーチャル・フィギュア)〈母〉を作成する。 この世に生まれてきた以上、死は誰にでも訪れる。失う哀しみもまた誰しも乗り越えるべき逃れられない試練である。 この世の生を終えた人を仮想空間に甦らせる。 どんなに瓜二つに仕上がったとしてもそれはやはり〈母〉でしかなく、死者の喜びとはならず、生者に対する慰めの高いおもちゃでしかない。 それでも、心の折り合いをつける術がそれしかないのであれば、他人がそれを否定することもまたできないのだ。 生前、朔也は母より〝自由死〟の相談をされていた。「もう十分」そう言う母の気持ちを受け入れられない朔也はその申し出を拒絶する。 「死の一瞬前の時を愛する息子と過ごしたい」 そう願っていた母であったが、朔也が出張中の事故により、見ず知らずの医師たちに囲まれて旅立ってしまう。 果たして自分は間違っていたのか。 〝自由死〟を認めるべきだったのか。 人は自由であるべきである。だけどそれは死ぬことも自由でいいのかという極論も含めてしまう。 自殺や自殺幇助という哀しい事件は跡をたたない。その中で〝尊厳死〟は問われ続けられている。 〝自由死〟を願った母の本心を知りたい一心で〈母〉を求め、母を紐解いてゆく中で、朔也と〈母〉の関係や生活も変化し始める。 人は、1秒前の自分に戻ることはできず、私たちは時間と共に細胞単位、感情も含め常に変化し続けている。 生活環境や新しい出会い、他者性とあらゆることが今のこの1秒の私たちを成している。 現実を受け入れ、変化を受け入れ、そして未来に向かって進む。 遠く無い未来のVRを旅しているような一冊。 今年の19冊目
Posted by
2040年。遠くない未来の物語。 AI等の活用事例にそうなるかもしれないと考えさせられる予言書めいた作品でした。 作者独特の表現に辞書を参照しながら意味を噛み締め、共感/発見することができました。
Posted by
自分の死ぬタイミングを決めることは人間に許されるのか。 というテーマのお話でした。 「自由死」が合法となった近未来の日本が舞台です。 本書では貧富の格差はくっきりと2極化している時代において日々の生活を維持していくだけで精一杯の貧困層にとってまさに無理ゲー社会です。 老後の...
自分の死ぬタイミングを決めることは人間に許されるのか。 というテーマのお話でした。 「自由死」が合法となった近未来の日本が舞台です。 本書では貧富の格差はくっきりと2極化している時代において日々の生活を維持していくだけで精一杯の貧困層にとってまさに無理ゲー社会です。 老後のお金、健康の心配をしていく人間にとってその心配がなくなるのなら自由死はとても魅力的に映るのだろうと。 まさに読んでいて私もこんなに辛い現代において死のタイミングを選べるのなら楽なのでは、と頭によぎりました。 でもそうなると人間にとって生きるとはなんなのか。なんのために生きるのか。 とても難しいテーマだと思います。 答えがでないというか世論が自由死を求めていってしまう風潮が今後出ていくのではないかという気さえしまうのです。 近未来の設定ならではのヘッドセット、AI、アバターなどマトリックス的な世界をあらわしているのがとても魅力的でした。 ほんとに実現しそうなリアルさを感じました。 名著です。
Posted by
星3.2という感じ。 今秋映画化される作品ですが、それよりは前に読みたいなあと思っていたところ後輩が貸してくれました。感謝。 この作家さん、私の中では "自分の存在、他者の存在、生きるということ、自由とはなにか" みたいな哲学的なテーマを見つめるのが好きな人と...
星3.2という感じ。 今秋映画化される作品ですが、それよりは前に読みたいなあと思っていたところ後輩が貸してくれました。感謝。 この作家さん、私の中では "自分の存在、他者の存在、生きるということ、自由とはなにか" みたいな哲学的なテーマを見つめるのが好きな人というイメージがあるんですが、今作もまさにそんな感じだった。母が生前思っていたこと、言っていたことは「本心」なのか?真意は別のところにあるんじゃないのか?母が本当に何を思っていたのか知りたい…という願望に突き動かされた主人公が、母のゆかりの人々と会って色々話を聞きながら、改めて「母の像」を認識していくような話なんですが、、、中盤から終盤にかけて、主題が「母」ではなく、母の足跡きっかけで出会ったとある女性との話に移っていって、その中で「自分の本心」みたいなものにも葛藤するという、二段構え(?)的なことが上手いなあとも思ったものの、内容的にもページ数的にも母エピよりむしろそっちのくだりのほうがボリュームあったので、なんとなく、あらすじに書かれているのとは違った小説を読んだような気分になってしまったり。。ちょっと哲学性がトゥーマッチな感じがして、期待値よりは少し「うーん…」な感じで終わったかも。
Posted by
印象に残るフレーズが多い一冊だった。 語られなければ、いや、たとえ語られたとしても、(親であれ子どもであれ、自分とは別の)他人の「本心」なんてわかるわけない。 どうあがいても、自助か…。 どんな映画になるのか楽しみ。 池松壮亮と綾野剛、、、、ほんまに楽しみでしかない。
Posted by
「あの本読みました?」という番組に平野啓一郎さんご本人が出演されていて、こちらの作品の話をされていたことから興味が湧き、読みました。 自分自身の現在置かれている状況にもよるのでしょうが、自分の思いをひとつひとつ解説してくれているような感じがして、そのせいかなんだか苦しくなって、...
「あの本読みました?」という番組に平野啓一郎さんご本人が出演されていて、こちらの作品の話をされていたことから興味が湧き、読みました。 自分自身の現在置かれている状況にもよるのでしょうが、自分の思いをひとつひとつ解説してくれているような感じがして、そのせいかなんだか苦しくなって、休み休み読みました…。 映画化されるというので、そちらも楽しみです。
Posted by