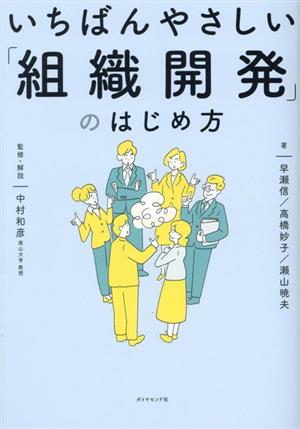いちばんやさしい「組織開発」のはじめ方 の商品レビュー
関係の質、対話、がまず大事。というのがわかった。 はじめから冷静に議論だけをしていては良い思考、行動には繋がらない。
Posted by
組織開発をする際に、文字どおりに最初に支障・壁になる「はじめ方」についての本。 その「はじめ方」は、ダニエル・キムの好循環モデルにおける「関係の質」の高め方と定義して説明し、中小企業・大企業・公共といった多様な組織における事例も紹介してくれている本。 事例紹介の後に、関係の質を4...
組織開発をする際に、文字どおりに最初に支障・壁になる「はじめ方」についての本。 その「はじめ方」は、ダニエル・キムの好循環モデルにおける「関係の質」の高め方と定義して説明し、中小企業・大企業・公共といった多様な組織における事例も紹介してくれている本。 事例紹介の後に、関係の質を4つのステップに分けたうえで、事例からのポイントになる部分を抜きだし、再度解説してくれている。 組織開発をはじめるとは、計画的なもの以外にこういうやり方があるのかとか、こういうはじめ方でもいいんだと思わせてくれる本。
Posted by
私ごとを私たちごとにするというテーマに魅力を感じた。「いちばんやさしい」とあるのはプレッシャーだができることから少しづつでも取り組めればと思う。
Posted by
社内である種課題図書的に勧められ、手に取った。 具体的な手法を細かく書くというよりは、規模別の事例を通して組織開発という考え方がどんなものかを示してくれていると感じた。 個人的に、一番最初の事例が読んでいてしっくり来ることが多かったと感じた。もちろんその他も、会社の規模感やヒエ...
社内である種課題図書的に勧められ、手に取った。 具体的な手法を細かく書くというよりは、規模別の事例を通して組織開発という考え方がどんなものかを示してくれていると感じた。 個人的に、一番最初の事例が読んでいてしっくり来ることが多かったと感じた。もちろんその他も、会社の規模感やヒエラルキーの違いによってアプローチの仕方が違うという意味で為になる点多かった。 次はこれを実践していくフェーズへ入っていくことになるのか。
Posted by
・感想 組織開発の為には関係者同士の対話が重要。 部下を見下したり、バカにしてるのはタコが自分の足を食べてるのと同じ。 緩く諦めず、常にあるべき組織論を取っていく。 お互いがまずは本音ベースで話せる関係性作りから。
Posted by
外部のコンサルによらず組織内で課題意識を持った人がはじめるという意味で、組織開発の「はじめ方」の本。 事例が中心で、いわゆるザ・組織開発というものではないのもあるが、そこも含めて、こんな感じだよねというリアリティを感じる本であった。 個人的には、「組織開発の探究」でガチ対話が...
外部のコンサルによらず組織内で課題意識を持った人がはじめるという意味で、組織開発の「はじめ方」の本。 事例が中心で、いわゆるザ・組織開発というものではないのもあるが、そこも含めて、こんな感じだよねというリアリティを感じる本であった。 個人的には、「組織開発の探究」でガチ対話が組織開発の出発点という議論がどうも違和感があったのだが、この本での「はじめ方」は、まず「関係の質」を高めるということが出発点になっているようで、そちらの方が自分の経験知に近い感覚があった。 ガチ対話をやるとしても、その前にそれをやれるだけの相互信頼感、「心理的安全性」が必要だと思うし、現実を関係者で理解するために「ガチ対話」というプロセスを必ずしも通らなくてもいいんじゃないかと思っている。 この本でも、最初のダイアローグのテーマは、問題というよりはポジティヴなトピックを選んだ方がいいということが書いてあって、私もそれに賛成だ。 著者は、「構造化された組織開発」と「構造化されていない組織開発」があるとして、この本では、「構造化されていない組織開発」であるとしている。が、この表現はやや違和感があって、要するに社内外の専門家が入ってやる組織開発と 社内の志がある人がやる組織開発ということではないかと思う。 で、私は、圧倒的に後者の方が重要だと思っている。仮に専門家を入れるとしても、日常は社内の志のある人が中心となって活動しているということが、成功の前提だと思う。それは「構造」があるか、どうかの問題ではないと思う。 多分、「組織開発の探究」で暗黙の前提になっているのは、社内外のコンサルがある組織の組織開発をはじめる時の課題の共有の必要事項として「ガチ対話」なのではないかと思った。 あと、この本では、組織開発と人材開発の連動ということも強調されていて、この点については、「組織開発の探究」でも触れらていて、私もその通りだと思う。 ただ、私は、もう一つ、業務との連動ということもとても大事だと思っていて、この本では、その辺りについては「タスク・プロセス」と「メンテナンス・プロセス」ということで触れらていると思うのだが、本での記述は、「メンテナンス・プロセス」が中心となっている。 その辺りは、この本は組織開発の話しで、業務は職場によって違うからここではあまり触れられてないということなのだろうか?著者たちはあくまでもこの本は「はじめ方」なので、その辺りははじめ方の次にあるステップという位置付けなのかな? でも、その辺りこそ外部の人ではなく、内部で業務をしている人たちが専門家であるわけで、そのあたりが次のステップというより、最初から連動しているべきだとも思うところだ。逆にいうと、その連動性が最初から意図として伝わっていないと、組織開発の取り組み自体が、「この忙しい時に、なんでこんな話をしているのだ?」という反感につながってしまうように思う。 などなど、いろいろ考えてしまった。 が、そういうことも含めて、組織開発にある程度の知識がある人も読んでみる価値のある本だと思う。
Posted by
タイトル通り優しくわかりやすい。後半は事例集となっており、自社と似通った組織の事例がとても参考になった
Posted by
組織開発に関する軽めの入門書。 理論よりも先に実際の事例研究から入るので、理解しやすかった。 自分が勤める会社でも、昨年あたりから「エンゲージメント」という言葉がキーワード化してきていて、関連する取り組みが増えている。その根底にあるもう少し大きな概念が組織開発だなと理解。 「組織...
組織開発に関する軽めの入門書。 理論よりも先に実際の事例研究から入るので、理解しやすかった。 自分が勤める会社でも、昨年あたりから「エンゲージメント」という言葉がキーワード化してきていて、関連する取り組みが増えている。その根底にあるもう少し大きな概念が組織開発だなと理解。 「組織がより良くなる、その組織に所属する人がコミュニケーションを通じてより良くなる」そんな事が組織開発の目的で、実行する組織の規模感や性格によって具体的な手法は大きく異なる。 大企業事例として東芝テックとパナソニックが出てくるが、どちらも組織の長の感度が十分に高かった事が成功の鍵だったように思える。 もう少し小さかなレベルで行うぶんにはやりやすいかな。
Posted by
組織開発のケーススタディとよいと考えられる手法の提示、乃至は手引き 初めに時間をかけた方がよい、相互理解、信頼関係の構築、価値観の共有、自己開示、問題意識を持っているところから取り組む 私ごと、を、私たちごと、にするための手法 見えていない問題について、提示し、否定せず、ポ...
組織開発のケーススタディとよいと考えられる手法の提示、乃至は手引き 初めに時間をかけた方がよい、相互理解、信頼関係の構築、価値観の共有、自己開示、問題意識を持っているところから取り組む 私ごと、を、私たちごと、にするための手法 見えていない問題について、提示し、否定せず、ポジティブな投げかけで話し合う これからの時代の企業で、給与以外にキャリアを踏んでいくための導
Posted by
読了しました。 ■なぜ手に取ったのか 私は、これまで大なり小なり組織を多く作って(開発)きた経験してきました。 しかし、その過程やアプローチを、なかなか自身で言語化できておらず、 体系的な知識を持っていなかったので、本屋でタイトルと立ち読みし、 惹かれて手にしました。 ■何が...
読了しました。 ■なぜ手に取ったのか 私は、これまで大なり小なり組織を多く作って(開発)きた経験してきました。 しかし、その過程やアプローチを、なかなか自身で言語化できておらず、 体系的な知識を持っていなかったので、本屋でタイトルと立ち読みし、 惹かれて手にしました。 ■何が語られていたのか 組織開発とは、「意図的により良いチームを作る」として 本書は話しが進められます。 現代社会は、多様な価値観、膨大な情報量、スピードが求められる 数々の判断などの環境が取り巻いており、これまで経験してきた スキルだけでは、なかなか成果がだせない、笑えないことが多い。 なんか「モヤモヤ」する。そのことをを解消するのが組織開発です。 決して緩い取り組みではなく、生産性・アウトプットを出す組織は どのように意図的に構築されるのか。 企業はもちろん、地域活動の組織など人が複数集まれば、必然と現れる「組織」。 7つの実際のケースを取り上げて、キーワードは「健全性」、「効果性」、 「継続性」を切り口に語られています。 似て非なる言葉としてあるのは、「人材育成」。 個人のスキルをアップするのではなく、目的のある、あらゆる人の集まり をどにように適切につなげ、一人一人を同じベクトルに向けることができ るかということが語られていました。 ■何を学んだのか 目的をもった組織の「モヤモヤ」をどのように解消するか。 これまで、私は「目的の共通認識を持つ」ということを意識的に 取り組んできました。 概ねそのようなことが記載されています。ただ、現代社会をもつ環境変化に 対応するため、柔軟かつ意識して手を打つことの重要性が得られました。 ■どう活かすのか これまで私が、無意識または意図的に行ってきた延長であることを 再認識させてくれた著作でした。 また、そこにとても大事なのは、自己肯定と他人尊重が欠けると、 致命的な状態になることも、改めて気づかされました。 そのことが現代社会はとても難しくなりつつあるので、現在の取り巻く環境に 合わせた、著作で得られた具盾居てきなアプローチを意識的に活用しようという 気持ちにさせてくれる本でした。 ■どんな人にお勧めなのか 職場を変えたい人、チームで成果を出したい人、リーダー、管理職、 地域活動している人にお勧めの本です。
Posted by