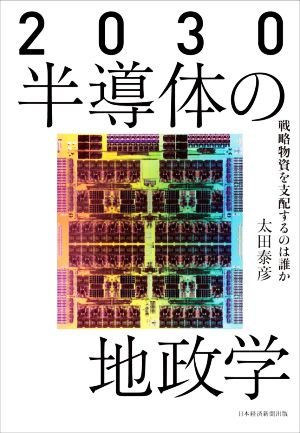2030 半導体の地政学 の商品レビュー
現在の半導体産業の構成、各国家の姿勢がわかる。安全保障の視点が入っていて面白い! 半導体そのものの仕組みについては解説なし
Posted by
半導体はもはや「産業のコメ」どころではなく、戦略物資であり社会インフラであり経済戦争の主役だ。それがわかる一冊。 米国によるTSMCゴリ押し誘致と対中半導体戦争のジャイアンぶりが凄まじい。 バリューチェーンのキープレイヤー ■設計:エヌビディア(AI)、クアルコム(スマホ) ■...
半導体はもはや「産業のコメ」どころではなく、戦略物資であり社会インフラであり経済戦争の主役だ。それがわかる一冊。 米国によるTSMCゴリ押し誘致と対中半導体戦争のジャイアンぶりが凄まじい。 バリューチェーンのキープレイヤー ■設計:エヌビディア(AI)、クアルコム(スマホ) ■メモリー:マイクロン ■5G:ファーウェイ、エリクソン、ノキア ■知財:アーム ■製造受託:TSMC、サムスン電子 ■製造装置:ASML、AMAT ■ユーザー:グーグル、アップル、MS ■日本勢:信越化学、東京エレクトロン、スクリーン、ソシオネクスト、キオクシア
Posted by
図書館で借りた。 半導体に関するここ近年の国際関係を綴り、これからを見つめる本だ。タイトルには2030とあるが、2030年キッカリに何かイベントが待っている訳ではなく、"この先数年間の間に起こるであろう"という観点というのが含意されている。 日経新聞の記者が書...
図書館で借りた。 半導体に関するここ近年の国際関係を綴り、これからを見つめる本だ。タイトルには2030とあるが、2030年キッカリに何かイベントが待っている訳ではなく、"この先数年間の間に起こるであろう"という観点というのが含意されている。 日経新聞の記者が書いた文章なので、技術的側面はそんなに深くない。しかし国際関係や日本政府内に関する情報は詳しい。やはり新聞の延長と思って読むのが良いのではないかと思う。よく「ニュース解説」的なジャンルがあるが、その範疇かと思った。 いちエンジニアとして、こういった話にもついていけるように、ある程度教養として知っておきたい。
Posted by
筆者は優れた国際報道をした記者に贈られる「ボーン・上田賞」の受賞者。ジャーナリズムの観点でも十分ドラマティックで刺激的なのだが、分析と提言がすばらしい。2023年に話題になった「半導体戦争」(クリス・ミラー著、ダイヤモンド社)と併読すると、半導体をめぐる国際政治・地政学と技術トレ...
筆者は優れた国際報道をした記者に贈られる「ボーン・上田賞」の受賞者。ジャーナリズムの観点でも十分ドラマティックで刺激的なのだが、分析と提言がすばらしい。2023年に話題になった「半導体戦争」(クリス・ミラー著、ダイヤモンド社)と併読すると、半導体をめぐる国際政治・地政学と技術トレンド、人間模様それぞれの解像度が一段と上がる。 半導体戦争もそうだが、ベースとなる感想はアメリカ恐るべし、モリス・チャン恐るべし、だ。日本への提言はおそらく著者の知己の経産省幹部らとの議論もふまえてのことと思われる。提言にある環太平洋半導体同盟などは対中国でみても必要性はわかる。その前の章のシンガポール、コーカサスの事例も興味深い。日本には半導体材料など素材・化学の分野で世界的に高シェアの企業は多い。日本なしではできないサプライチェーンをいかに磨き、冗長性があり、堅牢な仕組みにしていけるかが肝要なのだろう。 日本はかつて通産省が産業構造の変革を主導して成功したという歴史(一部は神話?)があり、その後はおとなしくなった。今起きている日本国内でのTSMCやラピダスの動きは世界が半導体重商主義といえる状況になる中での日本の目に見える対策なのだろうが、米中だけでなく韓国や台湾、ヨーロッパの友好国との連携と競争になる。これらを支えるには政治の安定と周辺産業の高度化・集積が不可欠だろう。 後者については、スタートアップ育成、その前の段階の教育・研究が重要であり、本に出てくる東大の黒田先生の取り組みが広がることに強く期待したい。同じく本に出てくる小池氏は日立と台湾UMCのファウンドリー合弁の挫折からラピダスの社長についての再挑戦だ。東芝にいた舛岡富士雄さんもご健在。日本の半導体の1990年代からの凋落からの復活戦で、世代を超えた挑戦に期待したい。 前者については、アメリカが「もしトラ」の前提ではなく、「すでトラ」と構えて、東アジアでは韓国のユン政権、台湾の頼次期政権との政治の友好関係を揺らぎないものにしておく必要があると痛感した。日本の政治が揺らいでいる場合ではないなあ。
Posted by
日本の立ち位置。将来への提言。 各国、各企業の解説がわかりやすく、まとまっているので素晴らしい! TPPってそうなんだ!半導体チップの微細化は今後こうなるんだ!と
Posted by
半導体はただのビジネスで扱う電子製品ではなくて、国防をも左右するもの。日本は半導体ビジネスに遅れをとった以上のビハインドを背負っているということがわかった。NTTのIOWN構想、どうかモノになってほしい。最近読んだ中では最も地政学を学ぶことができた本。
Posted by
世界規模でどれだけ半導体の需要があって争奪戦があるか背景を追って知ることができた。産業のコメと呼ばれる半導体を各国が鎬を削って投資しているが、日本はまだまだ他国に遅れをとっている。これから巻き返したいところ。
Posted by
大袈裟に書いてあるようにも思えますが、米国の異常なまでの誘致、排除を考えると筆者の意見に賛同せざるを得ません。 日本においては、まだ世界のトップランナーである所をベースとして、2030年〜それ以降にかけての戦略を考える事でしょう。 岸田君の頭と胆力では無理なので、役人の総力が...
大袈裟に書いてあるようにも思えますが、米国の異常なまでの誘致、排除を考えると筆者の意見に賛同せざるを得ません。 日本においては、まだ世界のトップランナーである所をベースとして、2030年〜それ以降にかけての戦略を考える事でしょう。 岸田君の頭と胆力では無理なので、役人の総力が全てとなります。合弁させるだけで金がない(でない)では勝てません。アメリカに対して2桁落ちですから。
Posted by
ページ数もそれなりにあり、身の回りの話題でもないので、読むのに苦労するかと思ったが、書き方がとても上手い。 各国がどんな思いで、戦力物質である半導体のサプライチェーンを手にできるかと鎬を削る様子を書いている。 安全保障、経済安全保障という観点はなるほどと思った。 加工度の高...
ページ数もそれなりにあり、身の回りの話題でもないので、読むのに苦労するかと思ったが、書き方がとても上手い。 各国がどんな思いで、戦力物質である半導体のサプライチェーンを手にできるかと鎬を削る様子を書いている。 安全保障、経済安全保障という観点はなるほどと思った。 加工度の高い電子部品という観点でいくと、電池なんかも似たような構図になっているのではないかと思った。 川下に近づいた現業で、開発で先手をとるためにどうすべきか、考えさせられる。
Posted by
半導体不足というニュースを見て、なぜそれほど共有が追いつかないのか、と疑問を持っていました。本書を読んでその理由がわかりました。サプライチェーンがあまりに複雑な上、投資規模が国家規模、そして高度な技術は特定の企業がほぼ独占しています。そんな状況では、需要があるなら作ればよい、とい...
半導体不足というニュースを見て、なぜそれほど共有が追いつかないのか、と疑問を持っていました。本書を読んでその理由がわかりました。サプライチェーンがあまりに複雑な上、投資規模が国家規模、そして高度な技術は特定の企業がほぼ独占しています。そんな状況では、需要があるなら作ればよい、というわけにはいかないのだな、と納得です。 普段あたりまえに使っているデバイスに必ず使われている半導体ですが、そのサプライチェーンの裏側がこんなに面白いものだったなんて驚きです。台湾のTSMCという企業のことも知らなかったですし、そこが最先端の製造技術を独占しているなんてことも初めて知りました。この業界は技術的な難しさと投資規模の大きさによる参入障壁の高さがあり、サプライチェーンの様々な段階で各国の企業が市場を抑えようと激しい競争を繰返しています。他人事としては面白い話ですが、最前線で研究開発している企業は本当に大変そう。 参入障壁によって技術や生産能力の独占が起きる上に、それが一国の安全保障を脅かすほどの重要な産業だということで、米中を中心とした国家規模のかけひきが繰り返されています。日本の将来への希望もそれなりに書かれている本ですが、客観的に見て日本企業がその中でメジャープレイヤーになる見込みはあまりなさそうだというのがとにかく寂しいですね。
Posted by