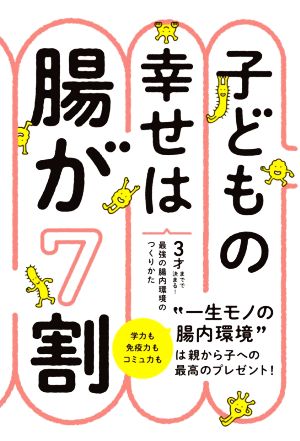子どもの幸せは腸が7割 の商品レビュー
【菌を排除することが自閉症につながる】 腸内環境に関する強めの主張が展開される1冊。 人によっては物足りないかもしれませんが、子どもの腸内環境のために、親は目を通しておいた方が良い1冊です。
Posted by
脳から腸に与えられる情報以上に腸から脳に与えられる情報の方が多く、腸内環境がその人の性格を決めていると言ってもいいほど腸の役割は大事。 セロトニンなどの幸福度に関わるホルモンも腸内細菌によって作られる。 腸のいい食べ物は ⚫︎不溶性食物繊維 さつまいも、きゃべつ、こんにゃく、玄...
脳から腸に与えられる情報以上に腸から脳に与えられる情報の方が多く、腸内環境がその人の性格を決めていると言ってもいいほど腸の役割は大事。 セロトニンなどの幸福度に関わるホルモンも腸内細菌によって作られる。 腸のいい食べ物は ⚫︎不溶性食物繊維 さつまいも、きゃべつ、こんにゃく、玄米、インゲン豆、ニラ ⚫︎水溶性食物繊維 ごぼう、キウイ、さといも、海藻、りんご、あぼかど ⚫︎発酵食品 ⚫︎きのこ類 ⚫︎オリゴ糖 バナナ、たまねぎ、とうもろこし、大豆、ながねぎ⚫︎オメガ3脂肪酸 アマニ油、青魚
Posted by
子供が生まれたばかりの頃は除菌気をつけていたけど、これを読んでからはそこまで神経質にならないことが将来の子供の健康に繋がる、と思えて気にならなくなった。
Posted by
腸活的な本は初めて読んだ。説得力がある研究を用いてわかりやすく説明されていて、勉強になったし、3歳になる前に読んでおいてよかったと思った。 以下が祖父母から「なめさせちゃダメ」等言われたときに言い返せるよう、個人的に覚えておきたい内容。 幸せになるための基本は何といっても「健...
腸活的な本は初めて読んだ。説得力がある研究を用いてわかりやすく説明されていて、勉強になったし、3歳になる前に読んでおいてよかったと思った。 以下が祖父母から「なめさせちゃダメ」等言われたときに言い返せるよう、個人的に覚えておきたい内容。 幸せになるための基本は何といっても「健康」。また。「幸せだな」と実感しながら生きていくにはドーパミンやセロトニンの「幸せ物質」が欠かせない。 腸内フローラは生まれた後に形成されるもので、遺伝の影響はほぼない。双子でも違う。どんな環境で誰に育てられるかが大きく影響。 土にいる土壌菌は腸内細菌の最大勢力、腸内に住まわせたい菌の代表。兄弟がいる赤ちゃんのほうがアレルギー症状を持つ可能性が低い結果も。 脳の発達は環境に左右される。生後3年までを「脳発達の臨界期」といいう、この時期に「感覚的経験」を数多く積むことで子供の脳は正常に発達していく。 そのために必要なのは裸足で走り回って泥んこになる等五感を使う遊びをすること。英語等の知識的な刺激を与えることではない。 「天才」と呼ばれるIQ121以上の人は7歳まではっ大脳皮質の厚さが平均より薄い。このあいだに早期教育を受けずに感覚的経験を積んだからと推測。 ペットのいる家庭で育つ赤ちゃんはアレルギーになりにくい体質に。動物園も効果的。 お母さん由来の抗体がなくなるころには、赤ちゃんは自身の免疫系を働かせて抗体を作れるようにならねば。そのためにいろいろなめて体に雑菌を取り込もうとしている。床には腸内細菌の最大勢力であり、腸内に住まわせたい菌の代表でもある日和見菌の土壌菌や大腸菌がいる。善玉菌だけを取り込んでも免疫は高まらず、少しだけ病原力のあるちょい悪金を取り込むことも必要だと赤ちゃんは知っている。 高度成長期以降、いきすぎた潔癖志向が高まり、赤ちゃんがちょい悪菌に触れる機会はどんどん少なく、免疫力を低下させるようになった。
Posted by
子供の免疫獲得、腸内細菌叢獲得のために読みました。 最初は知っている内容だったので読み飛ばしましたが、強調されている部分を読むだけでもどういう生活をさせたらいいのか、ヒントが詰まっています。
Posted by
Kindle Unlimitedだから読んだけど良かった!積極的に土に触れさせたりあんまり神経質に消毒しないようにしようと思った。 あとうんちの形や、菌育(子供への声がけ)も参考になった!もう少し話せることがわかるようになったらもっと参考にできると思う。 ただ腸で性格が変わるとか...
Kindle Unlimitedだから読んだけど良かった!積極的に土に触れさせたりあんまり神経質に消毒しないようにしようと思った。 あとうんちの形や、菌育(子供への声がけ)も参考になった!もう少し話せることがわかるようになったらもっと参考にできると思う。 ただ腸で性格が変わるとかはうーんほんとかな〜と思ったりもした笑 あまりにも腸が脳の次に大事!を押しすぎてる気もした。(ただ母数が多いかはわからないがちゃんと研究結果は出てる)
Posted by
生物学の勉強になるのはもちろんだけど、個人的には菌育の章が凄い大事だと思った。本当に未来の人のことを考えてるんだなって感動した
Posted by
この本を知り読んでみたいなーと思っていたけど、1歳半までに腸内フローラの種類が9割決まる!?という内容をちらっと知ったのが息子1歳4ヶ月の頃。 これははやく読まねば!と楽天booksでぽち。 ざっと読んで心に留まったのは、 動物と触れ合わせる 土と触れ合わせる 過度に除菌を...
この本を知り読んでみたいなーと思っていたけど、1歳半までに腸内フローラの種類が9割決まる!?という内容をちらっと知ったのが息子1歳4ヶ月の頃。 これははやく読まねば!と楽天booksでぽち。 ざっと読んで心に留まったのは、 動物と触れ合わせる 土と触れ合わせる 過度に除菌をしない こと。 我が家はペットを飼っていないので、積極的に動物園に行こう。公園も。
Posted by
母から勧められて読んだ本。 うちの子が風邪を引かないのは、やはり私が除菌出来るものを一切もっていないからかな?! …と言うのは冗談として、 結論、発酵食品を摂る、食物繊維を摂る、夕食は早く食べる、3食食べる、よく寝る、よく遊ぶ、笑う、って言う、まあ「規則正しい生活」と言うことな...
母から勧められて読んだ本。 うちの子が風邪を引かないのは、やはり私が除菌出来るものを一切もっていないからかな?! …と言うのは冗談として、 結論、発酵食品を摂る、食物繊維を摂る、夕食は早く食べる、3食食べる、よく寝る、よく遊ぶ、笑う、って言う、まあ「規則正しい生活」と言うことなのかな。 でも、いろんな菌を貰うために除菌し過ぎない!くらいは可愛いもんだけど、「自閉症の子は腸内細菌が少ない!」とか、「アレルギーは添加物のせい!」とかって、結局全部「母親責任論」になってしまわないか心配。 あなたのお子さんが自閉症なのは、3歳までの食生活が原因です。なんて言ったらどうなっちゃうのよ。。。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
オーディブルで。 本当に?と懐疑的に聞き始めたけどなるほどと思うことや大人にも参考になることがいっぱいあった。他の同種の本も読んでみたい。 ・腸は第2の脳(神経で繋がってる、ストレス等 相互に影響しやすい) ・3歳までに腸内細菌の種類が決定する その後は種類は増やせない ・腸内細菌の増やし方 ①スキンシップを行うこと(父母、祖父母、 親戚、友達との交流) ②土の上で遊ばせる(土壌菌と触れ合う) ③動物とのふれあい(動物園、ペット) ④除菌しすぎない(獲得する腸内細菌が減る、 アレルギー等にもかかりにくくなる) ⑤食べ物を意識する(野菜、豆、穀類、海藻、 発酵食品、オリゴ糖、食物繊維) ・腸内細菌が喜ぶ食べ物 善玉菌を含んでいる発酵食品(プロバイオ ティクス):納豆、ヨーグルト、漬物、味噌、 チーズ、酢、キムチ、鰹節 善玉菌を増やすオリゴ糖:大豆、ごぼう、玉ねぎ、 キャベツ、バナナ、とうもろこし、長葱 善玉菌の餌になる水溶性食物繊維:大麦、昆布、 わかめ、ひじき、里芋、りんご 腸の運動を促す不溶性食物繊維:玄米、キャベツ、 レタス、さつまいも、大豆 ・食品添加物や抗生物質は細菌を減らす ・3歳以降は細菌の種類は増えないが、既にある 細菌の数を増やすことはできる ・善玉菌(ビフィズス菌、乳酸菌etc.)を増やすこと が大事、食べ続けること。 ・善玉菌増のため生活の中で意識すると良いこと ・副交感神経(腸の働きをコントロールしている) が優位になる生活をする =生活リズムを整える(三食食べる、十分な睡眠、 適度な運動、日光浴びる) ・よく笑う 笑いがもたらすリラックスした空気が副交感 神経を優位にする、免疫力UPも出来る ・夕食は寝る2時間前に済ませる ・脳の発達は子供の頃の経験,環境に左右される。 生後3年までの"脳発達の臨界期"は知識的な 早期教育<感覚的経験※IQ121以上の天才は 7歳までは大脳皮質の厚さが平均より薄い =感覚的経験のが多く積んだからとされている ・肥満は腸内フローラの組成に影響される バクテロイデスモン>フィルミクテスモンにする ・風邪にかかりにくくするには、NK(ナチュラル キラー)細胞*を増やす、*食生活や精神的ストレス の影響を受けやすい=食生活を整えて腸内細菌を 増やし免疫細胞活性化させ神経伝達物質の合成 を促してストレス耐性のある身体を作る ・200種100兆個の腸内細菌の主な種類 ◎善玉菌:病原菌の繁殖を防ぎ免疫を高める、 消化吸収を促す、便の性質を改善するetc. ex)ビフィズス菌,乳酸菌 ◎悪玉菌:数が増え過ぎると下痢便秘肌荒れの 原因。ex)ウェルシュ菌,大腸菌(一部) ◎ひよりみ菌:多い方に加勢する、多くは土壌菌。 ex)フィルミクテスモン(太り菌), バクテロイデスモン(痩せ菌) ・理想バランスは善:悪:ひ=2:1:7
Posted by
- 1
- 2