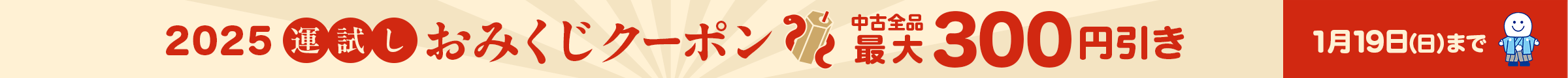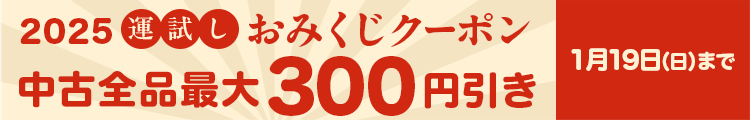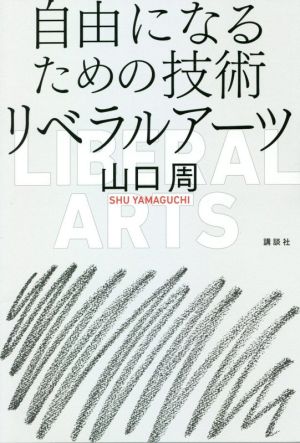自由になるための技術 リベラルアーツ の商品レビュー
どの方の対談も知らないことばかりで勉強になりましたし、山口さんの引き出しの多さは流石でした。対談という形式だからこそ、よりリベラルアーツの重要性を感じることができた気がします。
Posted by
リベラルアーツ アーツの部分が魅力的に感じる 文字、論理的 にとらわれずに言葉にできないものも含めて。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
リベラルアーツとは「自由になるための技術」。 リベラルアーツの真髄は、「問う」ための技術。 社会を生き抜くための功利的な武器になりうるのは、「なぜならイノベーションには相対化が必要だから」 →当たり前を疑う ★ただし、よく言われる「常識を疑う」でなく、「見送っていい常識」と「疑うべき常識」を見極める選択眼を持つ。 →相対化するための「知的な足腰」を得る ★それは、哲学や古典・歴史などの普遍的なスキル・知識である。 リベラルアーツは「したたかに生きる」ための足腰になる。 複雑で不安定な現代に「分析」「論理」「理性」の絶対的サイエンス重視の意思決定や方法論が限界にきており、自らの「真」「善」「美」すなわち「美意識」を鍛える。 個人のコナトゥスの発揮こそ。 縛りがない。ほどける。 1.中西輝政氏 歴史と感性 2.出口治明氏 論理的に考える力 3.橋爪大三郎氏 グローバル社会と宗教 4.平井正修氏 人として 5.菊澤研宗氏 組織の不条理 6.矢野和男氏 ポストコロナと普遍的価値 7.ヤマザキマリ氏 パンデミック後に訪れるもの 7名との対談。 ★共通して言えるのは、 「歴史」・「人」・「本」・「旅」・「哲学」・「禅 自己認識」 は絶対ということ。 現代社会では、 法が追いつかない故に実定法主義が危険であり、 「理論理性」だけでなく「実践理性」が大切。 これからより広がるであろう無連帯と幸福のあり方。その上で、リベラルアーツはやはりさらに不可欠なものとなるのであろう。 あくまでもこの書では各々のリベラルアーツの考え方であり、リベラルアーツの植え付けには、他の様々な書物を読む必要があると感じた。 各7人の書物や推薦する書物などもあり、今後はそれらを読み自身の蓄えにしていきたい。
Posted by
リベラルアーツとは、日本では教養と訳される事が多いが、本来意味するのは、「自由になるための手段」という事らしい。これが、捲って1ページ目。少し違和感があるが、リベラルアーツは、奴隷階級と自由人を区分した上で、自由人が身につけるべき3学4科の事であり、とりわけ3学が文法、修辞、論理...
リベラルアーツとは、日本では教養と訳される事が多いが、本来意味するのは、「自由になるための手段」という事らしい。これが、捲って1ページ目。少し違和感があるが、リベラルアーツは、奴隷階級と自由人を区分した上で、自由人が身につけるべき3学4科の事であり、とりわけ3学が文法、修辞、論理として思考様式に関わる学問であり、奴隷が身につけるべき技術とは一線を画すもの。やや乱暴に言えば企画職と技術職を分け、企画職が身に付けておくべき心構えや考え方のような感じか。頭のスキルと手のスキルの違い、とも言えるだろうか。同様に、ノブレスオブリージュに通底する所もあり、即ちエリートが身につけるべき教養という意味で理解をしていた。 だから、自由になるため、とか、何かを勝ち得る手段とは少し異なるし、本著で議論される、目的合理性の話や、著者自身がみっともないコンプガチャや儲け方のビジネス本に辟易してエリートの「美意識」を別で書にした、という話と矛盾する気がした。著者も結局は、そうした商業主義にリベラルアーツを利用していないだろうか。 ただ、その一点で丸ごとツマラナイという話ではなく、中西輝政との歴史話、出口治明お得意の人、旅、本。特に私には菊澤研宗との組織論の話が面白かった。山口周の本は、著者紹介的な意味合いもあるので「出会い系」のような側面があり、広がりが嬉しくもある。
Posted by
「目の前の事柄を相対化する力」 リベラルアーツを学ぶことで この力が身につくと学んだ。 高度経済成長が終わり、かつて世界を牽引していた 日本に暗黒期が到来した。 少子高齢化や、国の財源問題、単身世帯の増加や自殺数の増加が、日本という国が迷走していることを 現している。 多くの人...
「目の前の事柄を相対化する力」 リベラルアーツを学ぶことで この力が身につくと学んだ。 高度経済成長が終わり、かつて世界を牽引していた 日本に暗黒期が到来した。 少子高齢化や、国の財源問題、単身世帯の増加や自殺数の増加が、日本という国が迷走していることを 現している。 多くの人が将来に不安を 覚えなければならない状況だからこそ、 他者への気遣いなども減り、ストレスも溜まる。 そういった中で、リベラルアーツを学ぶことが、 1つの手助けになるのではないかと感じた。 今、日本の多くの人が苦しい状態にあると思うが、 その見方を変えるだけで少しは楽になるのではと思う。
Posted by
リベラルアーツを題材にした、角界の著名人と著者の対談集。 変化の激しい時代。専門知識だけで物事を判断しようとしても、新しい変化には対応しづらいし、全体の流れとは別の方向に向かう判断をしてしまうリスクもある。全体を俯瞰して、総合的に判断する力が必要であり、それを支えるのがリベラルア...
リベラルアーツを題材にした、角界の著名人と著者の対談集。 変化の激しい時代。専門知識だけで物事を判断しようとしても、新しい変化には対応しづらいし、全体の流れとは別の方向に向かう判断をしてしまうリスクもある。全体を俯瞰して、総合的に判断する力が必要であり、それを支えるのがリベラルアーツである。ということだと理解していますが、リベラルアーツという言葉がややバズワードすぎて、時間とお金に余裕のある人の、単なる絵画、音楽、文学などの趣味の領域を指すものと、単純に理解されがちな嫌いもある気がします。著者の主張はよくわかるので、ビジネスだけでなく一般人が、日々の暮らしの中で総合的な判断をするために必要となる基礎的な知識であることを、かみくだいて説くような書もぜひ出していただきたいと願います。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
VUCAの時代と言われるいまでも、多くの企業がコンサルティング会社や広告代理店に巨額の費用を支払って、「何年先にどうなるのか?」という未来予測を依頼しています。はっきり言ってそんな発想が時代遅れなのです。未来を他人に聞くのではなく、「あなたは、一体どうしたいのですか?」と、そろそろ問いそのものを変えなければならない時期に来ているのだと思います。 複雑で不安定な現代社会では、「分析」「論理」「理性」といった、これまで絶対視されてきたサイエンス重視の意思決定や方法論が限界にきていることを述べ、このような時代には、経営の判断にも、自らの「真」「善」「美」の感覚、すなわち「美意識」を鍛え、拠り所としていくことこそが重要だと訴えました。同書が幸いにも多くの読者に受け入れられたのは、私と同じような問題意識を持っている人が多かったからでしょう。(p.20) パブル経済の崩壊から三○年近くが経ったいまなお、戦後の高度経済成長があまりにも成功したために、ご指摘の製造業モデルから脱皮するのに苦労しています。一方、世界は大きく様変わりし、まったく異なる成長モデル、成功モデルが次々と生まれています。 いま、日本が行き詰まっている理由は、モノづくり信仰の一方でGDPに占める製造業の構成比が二割程度、雇用者数は約一〇○○万人で全体の一七%程度となったことからわかるように、もはや製造業では社会全体を引っ張れない状況になっていることが主因です。代わって伸びているのはサービス産業です。 また、この三〇年間、日本の正社員の労働時間はほとんど減らず、年間二〇〇〇時間前後で推移しています。にもかかわらずGDPの平均成長率は一%にとどまっている。日本と同様に少子高齢化が進行している欧州では、年間労働時間は一三〇〇~一五〇〇時間程度で平均二·五%近く成長しています。 なぜ日本でこのように成長率が低迷しているのかというと、製造業からサービス産業へと産業構造が変化しているのに、人材も働き方も製造業の工場モデルを続けているからです。サービス業で問われるのは、与えられた課題をこなす力よりも、課題を見つけ出す力、新しいサービスにつながる独創的なアイデアを生み出すカです。APUが評価されているのは、 そうした力を養うには、 とがった個性を尊重する教育に転換しなければならないということに、社会が気づき始めた証左かもしれません。(p.87,88)
Posted by
そんなに面白くない。 山口氏が本書のインタビュアーなのだが、上手く言葉を引き出せてないように感じる。そのため、よく話せる出口氏では口数が少なく、その他ではしゃべりすぎ。会話の中に教養を入れようとして必死感が感じられる。特に住職との会話は成り立ってるのか?編集者がカットしたのか? ...
そんなに面白くない。 山口氏が本書のインタビュアーなのだが、上手く言葉を引き出せてないように感じる。そのため、よく話せる出口氏では口数が少なく、その他ではしゃべりすぎ。会話の中に教養を入れようとして必死感が感じられる。特に住職との会話は成り立ってるのか?編集者がカットしたのか? 本書の貢献は出口氏と橋爪氏が9割か。筆者である必要はないと思った
Posted by
リベラルアーツを学ぶ必要性がわかった。 多様性をもつことや、誰が言ったかではなく、何を言ったのか理解する必要があることなど、先人たちが発したことを知ることが大事だ。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
読んでよかった対談本。各対談のあとに著者の振り返り、解説があるのが良い。「あぁ良い話を聴いた」で終わらず、理解を深められる。 対談相手は出口治明氏やヤマザキマリ氏など専門分野もしてきた経験も様々だ。それぞれがコロナ禍をどう見つめ、何を考えているのか。この一冊で知ることができた喜びがある。内容が濃い。正解のない時代を生きるため、自分の選択を正解にしていくために今後も考え続けたい。
Posted by