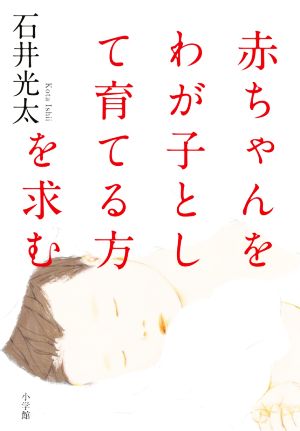赤ちゃんをわが子として育てる方を求む の商品レビュー
菊田医師、赤ちゃん斡旋という事件をネットで知った。 どのような経緯でどんな時代背景だったのかを知りたくてこの本を手にとった。 『特別養子縁組』 菊田昇医師が国に訴えてできた制度。 周りからどんなに批判されようと、産まれた赤ちゃんを当時の法律に反してでも実母の戸籍に残らないように...
菊田医師、赤ちゃん斡旋という事件をネットで知った。 どのような経緯でどんな時代背景だったのかを知りたくてこの本を手にとった。 『特別養子縁組』 菊田昇医師が国に訴えてできた制度。 周りからどんなに批判されようと、産まれた赤ちゃんを当時の法律に反してでも実母の戸籍に残らないように養子に出していた菊田医師。 そして菊田医師の考えに賛同して協力し、批判にも耐える周りの人達。 菊田医師とその方々のおかげで今もなお救われる命はたくさんある。 菊田先生、法律を変えて下さりありがとうございます。
Posted by
今まで男性は、どれだけ女性の話を聞いて来たのか。 女性だけで妊娠できると思っているのだろうか? ならば生物の創造主はなぜ男性という性を作ったのか? 女性だけで妊娠できるならば、男性はいらないだろう? その前に、未成年である母親は、散々罰を受けている。 妊娠し男に捨てられ、親に...
今まで男性は、どれだけ女性の話を聞いて来たのか。 女性だけで妊娠できると思っているのだろうか? ならば生物の創造主はなぜ男性という性を作ったのか? 女性だけで妊娠できるならば、男性はいらないだろう? その前に、未成年である母親は、散々罰を受けている。 妊娠し男に捨てられ、親に言い出せず苦しみ、産んだのに、是枝はさらに塩を塗るのか? この感情は、男には分かるまい、子宮を持たない男には一生分かるまい。 昭和30年代女はまだ男の経済力を頼りに生きて来た。 男に嫌われたら生きていけないのだ。 未婚の女が結婚するには、結婚前に別の男の子を身籠もってはいけないのだ。 妊娠中の女性の気持ち、中絶する女性の話しを男性はどれだけ聞き、気持ちを理解できたのか。 昭和55年まで日本では、妊娠7ヶ月までの中絶を認めて来た。 7ヶ月にもなったら、産声を上げる子もいたのだ。 それまでの産婦人科医は、クライアントの希望に添いその子供を殺していた。 宮城県石巻市の産婦人科医菊田昇氏は、そのことに罪悪感を感じなんとかしないといけないと感じていた。 この世に産まれることを母親、父親から拒まれた子を生ませ、不妊治療ををしている夫婦の養子にするのだ。 ただの養子ではない、母親の戸籍を汚すことなく養父母の実子として出生届を出さないといけないのだ。 さて、どうする? 当時は特別養子縁組制度がなく、実母の戸籍を通さず養子に出すことは違法だったが、菊田医師はそれを知っていて出生証明書を偽造した。公文書偽造罪だ。 しかし、子の生命は救われる。 毎日新聞の朝刊に、中絶の実態が報道される。 中絶のため、陣痛促進剤を大量に投与され強制的に早産された妊娠7ヶ月の胎児、息があってもクライアントの御所望通りに胎児をこの世から抹殺せねばならない胎児を産婦人科医は殺している。 その事実が世間に暴露され、その生きている胎児を生かせたいと思う菊田医師は、違法に出生届を出して退治を救っている。 反発したのは、本来反発してはいけない産婦人科医だった。 この件を考えると、思うことは、イグナーツ・フェルプ・センメルヴァイスのことだ。 乳児出産後、産褥熱で妊婦が死亡していた。 その原因を突き止めた医師だ。 センメルヴァイスは、1847年その原因を論文で発表した。 当時の産婦人科医は、我々が殺人者と言いたいのか、と反発した。 40年後、イギリスの医師ジョゼフ・リスターは、フェノールによる消毒法を確立した。 センメルヴァイスは、精神障害ありと精神病院でその生涯を閉じた。 ジョゼフ・リスターは、受け入れられた。 どう違うのか? 40年という月日によりモノの捉え方が変わったのか? 発表の仕方なのだろうか?
Posted by
一気に読了。特別養子縁組制度をつかみとった、菊田昇さんと、菊田さんを取り巻く名前の残らない方々をモデルにしたフィクション。 何かを自分自身が成し遂げることが大切なんではなく、無関心や思ってるだけをやめようと思った。動くこと。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
特別養子縁組の成立に貢献された、菊田昇医師の生い立ちから、法制度施行までのお話しです 望まれない赤ちゃんの命を救い、欲しくても授からない夫婦の為にもなる事なのに、当然賛成してくれると思った周りの産婦人科医師や日母などの大反対にあい、色々な試練を乗り越えられて大変なご苦労をされた事に驚きました そのお陰で救われた命が沢山あった事に感動致しました
Posted by
特別養子縁組の成立に尽力した実在する産婦人科医の人生を、フィクションも織り交ぜて纏めた物語。 妊娠する大変さを体験していると、読みながら時折涙が込み上げてきます。 当時の社会問題を理解するのにとても良い本でした。
Posted by
親から望まれない子供が生まれた場合に実子として養子縁組をする試みを始めた菊田医師のお話。遊郭の子供として生まれた幼少期から菊田昇の生涯を追う。 当時としては法律違反だったが子供を助けたい一心で行動した昇の生きざまと、特別養子縁組制度ができるまでを描いている。子供を持ちたいが不妊の...
親から望まれない子供が生まれた場合に実子として養子縁組をする試みを始めた菊田医師のお話。遊郭の子供として生まれた幼少期から菊田昇の生涯を追う。 当時としては法律違反だったが子供を助けたい一心で行動した昇の生きざまと、特別養子縁組制度ができるまでを描いている。子供を持ちたいが不妊のためうまくいかない人達はたくさんおり、一方で望まない妊娠に困る女性も多くいる。双方に有益な制度だと思うし、「子供が生まれる」ことや「子供ができる」こと、「子供を育てる」ことが当たり前だと思わずに、困っている人に目を向け、問題解決の手段を考えることの大切さを学んだ。
Posted by
特別養子縁組制度が、医師の辛い経験とそこから打ち立てられた信念で成立したことを初めて知った。 素晴らしい内容だった。
Posted by
どのくらいフィクションでどのくらいが真実なんだろう?元々特別養子縁組についてはよく知っていたし、菊田昇さんのことも知っていたけど、制度の成り立ちについて、より詳しく知れてよかった。 特別養子縁組については、大体養親目線の本が多いが、医師目線というのはなかなか新鮮だった。
Posted by
貧しさから遊郭を営まざるをえなかった家庭に生まれ、 遊女がお客をとったお金で、大学まで出してもらって、産婦人科医になった 菊田昇先生のノンフィクション。 「赤ちゃんあっせん事件」、知らなかったけど 日本にもこういう勇気と誠意のひとがいたんだって、明るい気持ちになりました。 保身...
貧しさから遊郭を営まざるをえなかった家庭に生まれ、 遊女がお客をとったお金で、大学まで出してもらって、産婦人科医になった 菊田昇先生のノンフィクション。 「赤ちゃんあっせん事件」、知らなかったけど 日本にもこういう勇気と誠意のひとがいたんだって、明るい気持ちになりました。 保身しか考えない、改正をしない無能な前例主義の面々はどこにでもいて、 それをくつがえす信念と、拡がる輪が素晴らしかったです。 家族、お友達、同僚に恵まれたのは、昇先生の人格ですね。 遠藤周作さんや三浦綾子さんの意見投稿が出てきて、 事件や時代背景が、すごく浮き上がりました。 表紙のイラストやブックデザインと、内容のタブー感(だからこその正義)の ギャップがすごい。こういう表紙にして、多数に読んでもらいたい思いも伝わってきます。 どの章もつらいけど、前半の遊郭編の悲壮感たるや。 上野千鶴子先生のフェミニズム系を読んでるくらい、考えさせられる内容です。 石井氏が参考文献として挙げられていた、菊田先生のご本も読んでみたいです。 【本文より】 「自分が思う正義を信じて、その通りに生きられる人って決して多くないと思うんです。みんな正義から目をそらして、長いものに巻かれて都合よく生きようとする。 だから、あなたみたいな方と一緒に人生を歩んだら、大変だろうけど、満足できるだろうなって思ったんです。」 「東京や横浜、それに仙台さ比べれば、たしかにちっちぇえ町だ。でも、石巻には漁港、田んぼ、工場など何でもあって、貧乏人から大金持ちまでそろってる。人間のありがたさもいやらしさも、全部手の届く範囲にある。ここほど人間臭い町はねえ」 「たとえばマタイの一節に、本当の親子っていうのは、血縁ではなく、愛情で結ばれた関係を言うんだって言葉があります。」
Posted by
この本は、フィクションなんです でも、ノンフィクションと錯覚するほどの内容です 特別養子縁組という法制度がどのようにして制定されたのか、読み進めるほどに医師の揺るぎ無い想いを感じます いったい、この医師の力でどれだけの命が救われてきたのだろうと。私も医療従事者として目の前の命を...
この本は、フィクションなんです でも、ノンフィクションと錯覚するほどの内容です 特別養子縁組という法制度がどのようにして制定されたのか、読み進めるほどに医師の揺るぎ無い想いを感じます いったい、この医師の力でどれだけの命が救われてきたのだろうと。私も医療従事者として目の前の命を救いたいと願うことは数知れず この姿勢は尊敬、という言葉では足りないくらいです フィクションはあまり好きではないという人にも事実を元にした内容なのでお勧めできる本です
Posted by