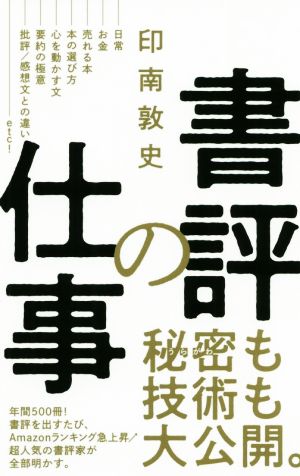書評の仕事 の商品レビュー
はじめに。が飄々としていて読み進めやすさが抜群。 「別に書評なんか書かないから関係ないや。と思われるかもしれません。たしかにそうとも言えますね。」 このくだりが非常によかったし、堅苦しくなく楽しんで欲しいというメッセージが伝わってきた。 ○書評の役割 書評の役割は、読者のために...
はじめに。が飄々としていて読み進めやすさが抜群。 「別に書評なんか書かないから関係ないや。と思われるかもしれません。たしかにそうとも言えますね。」 このくだりが非常によかったし、堅苦しくなく楽しんで欲しいというメッセージが伝わってきた。 ○書評の役割 書評の役割は、読者のために新刊の書物の内容を紹介、批評する。ものではない。 なるほど、これは面白そうな本だな。読んでみよう。と思わせることが書評の役割。 ○書評家がすべきことは2つだけ (1)伝える。伝わりやすい書き方を考えて実行する。共感をつかむ。 (2)読者の目線に立つ努力をする。 ○書評を書くための本の読み方 ・全部読む必要はない。大切なのは目的 ・目的は「これは面白そうな本だな。読んでみよう。」と思ってもらうこと ・目次を見て気になったところだけ読むのは有り ・書評目線(下記)で読む 『読者は何に興味があって何を知りたいのか』 『読者が知りたがっていて、でも知らない情報はなにか』 『多くの読者が(仕事で、プライベートで)どのようなことで悩んでいるか』 『どのような情報にそれを解決できる力があるか』 ○文章力のあげ方 ・自分の文を好きになる。好きのほうが「より良くなりたい」という思いが強い ・文章好きになるには方法論がある。好きな人(文章がうまいと思う人)の文章を覚える。これが基礎 1.とにかく色んな人の文章を読む 2.毎日毎日読み続け、そんななかから好きな書き手をみつける 3.好きな書き手の手掛けた作品をたくさん読む 4.その書き手の文章を意識しながら書く。真似する ○文章でもっとも大切な要素はリズム ・リズムは書きながら読みながら感じるしかない ・リズムを生み出すのは「。」「、」「てにおは」「行間」「漢字とカナの使い分けとこだわり」 ・結局好きな人の文章を意識して書ければリズムが身につく 本の終盤から音楽、特にラップの話に移行したのも当著の面白いところでした。 ラッパーは「おれが一番最強」「ラップがもっともうまいのは俺」という自己肯定感の高さが前提。 文章も同様に、自己肯定感を持てた人間がどんどんうまくなる。
Posted by
著者が書評を執筆する際に大切にしているや、どのような書評が読まれると感じるのか、などについて分かりやすく解説されている。著者の考え方に共感できる箇所が数多くありました。ブログ・SNSで気軽に情報発信できる現代で、とても役立つ一冊です。
Posted by
プロの文筆家である著者が、書評の手の内を明かしてくれる。 読み手のために文章を書く徹底した姿勢を貫く事の大切さを伝えてくれる。 読者へ役立つ事を伝えようとする誠実な姿勢の文章にあっという間に読んでしまう。 社内外へのプレゼンに使え、ビジネス書としても充分な知識になる。 文章がヘ...
プロの文筆家である著者が、書評の手の内を明かしてくれる。 読み手のために文章を書く徹底した姿勢を貫く事の大切さを伝えてくれる。 読者へ役立つ事を伝えようとする誠実な姿勢の文章にあっという間に読んでしまう。 社内外へのプレゼンに使え、ビジネス書としても充分な知識になる。 文章がヘタクソすぎて、イヤな自分に希望をもらえた作品。
Posted by
もう少しハッとさせられるようなことや新しい気づきみたいなものを知る事ができるかも知れないと思っていたから、そこは少し期待外れだった。 でも、書評に限らず、物事を要約すると(要約する力をつけられると)得られるメリットについては、なるほどなと思わされた。
Posted by
驚くような秘策などは登場しなかったが、それがかえって書評のプロの仕事を感じさせた。 まず、とにかくスラスラと読めてしまう文章がすごい。言葉の選び方や句読点の打ち方等、読みやすい文章の条件が整っているからだろう。 そんな読者目線に立った文章を書く筆者が、書評を書く上で意識しているこ...
驚くような秘策などは登場しなかったが、それがかえって書評のプロの仕事を感じさせた。 まず、とにかくスラスラと読めてしまう文章がすごい。言葉の選び方や句読点の打ち方等、読みやすい文章の条件が整っているからだろう。 そんな読者目線に立った文章を書く筆者が、書評を書く上で意識していること。読者に読んでもらうという目的意識を踏まえつつ、個人的な考えの織り交ぜ方に注意を払う。言葉にしてしまうと地味だが、そのバランスは非常に難しく、そこにプロの力が込められている。 1日に何冊も読み、書く。それを毎日続ける。 その継続力は、書評を書くことが「好き」だからだそうだ。 「好き」×「人(読者)のため」が書評の仕事。自分に驕らず、人に寄り添える。それがプロなのだろう。
Posted by
書評家の仕事といので気になった。書評だけではなく、プレゼンや資料作成、情報収集などのヒントにもなると思われる。 文章はリズムが大事と言うことは、語尾を変える、句読点の位置を考えるくらいしか考えたことが無かったので、参考になった。
Posted by
200903*読了 図書館でふと目に止まって、「そういえば書評家の仕事ってなんだろう」と気になったのがきっかけ。 書評家は本が好きな人なら一度は憧れる職業だと思います。 一日のスケジュールや本の読み方も興味深く読めましたし、書評・文章の書き方や本の選び方はとても勉強になりました。...
200903*読了 図書館でふと目に止まって、「そういえば書評家の仕事ってなんだろう」と気になったのがきっかけ。 書評家は本が好きな人なら一度は憧れる職業だと思います。 一日のスケジュールや本の読み方も興味深く読めましたし、書評・文章の書き方や本の選び方はとても勉強になりました。 時代も違うし、立場も違うので、書評家になりたいです!と言ったからなれる、というわけではないけれど、これだけインターネットが発達しているからこそ、書こうと思えばいつでも書けるし、どれだけだって書ける。自分の熱意次第なのだな、と気付かされました。 できない、やらない理由を考えるよりも、やってみた方がいい。それが本好きとしての楽しみであり、喜びであるように思えたので、早速、読書専用のTwitterアカウントを作りました。 本好きな人たちの感想や書評を読み、本好きな人たちと語り合いたい。それが容易にできるのが、この時代のすばらしいところだと思います。 印南さんによって、自分は本が好きなんだ、という情熱を再認識させていただきました。
Posted by
2020年27冊目。 年間500本という書評量に驚き(僕だったら読むだけでも何年かかるか...)、気になって読んでみた。 「ライフハッカー」「東洋経済オンライン」「ニューズウィーク」など、様々な媒体を通じて多様な読者層に向けて書評を書く印南さんは、書評の在り方に2種類の命名を...
2020年27冊目。 年間500本という書評量に驚き(僕だったら読むだけでも何年かかるか...)、気になって読んでみた。 「ライフハッカー」「東洋経済オンライン」「ニューズウィーク」など、様々な媒体を通じて多様な読者層に向けて書評を書く印南さんは、書評の在り方に2種類の命名をし、その変遷を語っている。一つは、新聞や雑誌などの紙媒体で綴られる、やや難度の高い従来の「トラッド書評」。もう一つは、ウェブ上に現れてきた比較的気軽に読める「ネオ書評」。 『新明解国語辞典』第七版によれば、書評とは「新刊の書物の内容を紹介・批評した文章」のこと。トラッド書評の敷居の高さでは、その「紹介」の役割(読者が読んでみたいと思うこと)は果たせていないのではないか、というのが印南さん主張だったように思う。 だから、印南さんの書評の書き方はかなりマーケット寄りである印象を受けた。読者層を特定し、その人たちがいまどんな情報を必要としていて、そこに対してどんなコンテンツをどう届けるか。大事なのはその部分だから、書評のなかに「自分」をあまり出さないようにしているという。この本には、そのような書き方のためのステップも紹介されている。 本書を読んでいて考えをめぐらせたのは、僕にとって「理想的な書評とはどんなものなのだろうか」ということだった。これは良い悪いの話ではなく個人の好みの問題なのだけど、僕は本書で紹介されるタイプの書評のあり方にそこまでひかれなかった。 要点を伝える書評を数多く書くために飛ばし読みをし、客観的な必要性を感じる部分だけを抜粋していく...というあり方に、個人的にはあまり愛を感じられなかった(それでも、そういう本の紹介から「これ読んでみたい」と思うことはもちろんある)。それよりも、本当にその本に惚れ込んで没頭して読んだ人が、「その人にとってどう響いたのか」という主観たっぷりに書いたもののほうが、読んでいて興奮するし、その本を手にとってみたいと僕は感じる(もちろん、主観のみで読者が置いてけぼりになっているものは違うと思うけれど)。 書評とはなんなのだろうか。「評」とついているからには、単なる本の紹介のことではなく、程度の差こそあれその本に対する価値判断が入っているものなのではないか、というような印象を受ける。今後自分が書評を書くときに、どんなことを大事にしたいか、一度整理してみたいと思った。そのきっかけをもらえてよかった。 (ちなみに僕がこのブクログに書いているのは「書評」ではないと思っています。メインは自分の感想と思考の拡散。自分で後から見返すことが主な用途。そこに、もし読んでくださった方がいるのならば...という程度の気持ちで、内容紹介やおすすめの気持ちを添えている、という感じ)
Posted by
私がここブクログで書いているような読書メモとは異なる「職業としての書評」にまつわる本である。 ここに読書メモを書くようになり、多少なりともアウトプットを意識して本が読めるようになった。私自身、読書の質が上がったと感じている。 ただ、職業として書評を書くことは、やはり読書メモを...
私がここブクログで書いているような読書メモとは異なる「職業としての書評」にまつわる本である。 ここに読書メモを書くようになり、多少なりともアウトプットを意識して本が読めるようになった。私自身、読書の質が上がったと感じている。 ただ、職業として書評を書くことは、やはり読書メモを残すことと根本的に異なるものである、ということも感じた点の一つである。 私が「書評」を書く場合、ここに書くものとはまた違った視点で書き、おそらくこことは別の媒体で始めなければいけないのだろうな、とも思う。
Posted by
レビューを拝見して知った本です。ありがとうございます。 ブクログに投稿を始めて、あとひと月ほどで、2年になります。 ちょうど、1年前の1年を過ぎた頃には豊崎由美さんの『ニッポンの書評』を拝読しましたが、またこの節目に、このような書評についての本を拝読できて、モチベーションアップ...
レビューを拝見して知った本です。ありがとうございます。 ブクログに投稿を始めて、あとひと月ほどで、2年になります。 ちょうど、1年前の1年を過ぎた頃には豊崎由美さんの『ニッポンの書評』を拝読しましたが、またこの節目に、このような書評についての本を拝読できて、モチベーションアップ、気持ちの切り替えに、ちょうどよかったと思います。 こちらの『書評の仕事』の方が『ニッポンの書評』より基本的なことが丁寧に書かれていて初心者向けの、教科書的な本かと思いました。(タイトルが『書評の仕事』なので、プロの書評家を目指す方向けに?ギャラのことなども載ってはいますが) ブクログに投稿する上で役にたちそうなこともたくさん載っています。 その中からピックアップすると。 ●書評家としての視点 ●「人の心をつかむ/動かす」文とは ●年間500冊の書評で得た「要約力」 ●読まれる書評・読まれない書評、違いは ●読まれる書評を書く人の視点 ●書評とネタばらし ●文章力より大切なこと ●書評を書く際に忘れるべきでないこと 1:書きたいことを書く 2:伝わるように書く 3:リズム感を持たせる 4:常に疑問を抱く 5:驕らない その他にも文章力の養い方などの基礎的な項目も載っています。 私も、ありがたいことにフォロワーさんがこのところ増えてくださり、いいね!も自分の実力以上に、身に余るくらい、いただけるようになりましたが、それは決してレビューがよいからではなく、フォロワーの皆さまのあたたかい御厚意の上に成り立っているものだと感謝しています。 こういう貴重なる「書評の書き方」やさらなる読書で、勉強して、決して驕らずに、皆さまに少しでも気持ちよく読んでいただけるレビューを目指して精進していきたいと思っています。
Posted by