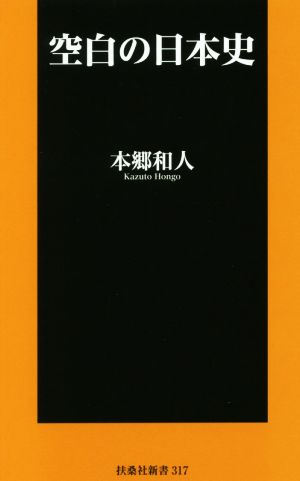空白の日本史 の商品レビュー
歴史の見方というか、視点が広がった気がした。 面白かったのは、三種の神器が実は複数セット存在するという点。 深く考えたことなかったけれど、言われてみれば……という。 そう、まさに「深く考えたことなかったけど、落ち着いて考えてみれば」なネタが多かった気がする。 常識だと思っていた歴...
歴史の見方というか、視点が広がった気がした。 面白かったのは、三種の神器が実は複数セット存在するという点。 深く考えたことなかったけれど、言われてみれば……という。 そう、まさに「深く考えたことなかったけど、落ち着いて考えてみれば」なネタが多かった気がする。 常識だと思っていた歴史観を改めたい方は是非。
Posted by
天皇は1000年伊勢神宮に行かなかった、たしかに! 何事も常識を疑ってみることで、今膠着している問題が解決できるかな?と思いました。 でも、伊勢神宮は大切な重要な場所!
Posted by
これまで当たり前の常識として捉えられてきた日本史の中に潜む「歴史的空白」に焦点を当て、歴史上の文献資料のいくつもの「空白」を紐解くことで、新たな「日本」という国の歴史像を浮かび上がらせ、いままでの「常識」が、まったく当たり前ではなくなる、そんな歴史の「穴」を検証した入門書。 飛鳥...
これまで当たり前の常識として捉えられてきた日本史の中に潜む「歴史的空白」に焦点を当て、歴史上の文献資料のいくつもの「空白」を紐解くことで、新たな「日本」という国の歴史像を浮かび上がらせ、いままでの「常識」が、まったく当たり前ではなくなる、そんな歴史の「穴」を検証した入門書。 飛鳥時代に持統天皇が伊勢神宮を参拝した後、再び明治天皇が公式に伊勢神宮への参拝を開始するまでの約千年の空白、「三種の神器」の矛盾点、「神仏分離」の誤認と「廃仏毀釈」、『吾妻鑑』に記されなかった源頼朝と上総介広常の死など・・・。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
いつものように本郷和人先生の歴史知識がアップデートされていないにもかかわらず諸説暴論を吐き散らかす一冊だと思っていた(実際そうでした) 知り得た一つの妄言パターンとして、古い通説に対して本郷先生の考える「普通こうだよね」という異物を撒いておき、色々と書いている もう一つ気が付いた点は皇室にたいして畏敬の念を持ち合わせぬ危険人物だと分かる 「女性史の空白」にて性のありようから万世一系なんてホントかよとクサし、管野スガの恋人幸徳秋水の考えとして代弁させているが「北朝は偽物だから殺して良い」と大逆事件に託けて皇室への不敬を本書では繰り返し記述している 本郷和人の正体を見た(´・ω・`)妄想
Posted by
令和2年コロナ騒動がやってくる前の2月頃に読み終わった本ですが、年末の部屋の大掃除で見つけた本です。この数年追いかけている本郷氏による本であることと、タイトルの面白さに惹かれて購入したのを覚えています。 この本では、なぜその事件は起きたのか、納得のいく説明がなされています。一つ...
令和2年コロナ騒動がやってくる前の2月頃に読み終わった本ですが、年末の部屋の大掃除で見つけた本です。この数年追いかけている本郷氏による本であることと、タイトルの面白さに惹かれて購入したのを覚えています。 この本では、なぜその事件は起きたのか、納得のいく説明がなされています。一つ一つ、膨大な文献を読みこなして達成された物だと思います。多くの時間を費やした上に、わかりやすく解説してくれた内容を読める幸せを感じます。 以下は気になったポイントです。 ・平安時代から江戸時代にかけて歴代天皇が伊勢神宮を参拝したという記録は残っていない、飛鳥時代に持統天皇が参拝した後、再び明治天皇が公式に参拝するまで、約1000年の時間が空いている。神道には1000年近くの空白の期間が存在する(p4) ・日本の神話に登場する神の種類は大きく2つに分けられる、一つは、天照大神を中心とした高天原の神々「天津神」、もう一つは、出雲の大国主など天孫降臨以前から日本にいる土着の神々「国津神」(p20) ・天武天皇は近畿につながる道に3つの関をおいた、1)北陸道を抑えるため、福井県に置いた「愛発関」、2)東山道を抑える岐阜県の「不破関」、3)関東と近畿地方を結ぶ東海道には、三重県に「鈴鹿関」、この3つを総称して「三関」という)(p28)三関の東、という意味で「関東=関の東側で田舎で辺境の地」という言葉が使われ始めたのは700年位から、関西という言葉が使われるようになったのは、明治時代以降である。関の西側は自分たちの日本なのでわざわざ呼称する必要がなかったから(p29) ・陸の奥にある場所=陸奥、陸奥に隣接する「毛の国」=上野(群馬)、下野(栃木)や「越の国」=越前(福井)、越中(富山)、越後(新潟)であった。(p31) ・紀元前660年1月1日こそが日本建国の日となった、1回目の辛酉(かののとり)の大革命では神武天皇の即位、二回目に聖徳太子が国を作ったとして、神武天皇即位を起点とした「皇紀」が誕生した。これは太陰暦なので、太陽暦に直すと2月11日となる。明治6年(1873)を紀元節とした(p47) ・中世における日本では、どう考えても神道より仏教の方が優勢であった。天皇の息子=親王は宗教界に入る際には、仏教の道に進む。摂関家や貴族出身の僧侶がたくさんいた。仏教の道に入ってから、入道新王や法親王になった人物はごまんといるが、反対は誰もいない。(p65) ・太平記を素直に読むと、三種の神器は、北陸にある1セット、後醍醐天皇から北朝に渡された1セット、天皇が吉野に持っていった1セットの合計3セットある。北陸に渡った1セットは戦乱の中で失われてしまい不明、南朝の後亀山天皇が北朝の後小松天皇に渡したのが、もともと難聴が持っていたものか、北朝から奪ったものか不明である(p77)本当の三種の神器を持っている南朝の天皇こそが正統であるという明治政府の見解が今まで引き継がれている(p78) ・神と仏の両者が手を携え、国家を守る「鎮護国家」、そして天皇の健康を守る「玉体安穏」という考え方が日本では親しまれている。他には「本地垂迹」これは、日本の有名な神様と仏様を同一視するもの。例えば、天照大神は仏の姿になると真言宗の一番偉い仏様である「大日如来」、逆に大日如来が日本に姿を表すときには天照大神の姿をとると考えられた(p87) ・秀吉がキリスト教を嫌い弾圧に踏み切ったのも、一向宗とキリスト教の教義が非常に似たスタイルであったから。阿弥陀様とキリスト、どちらも対象は違えども頭を下げる相手は現実の天下人でないので。この思想は江戸幕府にも受け継がれる(p93) ・日本から宋への往路では、材木を重石にできるが、問題は帰路。重石代わりに用いられたのが、宋銭であった(p124) ・摂関政治では、摂政や関白になれるのは「母方の親戚」である、祖父が権力を持つこともあれば叔父や伯父が権力を持つこともある。ところが平安後期になると摂関政治に代わって登場するのが院政である。院政は母方ではなく、父方の祖父、つまり天皇の祖父である先の天皇が天皇家の家父長として力を持つという形式を取る。これは婚姻形態が代わった(婿取り婚から嫁取り婚)のとほぼ同じ時期である(p208) 2020年12月29日作成
Posted by
三種の神器の話が,大変印象に残りました。 今,伝わっている神器が本物かどうかはともかく,我々が決して目にすることができない宝物だけに,歴史の中で果たしてきた役割に,神秘と悠久のときを感じました。 その他のテーマも含めて,ちょっと変わった視点から日本史を考えることのできる,興味...
三種の神器の話が,大変印象に残りました。 今,伝わっている神器が本物かどうかはともかく,我々が決して目にすることができない宝物だけに,歴史の中で果たしてきた役割に,神秘と悠久のときを感じました。 その他のテーマも含めて,ちょっと変わった視点から日本史を考えることのできる,興味深い本です。
Posted by
量産体制に入っている本郷先生の新作。「空白」というお題が良かったか、意外に読ませる(ザクじゃなくてグフくらい?)。
Posted by
日本史の空白にスポットを当てて、教科書で習う歴史の点と点を結ぼうとするこころみ。とても読みやすいので、サクサク読み進められる。 同じ事実であっても、その解釈、立ち位置によって違うようみ見えてしまうというところが面白い。世の中に出回っている様々な歴史本の解釈を楽しむのも良いが、その...
日本史の空白にスポットを当てて、教科書で習う歴史の点と点を結ぼうとするこころみ。とても読みやすいので、サクサク読み進められる。 同じ事実であっても、その解釈、立ち位置によって違うようみ見えてしまうというところが面白い。世の中に出回っている様々な歴史本の解釈を楽しむのも良いが、その中から事実は何か?を読み解くのも面白いのではないかと思った。また、同じ事実でも自分なりの解釈を持つのも一つの勉強になるのではないかと、別の観点でも学ぶことがあって有意義でした。
Posted by
歴史家である本著者本郷和人氏は色々な評価がある方だと存じ上げておりますが、私個人としては歴史を面白くさせてくれる稀有な歴史家さんで割と好きです。そして対極である呉座勇一さん、そうバカ売れした『応仁の乱』『陰謀の日本中世史』の著作さんですねぇ、氏は資料を元に陰謀論に与せず淡々と事実...
歴史家である本著者本郷和人氏は色々な評価がある方だと存じ上げておりますが、私個人としては歴史を面白くさせてくれる稀有な歴史家さんで割と好きです。そして対極である呉座勇一さん、そうバカ売れした『応仁の乱』『陰謀の日本中世史』の著作さんですねぇ、氏は資料を元に陰謀論に与せず淡々と事実のみで歴史を解説、解読してくれる、これもまた面白い歴史家さんで、この方の解説は歴史を読み解く視点以外に地震兵器とかフリーメイスンとか未だ陰謀論に右往左往している馬鹿をあっさり一刀両断してくるファクトフルネス的なハンス•ロスリング的で尊敬しております。 で、呉座氏は本著と全く関係ないです。すみません。本郷氏は正確な歴史資料の無い歴史的事案を自身の思い込み、いや違う、勉強と経験から来る直感で、この事案にはこう言う背景があって、この当時の人間だからこそこのような考え方を持っており、結果この様な事件が起きたと、非常に面白く読み解いてくれます。 今回は『空白の日本史』です。まさに、空白だからこそ色んなタブーについて、自身の思い込み、いや違う、読者も納得する説を解いてくれます。陰謀論じゃないです。ロスチャイルドは出ません。 三種の神器は3セットある話は非常に面白いし(草薙剣はやっぱないよねー)、江戸時代までの奔放な日本人の性については確実に学校では教えてくれないでしょう。 裏日本史たがらこそ面白いんです。新事実によりこの本郷氏の説が変わったとしても、こう言う面白い解説、評価を知って少しでも日本史好きを増やして頂き、後で呉座氏に修正して頂ければよろしいのではないでしょうか。 因み日本史専攻であったパパの娘は理系です。 本当にありがとうございました。
Posted by
興味深かったもの 三種の神器、伊勢神宮と皇室の関係 令和に改元し、関連行事もあり、今にぴったりの本だった。 たしかに参考文献載ってなかった!
Posted by
- 1
- 2