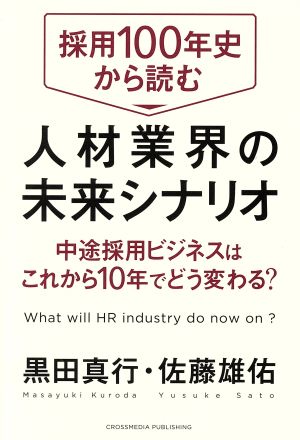採用100年史から読む人材業界の未来シナリオ の商品レビュー
人材業界の人にとっては既に知っている情報が多い。前半の歴史の変遷はなかなかよくまとまっている。 ・企業は優秀な人材をいかにやすく手っ取り早く採用できるかを考えている ・AIにとってかわれないスキルを培うことが重要 このあたりを改めて再認識した。
Posted by
・今後、企業が人材を採用する媒体は、 アグリゲーション→ダイレクトソーシング→人材紹介の優先度にシフトしていく。
Posted by
人材業界で働く人には必読書。 採用の歴史を振り返りながら、人材業界の未来にも焦点を当て述べられている。 個人的には ・ヘッドハンターがどのようにして生まれたのか ・indeedの強さ などはとても面白かった。
Posted by
【概要】 序章:採用支援ビジネスをとりまく全体像 第1章:職業選択の広がりと採用ビジネスの100年 第2章:求人広告と人材紹介、2つの人材ビジネスの誕生 第3章:リクルーティングビジネスにおけるビジネスモデル変遷 第4章:リクルーティングビジネスの新潮流 第5章:人材業界のディス...
【概要】 序章:採用支援ビジネスをとりまく全体像 第1章:職業選択の広がりと採用ビジネスの100年 第2章:求人広告と人材紹介、2つの人材ビジネスの誕生 第3章:リクルーティングビジネスにおけるビジネスモデル変遷 第4章:リクルーティングビジネスの新潮流 第5章:人材業界のディスラプター 第6章:人事採用部門は変化にどう対応すべきなのか? 第7章:リクルーティングビジネスの未来シナリオ 【まとめ】 新卒採用の始まりは19世紀に大学が発祥し、財閥企業の三菱が新規大学卒業者の定期採用をスタートさせたのが始まりというのは興味深い。その後、就活解禁などのいわゆる就活スケジュールが始まったのは、20世紀半ばのことである。 人材紹介の始まりは江戸時代の口入屋という人材の周旋業者であり、求人広告の始まりは明治時代の新聞に載った乳母の募集のもので、それらの歴史はかなり深いことがわかって面白かった。 その後1960年に現在のリクルート社が創業され、ビジネスとして求人広告が始まる。その後その市場を大きくさせたのも、今では当たり前の求人票の必須項目などを定めたのもリクルート社であった。 その後2010年以降、情報環境の変化によってリファラル採用などSNSでのリクルーティングが普及。 人材紹介業としては、戦後の職業安定法制定により確立されていく。その背景には、戦後発生した大量の失業者の存在がある。その後1997年の規制緩和により市場規模が急増する。そして人材紹介ビジネスとしての始まりも、現在のリクルート社。当初はヘッドハンティングを中心に人材紹介は広がる。 人材派遣に関しても発端は明治だが、搾取や劣悪な労働環境などが問題となっていて、その後派遣法など数年にわたって法整備されながら整えられていく。 その後求人広告においては、求職者価値を向上させ求職者がより多く集まるとプラットフォームにしていくことを追求、人材紹介においては企業価値向上に力点を置き、企業の課題や不満に対してクリアしていくことに注力された。 インターン先の仕事の関係で、ATSにはかなり馴染みがあるため、ATSの歴史は興味深かった。それは、採用頻度が少ない中小企業も含めた求人企業側との接点拡充、ネットワークを狙って作られたという背景であり、かなり理解と納得ができた。 適切な会社、ポジションに適切な人材を配置するという、企業と人材のフィッティング制度の向上を、業界を挙げて取り組む、という鈴木さんの言葉もメモ。採用面談の頃から社員さんも話しており、業界として良くしていこうという姿勢がとても好きです。 そして最後には未来のリクルーティングビジネスのあり方が述べられている。2030年のメイントピックは、さらなる少子高齢化と、テクノロジーの進化だと言われる。少子高齢化によりさらなる人材獲得難となり、同時にビジネスのスピードが増し企業の平均寿命は短くなり、より一層、終身雇用により一社でキャリアを積むことは難しくなる。また、テクノロジーの進化により日本の就業者のうち49パーセントが人工知能やロボットで代替可能となり、仕事がなくなると言われている。テクノロジーの進化により新たな仕事が生まれることになるだろうが、進化に対応することが必要である。 【感じたこと】 主に情報化社会が始まってからの人材業界の歴史を知ることができた。こんなに知識を一つにまとめてある本はなかなかないと思う。これから人材業界で働くに当たって前提となる知識だと思うので、入社までに軽くもう一周読んでおきたい。 また、印象深いのは、本の冒頭にも出てきた、リクルート草創期編集長神山さんの言葉である。それは、会社を辞めた人を脱落者扱いする社会への義憤があり、堂々とやり直しができる当たり前の社会を作りたかった、というもの。これと鈴木さんのお言葉と合わせて、誰もが仕事に対して生き生きとやりがいを持って取り組むためには、辞めるという選択も必要であり、ポジティブな転職ならなお良いが、例えネガティブな転職でも、誰でもやり直しができる。そのために人材業があり、人材業で働く人たちは転職者にとって適切で、やりがいを感じられる会社やポジションを見つける手助けをする必要性がある、と改めて強く感じました。社会人になる前に、改めてなぜ自分はこの業界、この会社を選んだのかを考えさせられる良い機会となりました。
Posted by
■面白い点 ・人材業界の歴史が社会変化と合わせてまとめてある点→社会変化とはたらくの関連性の深さを感じる。特に第二次世界大戦前後の所。 ■うーんな点 ・リクルート、ミイダスに話が寄りすぎている。協力者が偏っている。 ・これからの人事がやるべきこともよく言われている「選ばれる存在...
■面白い点 ・人材業界の歴史が社会変化と合わせてまとめてある点→社会変化とはたらくの関連性の深さを感じる。特に第二次世界大戦前後の所。 ■うーんな点 ・リクルート、ミイダスに話が寄りすぎている。協力者が偏っている。 ・これからの人事がやるべきこともよく言われている「選ばれる存在へ」という普遍化されたメッセージ性 ▼まとめ ・歴史についてはもう少し語れるように、要約やまとめを見てみる
Posted by
ただのウィキペディア。昔の軌跡や、構造整理。 新しい未来の姿は読みとけない。 メモ - ビズリーチ他の主要メディアでのコメントをすることは、ブランディングに直結しうる - 求人票にコンピテンシー、会社ストーリーを入れ込む必要があり、クルデンシャルも一新すべき。マインドとしては営...
ただのウィキペディア。昔の軌跡や、構造整理。 新しい未来の姿は読みとけない。 メモ - ビズリーチ他の主要メディアでのコメントをすることは、ブランディングに直結しうる - 求人票にコンピテンシー、会社ストーリーを入れ込む必要があり、クルデンシャルも一新すべき。マインドとしては営業。エージェントに優先企業にしてもらう必要ぎある。
Posted by
人材ビジネスで飯を食っている身として、読んでおいて損は無い本。各サービスの成り立ちや、現状の立ち位置が整理できる。
Posted by