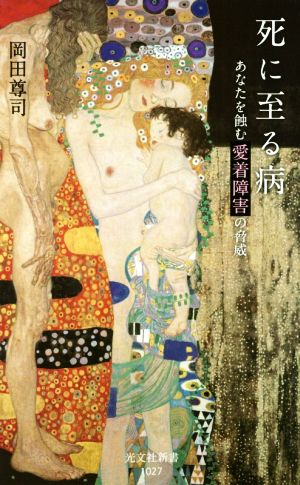死に至る病 の商品レビュー
前半を読んでいるうちは、「科学的ではない」お話だなぁ、と感じるところが多かった。 母親との愛着ばかりに何故か着目し、父親、あるいはその他の周囲の人との関係に関する話、分析が全く出てこないところなどは、その姿勢の偏りだけで、この内容を読み進める価値がないのではないか、と思ったほどだ...
前半を読んでいるうちは、「科学的ではない」お話だなぁ、と感じるところが多かった。 母親との愛着ばかりに何故か着目し、父親、あるいはその他の周囲の人との関係に関する話、分析が全く出てこないところなどは、その姿勢の偏りだけで、この内容を読み進める価値がないのではないか、と思ったほどだった。 しかし、実のところ、自分自身も、直感的には著者と同種の感覚を持っていたこともあり、読み進めたところ、共感する部分が多く、読後感としては、そのとおりと腑に落ちるものだった。 P99前後の「例えば、幸福になるという一事をとってみても、生物学的な仕組みを超えることはできない。」というあたり、正にそのとおりと思う。 自然に設計された、与えられた肉体で生きていく以上、感覚、幸せの源はロジックや正義では説明できない、与えられた肉体、頭脳が勝手に感じるものでしかないはず。 だから、その法則を理解し、それを前提として、上手にコントロール可能なことがらをコントロールしていくことが、幸せにつながる、ということだと思う。 例えば、ポリコレに沿うことは、多くの人の幸せにはつながらないのではないか、と思う。 昨今、喧しいポリコレが鬱陶しいが、その鬱陶しさを中和する良著でした。
Posted by
後半の愛着障害を克服するために必要な「認知的共感性(メンタライゼーション)」の記述が興味深かった。 安全基地の記述に関して、自分の言動にも重なる点がありもっと認知的共感性を身につけていきたいと考えた。 ただ愛着障害の原因が母親の方に偏った記述だったのが気になった。母親を両親と置...
後半の愛着障害を克服するために必要な「認知的共感性(メンタライゼーション)」の記述が興味深かった。 安全基地の記述に関して、自分の言動にも重なる点がありもっと認知的共感性を身につけていきたいと考えた。 ただ愛着障害の原因が母親の方に偏った記述だったのが気になった。母親を両親と置き換えた方が良いのでは?
Posted by
一見するとADHDのようなものも、それは生来の愛着から形成されたものが理由かもしれない。 生きづらさという誰しもが抱えていることを「愛着障害」という切り口で分析するのは読んでて面白かった。 かくいう私もコミュニケーションがうまく取れないことが多く、ADHDではと勝手に思っていたが...
一見するとADHDのようなものも、それは生来の愛着から形成されたものが理由かもしれない。 生きづらさという誰しもが抱えていることを「愛着障害」という切り口で分析するのは読んでて面白かった。 かくいう私もコミュニケーションがうまく取れないことが多く、ADHDではと勝手に思っていたが、この本を読んでから自分という人間が形成された過程を思い起こしていた。 ただ、もう少しこの愛着障害の克服を具体例をもって記載してほしかった。 生まれてから最も生き残りやすい方法で人格が形成されていくことは、親という安全地帯が正常に機能しているかどうかで愛着障害になるかが決まってくる。 求めにすぐに応じるのではなく、基本すぐに応じるだけで、すぐに対応できないこともあるくらいの距離感という一文が印象に残った。 そのくらいの距離感を手探りながら探したい。
Posted by
名著。社会の課題、闇の問題に精神科医として言葉のメスを入れた。世話をする仕組みを維持することが、生きることに意味を持つ社会を作るのにもっとも重要であるとのお話に心から同意する。 この本に出会えてよかった。何度も読み返したい。
Posted by
愛着の問題が色々な精神障害に起因する事が実例から学べて良かった。 独身者の増加は人との関わりが消極的になったことからで愛着の問題でもあるいう推測は面白い。 愛着障害は発達障害A.D.HDとの誤診されやすいようだがASDに関する情報はなかった。
Posted by
個人的に、『誰が国語力を殺すのか』(石井光太著)で書かれていた国語力の衰えと共に、現代社会の根底にある問題だと思っているのが『愛着障害』です。 本書より… ○死に至る病とは絶望のことである、と、かつて哲学者キルケゴールは書いた。絶望とは、神を信じられないことを意味した。だが...
個人的に、『誰が国語力を殺すのか』(石井光太著)で書かれていた国語力の衰えと共に、現代社会の根底にある問題だと思っているのが『愛着障害』です。 本書より… ○死に至る病とは絶望のことである、と、かつて哲学者キルケゴールは書いた。絶望とは、神を信じられないことを意味した。だが今日、死に至る病の正体は、「親の愛さえも信じられない」こと、つまり「愛着障害」にほかならない。 数年前から自分の生きづらさは、「愛着障害」にあるのではないかと、岡田尊司さんの数ある著書を読んで思っていました。ただ、先日読んだ、『愛着障害は何歳からでも必ず修復できる』(米澤好史著)を読んで、岡田尊司さんとは愛着障害の捉え方がかなり違うように感じ、愛着障害ではないのかな?と混乱していました。 今回改めて岡田尊司さんのこの本を読んで、やはり岡田さんが考えている愛着障害というものだろうとは思いましたが、自分の問題としてだけではなく、社会全体の深刻な問題として、捉え直しました。 愛着の基盤となるのが、幼い頃の(主に)母親との関わりで、その関係性が安全地帯になることで、十分な愛着が自然と養われ、その人の土台となっていくそうです。 作者はまた、大人のADHDは子供のADHDとは違い、発達障害ではなく、愛着障害による物だと訴えています。子供のADHDの治療について気をつけるべきことも書かれているので、興味のある方は是非読んで欲しいです。 愛着障害は次の世代へとどんどん受け継がれ、更に大きな生きづらさになって発現します。愛着障害は回避型、不安型など、色々な型があり、それぞれ性質が違うので、この本を読んで学びとなることはその人により異なると思われます。 ここでは、私自身が子育てをする上で、自分にとって大切と思った所を抜粋します。 ○親としては一生懸命育ててきたつもりなのに、しばしば共通する課題として浮かび上がるのは、共感性の問題である。 その最大の原因は、子供が何を感じ、何を求め、何を嫌がっているのか、という本人の視点ではなく、将来のために、あるいは本人のために、あるいは、世間体のために、これをすることが必要であり、正しいことであるという親が抱いた基準や期待に沿って、本人を動かそうとしているということである。 そこでは、本人の気持ちよりも、親側の思いが優先されている。そして、親は子供よりも、賢明な方法や正しいことを知っているのだから、それを子供に求めるのは当然だと思っている。ここで欠如しているのは、共感性なのである。子供のために有利だと思って、いつの間にか自分の判断をしつけてしまう親に共通するのは、共感性がとても弱いということである。 障害と聞くと、そんなものは自分や子供には関係ないと思われる方も多数いらっしゃると思います。しかし、この本を読むと、決して特別なことではなく、時代と共に愛着障害を起こしやすい社会になり、おこるべきしておきた弊害である事に気づくと思います。そして、社会の流れを修正していく助けになるのではと思います。これから親になる世代の方にも是非読んで欲しいと思いました。
Posted by
なんだろう。頭では理解できても感情的に受け入れられないでいる。喪の作業とか、執着しないとか、そういう話かと思ったら真逆で、この世界に生きる意味を見出していくような話。難しいけど大切なことだ、と頭では理解できるんだけど。
Posted by
愛着障害には2つの種類がある。ひとつは回避型で、もうひとつは不安定型だ。どちらも養育者(母親)と安定した愛着関係を築けなかったことが要因となり、引き起こされる。昨今の恋愛指南書で、あなたは不安型?回避型?のような形で扱われているのを見かけるので、知っている人も多いはず。本書では、...
愛着障害には2つの種類がある。ひとつは回避型で、もうひとつは不安定型だ。どちらも養育者(母親)と安定した愛着関係を築けなかったことが要因となり、引き起こされる。昨今の恋愛指南書で、あなたは不安型?回避型?のような形で扱われているのを見かけるので、知っている人も多いはず。本書では、その愛着障害が大人のADHDや社交不安、気分障害などを引き起こす根本的な原因になっていると解説している。 特に印象的なのは、愛着障害によりアルコール依存になった方が、依存症は改善できたものの、その後自殺してしまうというケース。依存症の治療はできても、依存症を引き起こした要因と考えられる母親との愛着関係が不安定だったがために、死を選んでしまったのだという。 愛着障害は、親子で治療していくことが最も重要なことだ。子が大人になってからでも、治療は十分に行える、そのことに希望を抱いた。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
愛着障害を抱える人にとって、人生とは苦痛が多く喜びは少ない。医療が未発達の時代なら、愛着障害から起こる免疫力の低下により早くに死んでしまった人たちが、現在では発達した医療に支えられて生き延びている。そんな時代であるから、様々な症状に苦しむ人たちや、問題行動が目立つ人たちが増えた。これらを治すには、愛し愛される。世話をすることに喜びを持てる社会にすることだと、そう書かれてるのかなと思った。 共感能力を高めて、「ほどよい距離」で人と関わるのって、凄く難しいなと思う。私は他人との「ほどよい距離」がわからないなと、この本を読んで気づいた。
Posted by
愛着障害により、生きづらさを抱える人が増え続ける社会。愛着障害とは一体なんなのか。歴史上の著名人たちのエピソードを前じえてそれらの課題と問題点を探る一冊。
Posted by