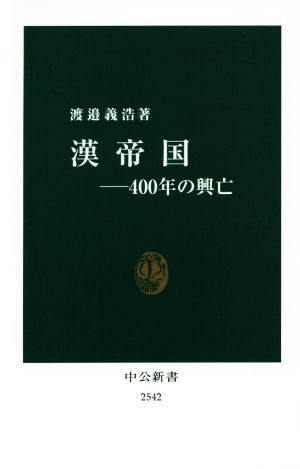漢帝国―400年の興亡 の商品レビュー
20230812-0831 紀元前202年〜紀元後5年前漢、王莽による簒奪(新)を経て、紀元後25年〜220年後漢。訳00年間の漢帝国の興亡をその儒教国家としての成立を軸に描いている。自分は特に前漢の武帝から宣帝(@お嬢様と私)の時代に興味があり、色々と想像しながら楽しく読めた。...
20230812-0831 紀元前202年〜紀元後5年前漢、王莽による簒奪(新)を経て、紀元後25年〜220年後漢。訳00年間の漢帝国の興亡をその儒教国家としての成立を軸に描いている。自分は特に前漢の武帝から宣帝(@お嬢様と私)の時代に興味があり、色々と想像しながら楽しく読めた。また、後漢の光武帝が即位する前後の状況は思っていた以上に興味深く読めた。
Posted by
漢の詳細がわかる新書。 董仲舒が司馬遷の師匠だったり、法家、黄老思想が時代をリードしていて、儒教は後漢になるまでメインではなかったり、王莽は国の簒奪を正当化するため必死だったりとと面白いエピソードが沢山あった。
Posted by
約400年にわたる漢についての通史で,全体として「儒教国家」であることを重視。また著者の問題意識は三国志を中心としており,諸葛亮による蜀「漢」への流れとして結びつけている。
Posted by
「漢字」「漢民族」という言葉に表れるように、漢帝国は後世の中国にとっていわば「古典中国」として原点とされ続けた「儒教国家」である。 いかにして「古典中国」が築かれていったかを概観する一冊。 そのため、通史に沿って最低限の政治史・外交史は触れられるものの、どちらかと言えば思想や文化...
「漢字」「漢民族」という言葉に表れるように、漢帝国は後世の中国にとっていわば「古典中国」として原点とされ続けた「儒教国家」である。 いかにして「古典中国」が築かれていったかを概観する一冊。 そのため、通史に沿って最低限の政治史・外交史は触れられるものの、どちらかと言えば思想や文化史の側面が強い。 儒教という一本の筋を通して漢の歴史を読んだのは初めてであり、大変勉強になった。 (以下は備忘録) 前漢成立初期(文帝の頃)までは、秦の法家思想や中央集権を引継ぎながらも、その峻厳すぎた反省を生かして、国政としては郡国制を採り、思想的には無為自然に代表される黄老思想が重要視され、皇帝の柔軟な政策判断を積み上げていった時期であった(後に漢の故事として先例となる)。 ついで、景帝・武帝期は、呉楚七国の乱を契機として、再び中央集権化が進み、「漢帝国」としてのアイデンティティ・求心性が確立した時期である。武帝による積極的な政策運用に伴い、黄老思想は後退し、この時期に儒家が台頭してくる。春秋の解釈を現実に当てはめ政策を支持あるいは批判する根拠とすることで、儒家は政権に食い込んでいく(董仲舒が有名だが、実は五経博士が置かれたのは武帝期ではないそうだ)。 その後、儒教に傾倒した元帝(前49年即位)から、儒教を革命の根拠に利用した王莽による新建国までの期間に、儒教の影響力はいよいよ高まり、政策や政権を儒教を根拠に正当化する「儒教国家」としての内実が確定していった。 後漢期は、漢を正当化するに都合の良い経書・緯書を正統として宣言し、更に郷挙里選の仕組みによって全国の豪族にも儒教教育が普及していった時期である。 そして第3代の章帝が主催した「白虎観会議」にてついには国教と化したと著者は論ずる。 しかし外戚・宦官の専横により、後漢・儒教国家は黄巾、次いで曹操による挑戦を受け倒れた。しかし、同時代に漢を理想とした劉備・諸葛亮らがいたように、後漢・儒教国家は「古典中国」として西晋以降にも模範として継承されていくほどに根付いていた。
Posted by
中国「漢」王朝の通史。後世の中国において規範となる「古典中国」の形成・完成という視点から、儒教と国家の関係の変容を軸に叙述している。社会が思想を規定するというより、思想による体制への規制力を重んじているように読める(体制はいかに恣意的な政治行為であっても儒教による正当化理論を要...
中国「漢」王朝の通史。後世の中国において規範となる「古典中国」の形成・完成という視点から、儒教と国家の関係の変容を軸に叙述している。社会が思想を規定するというより、思想による体制への規制力を重んじているように読める(体制はいかに恣意的な政治行為であっても儒教による正当化理論を要し、なおかつそれに拘束される)。儒教国教化の時期を通説より遅い後漢章帝期まで下ろしているのは(個人的には20年以上前に新進若手だった頃の著者の講義で直接教え込まれていたので既知だったが)、教科書でしか中国史を学んでいない人には新鮮であろう。儒教の規制力を重視するからこそ、脱「儒教国家」を図った曹操の革新性と「儒教国家」の枠内に留まった諸葛亮の保守性という評価に至る。「三国志」の前提としても勉強になろう。
Posted by
思想史を軸に楚漢戦争から三国志の時代までが扱われている。儒教が国教として受け入れられていく過程を通して、後世の範となる古典中国がいかに形成されたかが書かれていて、これまで持ってなかった視点が勉強になった。
Posted by
三国志は好きなので後漢末期の知識は多少あるが、それ以前の知識は余り無く興味を惹かれたので購入。 漠然と疑問に思っていた法家的な秦から儒教国家である漢への繋がる謎が丁寧に説かれていて常に感心しながら読み進められた。 やはりドラスティックに変わった訳では無く、前後400年の中で思考錯...
三国志は好きなので後漢末期の知識は多少あるが、それ以前の知識は余り無く興味を惹かれたので購入。 漠然と疑問に思っていた法家的な秦から儒教国家である漢への繋がる謎が丁寧に説かれていて常に感心しながら読み進められた。 やはりドラスティックに変わった訳では無く、前後400年の中で思考錯誤や政治的思惑が混ざり合い儒教自体が形を変えて国家体制と呼応していく様は面白い。簒奪者王莽が意外にも後漢の基礎づけに資していたことも驚き。 これまで意識していなかった四書五経や正史の歴史的位置づけもとっかかりが出来、今後中国の古典を学ぶ際にも役立ちそうで読んで正解でした。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
新書版なので当たり前なのだが、漢帝国の歴史をかいつまんで説明するというような本ではなく、あくまで漢という国が中国(中華帝国)の礎となった理由を漢時代に確立した制度から紐解くという学術的な本。それでも前漢まではそれなりに歴史書になっているが、本の半分以降はほぼ制度的な説明に終始して、正直なところそのようなことを期待してなかった身としては読み進むのがきつかった。漢の制度に興味がある読者(多分、中国史を勉強している学生)には大変な良書であるとは思うが、一般読者にはなかなか難しい内容となっている。なお、登場人物の名前の読みが非常に難しいので、できれば初出の部分だけではなく数ページ置きにはルビを振っていただきたかった。それくらいの気遣いは是非、出版社にお願いしたい。
Posted by
第1章 項羽と劉邦―時に利あらず 第2章 漢家の拡大と黄老思想―「無為」の有用性 第3章 漢帝国の確立―武帝の時代 第4章 漢家から天下へ―「儒教国家」への始動 第5章 「古典中国」への胎動―王莽の理想主義 第6章 「儒教国家」の成立―「古典中国」の形成 第7章 後漢「儒教国家」...
第1章 項羽と劉邦―時に利あらず 第2章 漢家の拡大と黄老思想―「無為」の有用性 第3章 漢帝国の確立―武帝の時代 第4章 漢家から天下へ―「儒教国家」への始動 第5章 「古典中国」への胎動―王莽の理想主義 第6章 「儒教国家」の成立―「古典中国」の形成 第7章 後漢「儒教国家」の限界―外戚・宦官・党人 第8章 黄天 当に立つべし―三国志の始まり 終章 漢帝国と「古典中国」 著者:渡邉義浩(1962-、東京都、中国史)
Posted by
基礎知識の乏しい自分には、史実の洪水について行くのが難しかったが、論旨は平易に感じた。終盤の三国志・諸葛亮のくだりを理解できたのが嬉しかった。
Posted by
- 1
- 2