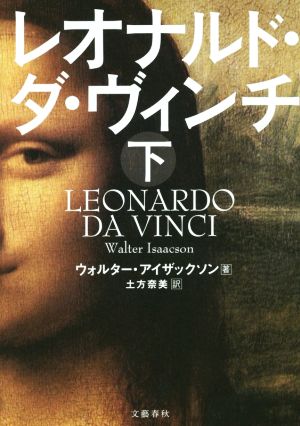レオナルド・ダ・ヴィンチ(下) の商品レビュー
工学者でもあり画家でもある彼の好奇心、目の付け所が面白いと感じた。最後の晩餐、モナリザ、東方三博士の礼拝、フランチェスコ、人体と機械の動き、フィボナッチ数列、メディチ家、芸術と科学等知的好奇心が掻き立てられる本であった。まさか子宮の中の胎児が出てくるとは思わなかった。
Posted by
『最後の晩餐』、『モナリザ』あたりの解説がとても分かりやすかった。更に『サルバトール・ムンディ(救世主)』については未知であったので真作と認めらえるまでの過程も含めて面白かった。 好奇心が強すぎて人体解剖、建築、武器の発明、運河の計画、彫刻など多岐にわたるが上巻で宮廷舞台演出家と...
『最後の晩餐』、『モナリザ』あたりの解説がとても分かりやすかった。更に『サルバトール・ムンディ(救世主)』については未知であったので真作と認めらえるまでの過程も含めて面白かった。 好奇心が強すぎて人体解剖、建築、武器の発明、運河の計画、彫刻など多岐にわたるが上巻で宮廷舞台演出家として「入り込んでいる」がそれも含めて人生に無駄なしということが分かる。 終章にある彼から学べることについての記載が素晴らしい。個人的には何にでも興味を持つ(メモには誰に聞かねばみたいなタスクになっているのも多い)、人との交流から学ぶ(孤独な巨匠タイプだと思っていたが違っていた!)、観察力(トンボの羽の動きとか細かい)というのは時代を超えた大切さだと思った。 また機会があれば再読したい。
Posted by
圧倒的な好奇心が成せる天才の技。ただ、近しいことは先人や同時代の人も考えており、歴史はつながっている、ということと、融合しあって創発されていくもので、1からすべてを創ったわけではないことが学び
Posted by
圧倒的好奇心で広範な知識を得ること、そしてそれを幅広く活用することは本当に見習いたい。レオナルド、ステキな人だと思った。最後の晩餐、モナリザはこの本を読んだ後は見方が変わる。伝記の面白さをあらためて知ることができて嬉しい
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
『最後の晩餐』はいかにもレオナルドらしい科学的遠近法と舞台のような自由な発想、知性と空想の融合した作品と言える 『聖アンナと聖母子』で最も重要な点は、レオナルドの芸術を貫く主要なテーマである、地球と人間との精神的つながりと類似性が表現されていることだ 絵画が得意なレオナルド、彫刻が得意なミケランジェロ 人間の血管網は、オレンジのそれと同じ性質を持つ。つまり古くなるほど、皮が厚くなり、果肉は薄くなるのだ 山から水が湧き出る原因は何か、なぜ谷が存在するのか、月が輝く原因は何か、化石はどうやって山頂に達したのか、水や空気の渦が発生するのはなぜか。そしてレオナルドを象徴する問もある。なぜ空は青いのか
Posted by
「上」はレオナルド立志編 「下」はレオナルド無限創造編 といったところ。 あらゆる力を身に付けて、今も知られる作品を残すまでのストーリーについて書かれていた。 図書館の返却期限に読了が間に合わず途中で断念した。機会があればまた読みたい。
Posted by
レオナルドの伝記決定版とされるが、確かに手記をもとに彼のあらゆる研究、特に水の力学、人体解剖、光学、兵器、などが彼のフィレンツェ、ミラノ、ローマ、フランスといった各パトロンに使えるきっかけとなり、その総合がモナリザにつながったとしており、発散的な研究が一つの天才によってまとめられ...
レオナルドの伝記決定版とされるが、確かに手記をもとに彼のあらゆる研究、特に水の力学、人体解剖、光学、兵器、などが彼のフィレンツェ、ミラノ、ローマ、フランスといった各パトロンに使えるきっかけとなり、その総合がモナリザにつながったとしており、発散的な研究が一つの天才によってまとめられていった形跡を示すものとしている。が、後出しな感じがして当時からマエストロではあったし、解剖はその時代の200年先も行っていたが、本当に意味のある天才なのかは、実際に世に出したアウトプットが少ないし、弟子も大成した者がいないことから評価は分かれるだろう。
Posted by
上巻があまりにも興味深い内容だったため、下巻も読みました。結論としては下巻も最高の一冊でした。今回も上巻に引き続きレオナルドという天才に近づくためにレオナルドがどんな性格だったのか、どんな人間だったかを注目して読み進めました。 レオナルドといえば芸術家であるイメージがある...
上巻があまりにも興味深い内容だったため、下巻も読みました。結論としては下巻も最高の一冊でした。今回も上巻に引き続きレオナルドという天才に近づくためにレオナルドがどんな性格だったのか、どんな人間だったかを注目して読み進めました。 レオナルドといえば芸術家であるイメージがあるかと思いますが、レオナルドは絵画でしか評価されない状況を嫌いフィレンツェからミラノへ拠点を移しました。また、お金を積まれても興味がなければ絵を描かなかったそうです。大きな才能を持っていてもそれに縋るのではなく、本当にやりたい事をやり続ける。ただお金のために絵を描き続けるのではなく、より良い絵を描くために生物の構造を学び、水の流れを研究し、解剖を続ける。本当の意味で学びが好きな人物であると改めて実感しました。 また、上巻で十分数多くの学問において才能を学んできたつもりでしたが、下巻ではこれまで知らなかった分野についても秀でていたことが学べました。さらにレオナルドは〇〇という考え方、概念がない時代にこれを作りだす天才、つまり0から1を生み出す天才であると感じました。コペルニクスやガリレオより早く地球が平坦でないと考え、微積分がない時代に連続量を扱いました。そして化石をもとに地層の研究を行う生痕学の祖であったというから驚きです。生痕学が主流になるのはレオナルドの死後300年後であるため、例えるなら、江戸時代にAIの研究をしていた商人がいたようなものだと私は考えました。 最後に、私は本書を読み進めるにあたり、ただレオナルドの歴史を学ぶのではなく、自分がレオナルドに近づくには何をしたらいいのかを主軸にしていました。本書の最後にはレオナルドに学ぶべきことが20個ほど述べられています。人類史の中でも指折りの天才から学びを得れる。本書は私がこれまで読んだどの書籍よりも説得力がありました。
Posted by
おもしろかったです。名前も作品も知っていたけど、こんなに生き方をしていたとは知らなかった。絵画も科学も医学も生物学も地形学も芸能も、ジャンルなんて関係なく、興味、関心のまま問い続け、観察し続け、教わり、協働する。それが彼の作品となってあらわれる。本当にすごい人。筆者も書いています...
おもしろかったです。名前も作品も知っていたけど、こんなに生き方をしていたとは知らなかった。絵画も科学も医学も生物学も地形学も芸能も、ジャンルなんて関係なく、興味、関心のまま問い続け、観察し続け、教わり、協働する。それが彼の作品となってあらわれる。本当にすごい人。筆者も書いていますが、天才だからですませず、真似できる部分は真似したいです。そうしたら、世界の見方が変わっておもしろくなりそう。
Posted by
この本を読んでわかったのは、レオナルドはいわゆる”天才”ではなかったということ。 多くの挫折や悩みを抱えながら、それでも自身の好奇心を純粋に追求し、死ぬまでその信念にブレがなかった人。 そして、非嫡出子であり、父からの愛に飢えていたがゆえに、自分を認めてくれる権力者の庇護を終生求...
この本を読んでわかったのは、レオナルドはいわゆる”天才”ではなかったということ。 多くの挫折や悩みを抱えながら、それでも自身の好奇心を純粋に追求し、死ぬまでその信念にブレがなかった人。 そして、非嫡出子であり、父からの愛に飢えていたがゆえに、自分を認めてくれる権力者の庇護を終生求め続けた人。 (それでいながら、言うことをきかないこともしばしば。。) 多くのことに対して好奇心を持ち探求し続けたその精華が、「モナリザ」に結実しているからこそ、名画と言われるのだろう。 実物を見たくなった。
Posted by
- 1
- 2