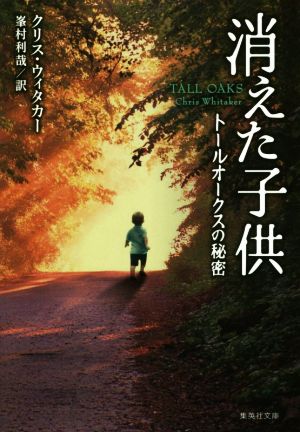消えた子供 トールオークスの秘密 の商品レビュー
子どもの行方不明事件が起きた平和な田舎町の住民にスポットを当てたストーリー。それぞれの苦悩が現れてきて重くなりそうだけど、不良で雑な高校生に見えるマニーが家族想いで誰にでもストレートに接するのに救われる。行方不明の子どもハリーをもっと丁寧に掘り下げて欲しかった。
Posted by
イギリスの作家クリス・ウィタカーの長篇ミステリ作品『消えた子供 トールオークスの秘密(原題:Tall Oaks)』を読みました。 アガサ・クリスティの『ポケットにライ麦を』に続き、イギリスの作家の作品です。 -----story------------- 誰もが怪しい誰もがおか...
イギリスの作家クリス・ウィタカーの長篇ミステリ作品『消えた子供 トールオークスの秘密(原題:Tall Oaks)』を読みました。 アガサ・クリスティの『ポケットにライ麦を』に続き、イギリスの作家の作品です。 -----story------------- 誰もが怪しい誰もがおかしい 英国推理作家協会賞新人賞受賞作!! 誰もが顔見知りの小さな町トールオークス。 深刻な犯罪とは無縁のこの町で、嵐の晩に、三歳の子供が忽然と消えた。 全米の注目を集めたこの失踪事件は、住民総出の捜索でも警察の捜査でも、手がかりすら出てこない。 絶望に抗いながら捜し続ける母親。 そして、町の住民たちそれぞれが抱えていた秘密が次第に明らかになっていくなかで、意想外の真相が姿を現して──CWA新人賞受賞の傑作ミステリ! 解説/杉江松恋 ----------------------- 2016年(平成28年)に刊行されたクリス・ウィタカーのデビュー作です。 背の高い樫(オーク)の林があることにその名は由来する穏やかな町トールオークス……そんなトールオークスで幼児の行方不明という痛ましい事件が起きる、、、 いなくなったのは、ハリー・モンローという3歳の少年……事件の晩、ハリーは自宅の子供部屋に1人で寝かされていたが、そこに何者かが侵入し、彼を連れ去ったのである。 母親のジェシカ(ジェス)によれば、子供部屋を監視するモニタ画面には、ピエロの格好をした不審人物が映っていたという……大事件の発生に町は騒然となり、住民は一丸となってハリーの行方を探し始めたが、それもしばらくの間だけだった。 幾日経っても少年は出てこなかった……捜索隊の参加者は日常に戻り、ハリーの名を囁きあっていた人々も口をつぐんだ、、、 街角を彷徨って我が子の捜索ポスターを貼り続けるジェシカから、礼儀正しく目を背けるようになった……今やハリーは初めからこの世に存在しなかったようにさえ見える。 トールオークス警察署の署長ジム・ヤングのもとをジェシカが定期的に訪れ、事件当夜のことについて話し合いを持つことが、唯一の現実とのつながりとなっていた……他の住民は自分自身の不幸に向き合うだけでも大変で自分の生活で手一杯、よそに目を向けている余裕がなかった、、、 住民たちが抱える、それぞれの悩みや秘密が明らかになるにつれ予想外の真相が判明していく……。 小さな町で起こった重大事件を機に住民たちが抱える秘密と嘘が浮き上がる……その過程で徐々に明かされる交雑する人間模様、、、 子どもを探し続ける母、近所の住人たち、写真館、工務店、パティシエ、薬局、そして、それぞれの家族……各々の人たちの視点で語られるエピソードにより、少しずつ小さな町の物語が繋がっていく という展開。 そんな小さな町の群像劇……それぞれの家族や住民たちの哀しみや幸せ、葛藤 等の人間ドラマが描かれるうちに、終盤で一気に全ての謎が解ける、、、 真犯人は想定内だったかな……ある意味、最もリアリティのある結末だったかもしれませんね。 家族、親子、夫婦などのデリケートな物語が生き生きと描かれていることが特徴の作品でしたね……性や人種のマイノリティに対する目線も温かく、血の通ったキャラクター造形が印象的でした、、、 本筋にはあまり関係しないのですが、イチバン印象に残った登場人物は、トールオークス高校3年生のマニー・ロメロ……間もなく卒業予定の彼は、何を思ったのか高校生活最後の夏をイタリアン・マフィアのような衣装に身を包み、街のやつらをしめて、みかじめ料を回収することに捧げようと決意し、「あんたはメキシコ系なんだからマフィアになれるわけがないだろう」という母親エレナのもっともすぎる忠告にも耳を貸さないんですよねー いやぁ、イイなぁ、幸せになってほしいと思いました。
Posted by
マニーが最高だった。 イギリス人が書いたものという先入観で、ユーモアもイギリス的だったので、舞台がイングランドかと思いきや、アメリカの片田舎だった。どこで起きようが普遍的な内容の人々の暮らしを描いているので、気にならないけども、何度もそれを思い出して頭の中の情景を修正した。意外...
マニーが最高だった。 イギリス人が書いたものという先入観で、ユーモアもイギリス的だったので、舞台がイングランドかと思いきや、アメリカの片田舎だった。どこで起きようが普遍的な内容の人々の暮らしを描いているので、気にならないけども、何度もそれを思い出して頭の中の情景を修正した。意外とそういう細部は頭の中で作りながら読んでるものだなと思った。 軸となる消えた子供の誘拐事件の謎を追いかけるよりも、トールオークスという街で起きる群像劇。どの人物もいきいきしていて、最後がモヤったものの楽しく読めた。
Posted by
なんと言うか…、良く言えば「意表を突かれる」感じ、でしょうか? 「子供が消えた→警察の捜査」とはならずに、トールオークスの町の人々のエピソードが交互に連なっていく展開に、戸惑いを覚えつつ読み進み、(皆さんが思うのとは違う)驚愕のラスト… というか、邦題の付け方に難があったのでは?...
なんと言うか…、良く言えば「意表を突かれる」感じ、でしょうか? 「子供が消えた→警察の捜査」とはならずに、トールオークスの町の人々のエピソードが交互に連なっていく展開に、戸惑いを覚えつつ読み進み、(皆さんが思うのとは違う)驚愕のラスト… というか、邦題の付け方に難があったのでは?とも思います。 原題のままの「トールオークス」だけではインパクトに欠けるからか、敢えてミステリ色を強めようとしたのか…と推察しますが、そうなると強くなり過ぎた嫌いが出てきたように感じました
Posted by
登場人物一人一人の性格、暮らし、そして秘密が少しずつ明らかになりながら、物語はさらに絡み合って行きます。人物の描きかたが秀逸でした。 暗く陰鬱な中にも、救いと明るさがあり、読後感も良かったです。
Posted by
母親ジェシカと暮らす三歳の息子が行方不明になった。 寝室は別だったがモニターまで設置していたのにも関わらず姿がないと言う。 父親が去ってから精神的に不安定だったのか…。 絶望感を隠そうともせず、探し続ける母であったが。 小さなこの町では誰もが知り合いであるというようほど、次々...
母親ジェシカと暮らす三歳の息子が行方不明になった。 寝室は別だったがモニターまで設置していたのにも関わらず姿がないと言う。 父親が去ってから精神的に不安定だったのか…。 絶望感を隠そうともせず、探し続ける母であったが。 小さなこの町では誰もが知り合いであるというようほど、次々と曰くある人物が出てきて誰もを疑ってしまうのである。 それぞれに何かしら問題を抱えていて、上手くいっていないことだらけで。 少しずつその抱えている秘密が明らかになっていく。 行方不明の子どもの足取りを追うよりも周りの細々とした出来事に振り回されていたが、最後の最後になんということか…と。 あまりにも他の出来事に目を奪われていて、ちょっとしたことを見逃してしまってた。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
マニーという青年のお陰でほどほどに楽しめたのだが… 目まぐるしく変わる場面と多くの登場人物にようやく慣れた長い物語の末に辿り着いたのが自己愛の塊で、なにもかもが『人のせい』のくだらないクソ低能ビ⚪︎チとは… 本当に、 もうほんとうに児童虐待の話はたくさんだ。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
はい、クリス・ウィタカーは本物でした。 とはいえ若々しさというか、初々しさというかまだ手探りな感じは受ける。 『我ら、闇より天を見る』は余白を携えた中に痛みと愛が同居する、完璧なまでに洗練された物語だったが、こちらはやや目まぐるしい程の詰め込み具合。 冒頭はジェスの3歳の息子、ハリーが嵐の夜にピエロの仮面を被った何者かに連れ去られたシーンに始まる。 物語はこのハリー失踪事件を通底音に繰り広げられる、スモールタウン、トールオークスに暮らす人々の抱える秘密と真実。 誰もが何かしらの秘密を抱えているようで、いわくありげな空気が漂う。 必ずしも失踪事件の真実を追うだけでなく、この町に暮らす各人の生き様をじわじわと浮かび上がらせる展開。 特に際立っている点は、ともするとシリアスで陰鬱な語りの後に急に差し込まれるコメディタッチのやりとり。 口の悪さはピカいち、メキシコルーツなのに何故かイタリアマフィアに憧れ、サイズの小さい中折れ帽を被っているがために額の周りに赤い線が浮かぶ、夏でもウールの三つ揃いを着るマニー。 マニーの親友でひょろ高いユダヤ人のエイブ、マニーの一目惚れを誘ったイラクから隣家に越してきたフラット。 この3人を中心に繰り広げられるザ・青春の笑い。 あのクリス・ウィタカーの作品にこんなコメディタッチがと異質な感じを受けるのだが、これがまた何とも言えない。 痛快なまでの口汚さの奥に潜む本物の感情。 どんな場面でも、ことごとく口にしちゃいけない言葉をまくしたてるマニーと、さらっと受け流すフラット。 その心通ずる様が微笑ましい。 もっともっとこの作家の作品を読んでみたい。 早く、新作翻訳されないかな。
Posted by
事件が話の中心にならない。事件は確かに存在するが、同時に存在する周りの者の生活も同じくらい大事に、そして当然のように描かれ、全てがゆっくりと確実に進んでいく。本当に面白かった。特にマニーの存在。彼がいるかいないかで、印象が大きく変わる。
Posted by
「これは凄い。おそらく今年、一押しの作品である」 ぼくが書いた『われら闇より天を見る』レビューの一行目である。「このミス」で2位作品に倍近い差をつけて、圧倒と言える年間第一位の座を獲得したのがクリス・ウィタカーであった。 この度、この作家の4年前に出版されていた翻訳作品...
「これは凄い。おそらく今年、一押しの作品である」 ぼくが書いた『われら闇より天を見る』レビューの一行目である。「このミス」で2位作品に倍近い差をつけて、圧倒と言える年間第一位の座を獲得したのがクリス・ウィタカーであった。 この度、この作家の4年前に出版されていた翻訳作品『消えた子供』を開いてみて、クリス・ウィタカーの並々ならぬ物語力、人物造形力にふたたび圧倒される経験を味わった。この作家はやはり4年前の時点で既に凄絶である。昨秋の『このミステリーがすごい!』には、作者自らが寄稿している。そのわずか2頁からは、作者のたぐいまれなる負の経験、痛みの感覚、復活への渇望、物語ることへのモチベーション、遂に辿り着いた高み。そして幸福の地点からの歓喜の震えが存分に窺えるので、今一度ご確認願いたい。 そしてここで取り上げる作者4年前の作品『消えた子供』もまた秀逸極まりなく、オリジナリティが溢れるばかりか、実にスリリングでヒューマンな人間ドラマなのである。この作家はただものではないことを、既にこの作品は予見していたようである。ぼく自身としては出遅れて本書に辿り着いたのが悔やまれるくらいなので、この作品に新たに取り組まれる読者はおそらく本作でも満足して頂けるであろう。昨年の傑作に勝るとも劣らない人間悲喜劇の迷路と隘路とを、この作家特有の物語力というパワーに引きずられて、混沌の田舎町トールオークスを彷徨しつつ深い味わいを堪能して頂けることだろう。 町の人々の個々のドラマが猫の目のように入れ替わるなかで、次第に浮き上がってゆくのは、幼児行方不明事件の真相である。否、真相に思われたかと思うと逃げ水のように遠のいてゆく光、なのかもしれない。事件とは一見関係のないキャラクターたちの、不思議だが謎めいた行動もそれぞれ気になる。怪しいと思われる人間たちがかしこに出没する物語なのである。読者の推理力をくすぐりながらも、多くの主演格のキャラクターたちの個性が浮き彫りにされてゆく。見た目の向こう側の真実へと、読者は暗闇を辿ることになる。 昨年の翻訳小説の傑作『われら闇より天を見る』で最も印象的だったヒロイン、自分を<無法者>と呼ぶ少女ダッチェの存在は強烈であったが、実はその実験的モデルケースが、本書には既に登場していた。マニーという少年である。彼は、自分をギャングに見立て、シチリア・マフィアのような服装に身を包んで口汚く行動し、可笑しいほどに悪ぶっている。大好きな映画は『ロッキー』でシルベスター・スタローン演じたロッキー・バルボアのように、貧しさから拳だけで這い上がることを夢見る。生活の中で、かの映画のどのシーンをも再現しながら、自分のリングを空想してはばからない。それでいて友だちやガールフレンドに慕われ、町の人たちからも興味深い眼で愛される存在でもある。不思議なキャラクターだが、そこがクリス・ウィタカーの世界なのだと言える。だからこそ、昨年の傑作に胸打たれた読者には本作も是非手に取って頂きたいのだ。 数多くの主人公が同時並行的に動く本作であるが、章割りが短いため読みやすい。ミステリーを骨子とするドラマなので、ミスリードのあざとさといった感はぬぐえないが、多くの個性と、それぞれの人生や物語や家族、親子、夫婦などのデリケートな物語が生き生きと描かれてゆく様子は、この作者ならではのものである。性や人種のマイノリティに対する目線も温かく、決してぞんざいには扱わず、血の通ったキャラクター造形が何より光る。 まだまだ若い期待の作家である。他の未訳作品もどんどん邦訳され、それら未だ見ぬ物語と、その世界を躍動する本書のような登場人物たちが、ぼくらの心の中でみたび躍動する機会がやってくるべく、心より願いたい。心より!
Posted by
- 1
- 2