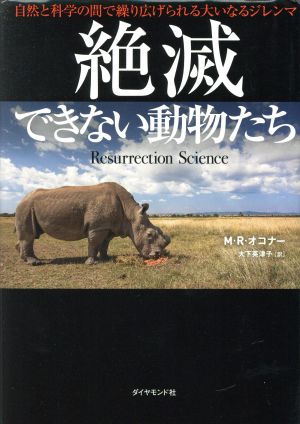絶滅できない動物たち の商品レビュー
全ては『ヒト』という種のエゴであると。 地球からしたら、我々は癌細胞と同じで蝕み全てを破壊し尽くしていく。 絶滅した種を復活させるなど、神にでもなるつもりなのか。
Posted by
『絶滅できない動物たち 自然と科学の間で繰り広げられる大いなるジレンマ』読了しました 絶滅する動物たちを守るための様々な行動とその倫理の壁や難しさに触れた本作 ◯経済的な事情により人間の生活のためのインフラ設備と種を守ることのどちらを選ぶかを象徴するキハンシヒキガエルや、人...
『絶滅できない動物たち 自然と科学の間で繰り広げられる大いなるジレンマ』読了しました 絶滅する動物たちを守るための様々な行動とその倫理の壁や難しさに触れた本作 ◯経済的な事情により人間の生活のためのインフラ設備と種を守ることのどちらを選ぶかを象徴するキハンシヒキガエルや、人間が何かをすることができるのか問いかけるタイセイヨウセミクジラ ◯政治的と地政学的事情が絡み密猟者によって絶滅する運命にあるキタシロサイや、すでに絶滅したジャコウバト、そしてネオンデタール人をIPS細胞などの遺伝子操作によって蘇らせようという試み こういった面から『絶滅動物を救う』ということの実情とその課題、そして倫理的な問題に触れた書籍でした 単純に生物多様性と環境保全と言いつつも、それは人間がコントロール可能なのか、という問いも含んでおり、果たして多様性とはなんだろうか、結局DXなどはインフラが整った先進国の戯言なのか? という書籍にはないことについても考えるきっかけとなる1冊でしたね
Posted by
動物を生かす事も絶滅させる事も人間のただのエゴ。 そもそも頼まれていない。読み物として面白かった。 しかし、仕事に活用は出来ない本なので、次回からこのジャンルは図書館でレンタルする。
Posted by
たしかに、絶滅した種をDNAから復元することは、果たして自然保護なのか…?? 自然とは、絶滅とは… うーん、向き合わなくてはいけない問題だ…
Posted by
人間による種の保存という行為について、生態系の維持に必要なものなのか、人間の独善的な行為なのかという2つの見方ができると知った。絶滅危惧からの復活という目的で、絶滅の恐れのある種を動物園や研究施設で管理することは、人間から見れば未来に繋がる大切な工程のひとつであると思われるし、管...
人間による種の保存という行為について、生態系の維持に必要なものなのか、人間の独善的な行為なのかという2つの見方ができると知った。絶滅危惧からの復活という目的で、絶滅の恐れのある種を動物園や研究施設で管理することは、人間から見れば未来に繋がる大切な工程のひとつであると思われるし、管理される側の動物は自由に活動できない状況になってしまう。 日本の事例では、兵庫県のコウノトリや佐渡島のトキが挙げられる。中国から個体を輸入し人工授精後に自然界に放流した結果、現在でも一定数が生息し、絶命危惧度が緩和された。確かに日本の原風景の再現には貢献できたかもしれないが、トキらが絶滅した後、その土地で新たに形成された生態系を脅かす存在にもなり得る。今後個体数が増加していき自然界に問題が顕然した場合には、人間の独善的な行為と指摘されてもおかしくない。 本書の終盤ではオブジェクト指向存在論に触れている。人間からの一方的な自然や種の解釈を行うだけではなく、双方向的な理解を模索する必要があると学んだ。地球に生命が誕生して30億年以上が経過したが、その間、ある種が繁栄・進化したら他のある種が衰退・絶滅に追いやられるという事例は汲めども尽きなかった。現代は人間が繁栄する種であり、その余波で他の種が衰退していると考えられる。以上を踏まえ、他の種にとっての人間の存在意義を考え続け、人間による種の保存行為の是非を検討する必要があると感じる。
Posted by
「絶滅を防ぐことは良いこと」と思っていた自分の考え方を広げてくれた一冊。 インパクトでいえば今年読んだ本の中では一番かもしれない。 まずタイトルにやられた。なんてキャッチーなタイトル。 本書に出てくるのは絶滅「できない」というよりは「させてもらえない」動物たちだなと思った。 仮に...
「絶滅を防ぐことは良いこと」と思っていた自分の考え方を広げてくれた一冊。 インパクトでいえば今年読んだ本の中では一番かもしれない。 まずタイトルにやられた。なんてキャッチーなタイトル。 本書に出てくるのは絶滅「できない」というよりは「させてもらえない」動物たちだなと思った。 仮に動物たちと意志を通わせることができたとして、人間が行っている取り組みに対して、何を感じているのかと思いを馳せた。 人類が地球環境に与えている影響の大きさを知ることができた。 しかし、それすらも地球にとっては些細なことなのかもしれないなとも思った。 そもそも人類が生態系に干渉すること自体がおこがましいのでは?とすら思った。 ハイパーオブジェクトという概念をもっと掘り下げて理解したい。
Posted by
絶滅を危惧される種を保護することが、本当に種の継続に繋がってるんだっけ?という問題提起を意識できるようになってよかったかなっていう。この手の翻訳物は本当に無駄なセンテンスが多くて読みづらい。気の利いた風の言い回しとか、バッサリ切ってしまえばもっと読みやすくて意図も通じるのにと毎回...
絶滅を危惧される種を保護することが、本当に種の継続に繋がってるんだっけ?という問題提起を意識できるようになってよかったかなっていう。この手の翻訳物は本当に無駄なセンテンスが多くて読みづらい。気の利いた風の言い回しとか、バッサリ切ってしまえばもっと読みやすくて意図も通じるのにと毎回思うけど。
Posted by
保護して生かしておけば絶滅を免れているかというとそんなことはなくて、保護環境下で生活様式が変わって何世代か経つと自然環境下とは違う進化をしてしまう。保護する意味を考えさせられる。
Posted by
今までは、種を絶滅から守る?いいんじゃない?程度にしか思っていなかった。 だが必ずしも全てが正しいというわけではないようだ。 人工的な環境下でしか生きられない動物は、自然に生きていると言えるのか。 人間の手によって育てられた動物は鳴き方すらも忘れてしまう。 DNAより復活させら...
今までは、種を絶滅から守る?いいんじゃない?程度にしか思っていなかった。 だが必ずしも全てが正しいというわけではないようだ。 人工的な環境下でしか生きられない動物は、自然に生きていると言えるのか。 人間の手によって育てられた動物は鳴き方すらも忘れてしまう。 DNAより復活させられた動物は、果たして絶滅前の動物と同じ種で括っても良いのか。 人間の都合で絶滅に追い込んでおいて、今度は復活だなんて勝手すぎる。とは思うが今までこういう話題にはあまり関心を持っていなかったので何も言えない。
Posted by
種の絶滅とはなんぞや、種の保護とはなんぞや、自然保護とはなんぞや。環境保護と貧困対策の優先順位はどうあるべきか。DNAさえ保管すれば良いのか、種の遺伝的多様性を維持するために、やっていいことと悪いことの線引きはどこにあるべきか。どこまでが保護すべき遺伝的グループだと言えるのか?e...
種の絶滅とはなんぞや、種の保護とはなんぞや、自然保護とはなんぞや。環境保護と貧困対策の優先順位はどうあるべきか。DNAさえ保管すれば良いのか、種の遺伝的多様性を維持するために、やっていいことと悪いことの線引きはどこにあるべきか。どこまでが保護すべき遺伝的グループだと言えるのか?etc.etc. 人類の支配を企む人や組織は、これらの問いへの答えを用意しなければならないのか、大変だなw
Posted by