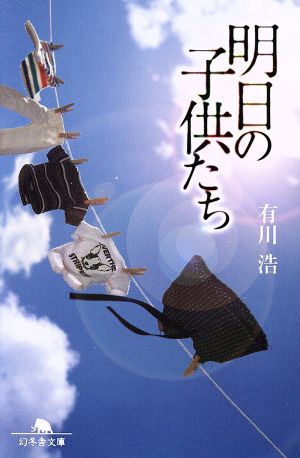明日の子供たち の商品レビュー
児童施設を舞台にした小説で、現実は小説よりも大変なことが多いとも思われますが、施設について知ったり考えたりするきっかけになりました。読後は明るい未来を感じました。
Posted by
最終盤に出てくる読者から小説家への手紙と、解説に感動した。ストーリーやキャラ設定は好みよりやや平易で、もう少し深みが欲しかった。
Posted by
児童養護施設を舞台にした、お仕事小説と思いきや、子供達の気持ちに寄り添い、特に退所する一歩手前の高校生達にスポットを当てて、施設の実態を見たような気になりました。彼らの未来が明るいことを祈ります。出会えて良かった小説でした。
Posted by
かわいそうって思わないでほしい… この言葉が沢山出てくる。それにとても違和感を覚える作品だった。 かわいそうって言わないで、なら分かる。下に見られてる、見下される気持ちになるから言わないで…ならとても共感できる。 でも、人はかわいそうって思わないと手を差し伸べる、支援するのはなか...
かわいそうって思わないでほしい… この言葉が沢山出てくる。それにとても違和感を覚える作品だった。 かわいそうって言わないで、なら分かる。下に見られてる、見下される気持ちになるから言わないで…ならとても共感できる。 でも、人はかわいそうって思わないと手を差し伸べる、支援するのはなかなか難しい。 自分で生きていくのに精一杯だから。
Posted by
これは、有川浩さん作品の中で上位にランクインしますね。 それぞれ先生の良さが出ていますが梨田先生の男気に涙しました。普段生きていて意地になっていることを変えるのはとても難しいことです。それを相手のことを第一に考えることに変える勇気、感動しました。 最後の有川さんに実際手紙を送った...
これは、有川浩さん作品の中で上位にランクインしますね。 それぞれ先生の良さが出ていますが梨田先生の男気に涙しました。普段生きていて意地になっていることを変えるのはとても難しいことです。それを相手のことを第一に考えることに変える勇気、感動しました。 最後の有川さんに実際手紙を送った方の解説にも心揺れました。この本の目的である施設を知らない人に知ってもらうについては、十分知る事が出来ました。ありがとうございました。 清々しく読み終える事ができる作品でした。 良い昨日に出会えて満足感いっぱいです。 三田村さんは読み始めは苦手なタイプで嫌でしたが最後はそこそこ好きになっていました。
Posted by
施設で暮らすことを勝手に不幸だと決めつけていること。 自身にもあったかもしれない。 若い頃に障がい者施設で働いていたこともあり、今は企業で障がい者の雇用と定着支援を担当しているが、中には施設出身の子もいる。 はたして本作の職員のように接することが今まで自分はできていただろうかと自...
施設で暮らすことを勝手に不幸だと決めつけていること。 自身にもあったかもしれない。 若い頃に障がい者施設で働いていたこともあり、今は企業で障がい者の雇用と定着支援を担当しているが、中には施設出身の子もいる。 はたして本作の職員のように接することが今まで自分はできていただろうかと自問自答しながら読んだ。 有川さんの著書なので、期待を裏切らない安定の読後感。 読んでよかった。
Posted by
施設で育ったからかわいそうなんて思ってほしくない。施設育ちのカナコがこう思うように、誰もがこういう気持ちってあると思います。 かわいそう?誰目線で?あなた目線で?それとも一般的に?平均的に?標準的に? それはあなたが何かを基準にして比較してるからでしょ?しかもかわいそう?どれだけ...
施設で育ったからかわいそうなんて思ってほしくない。施設育ちのカナコがこう思うように、誰もがこういう気持ちってあると思います。 かわいそう?誰目線で?あなた目線で?それとも一般的に?平均的に?標準的に? それはあなたが何かを基準にして比較してるからでしょ?しかもかわいそう?どれだけ上目線なの?? この気持ちよくわかります。 やはり自分の思考を考えても、自分ラインより下かもしれない、と思う相手に対しては気の毒だなとか思ってしまう気持ちはあります。だけどもしかしたら、相手にとってはすごく幸せなことかもしれない。結局は、かわいそうと思う気持ちは、その人に何かをしてあげたいという気持ちよりも比較して自分が上位でありたいという傲慢な考えなのかなと思いました。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
元営業マンだった主人公が、「施設育ちの子供たちは、かわいそうだから その子たちを支えたい」という偏見で児童養護施設で働き始めた。 しかし、その偏見のせいで子供たちとなかなか距離が縮まらなかったり、色々な年齢の子供たちに合わせた世話を個別性を考えながら奮闘したりして主人公自身も成長していく物語だった。 施設で育つ子供は、家よりも施設のほうが安心安全な生活ができることが ほとんどなため、かわいそうな子供ではないことを知った。 また、施設で育つ子供は、高校生くらいになると自分で衣類を購入するように お金を与えられること、高校卒業後 施設を退所させられ施設を頼れず親類などがいない子供たちが ほとんどなため経済的自立を促し身を持ち崩さないように進学よりも就職を施設が推奨していることを知った。
Posted by
児童養護施設での生活を仔細に描いており、綿密な取材をされたことがよく伝わる。 例えば、年間の被服代は3万円であり、3万円で靴下のような消耗品もやりくりすること。間着にまで予算を回せないこと。進学か就職なら就職を推進すること。なぜなら頼れる大人が少なく経済的に行き詰まるリスクが高い...
児童養護施設での生活を仔細に描いており、綿密な取材をされたことがよく伝わる。 例えば、年間の被服代は3万円であり、3万円で靴下のような消耗品もやりくりすること。間着にまで予算を回せないこと。進学か就職なら就職を推進すること。なぜなら頼れる大人が少なく経済的に行き詰まるリスクが高いから、特に女の子ならば身を持ち崩すのも珍しくないということ等々。 施設出身の子供たちは、貧困や虐待で社会の波間に沈みやすい不安定さを孕む。だからこそ、聡く逞しく生きていかなければ飲み込まれてしまう。 虐待された子供が成長すると、自分がされたような虐待に及んでしまうことがある。そうした苦い事実を知識として蓄え、ロールモデルを見つけることや立ち回りを身につけていく賢さが彼ら自身の武器になるのだと作品を通じて痛感した。
Posted by
児童養護施設について、当事者の立場で読み進められる素敵な小説でした。可哀想という世間一般のイメージと、当事者の気持ちがどれだけかけ離れているか、間違った同情や支援では誰も救われない、 まさに「無知は罪」なのだな、と感じました。 最後の解説を読んで、さらに感動しました。 全ての方に...
児童養護施設について、当事者の立場で読み進められる素敵な小説でした。可哀想という世間一般のイメージと、当事者の気持ちがどれだけかけ離れているか、間違った同情や支援では誰も救われない、 まさに「無知は罪」なのだな、と感じました。 最後の解説を読んで、さらに感動しました。 全ての方にお勧めです!!
Posted by