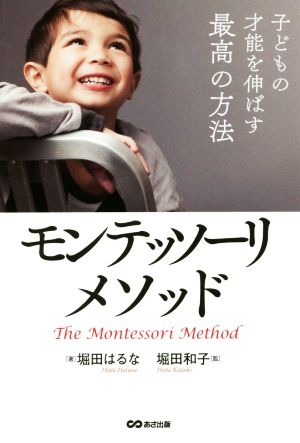子どもの才能を伸ばす最高の方法モンテッソーリ・メソッド の商品レビュー
モンテッソーリメソッドについては既にいくつか本を読んできたが、こちらは具体的な教材の使い方や子どもとの関わり方にも言及しており、興味深かった。 以下メモ ◆子どものなぜなぜ?には、答えじゃなくて共感するだけでいい。理由を知りたそうなら、図鑑で一緒に調べるなど、納得する答え見つけ...
モンテッソーリメソッドについては既にいくつか本を読んできたが、こちらは具体的な教材の使い方や子どもとの関わり方にも言及しており、興味深かった。 以下メモ ◆子どものなぜなぜ?には、答えじゃなくて共感するだけでいい。理由を知りたそうなら、図鑑で一緒に調べるなど、納得する答え見つけを手伝うだけ。 ◆子どもが育つ課程で凹凸ができるのは当たり前。大人が先読みして足りないもの探しをするより、子どもが今興味あることに共感して一緒に楽しむ ◆3ー6歳 感覚の敏感期。感覚器官を沢山使う。芸術的センス、色彩感覚、音への鋭い感覚、微妙な違いのわかる味覚はこの時期の経験によって育つ。 ◆子どもと同じ目線で共感する。子どもの気持ちの程度に合わせる。子どもが頑張った気持ちになっていないときにほめても響かない。むしろ褒められるからやるという気に。 ◆ネガティブよりポジティブな言い方の方が受け入れられやすい。 ◆ダメを伝える際は、短く完結、具体的、穏やかに。 ◆社会で自由でいるためには、さまざまな社会性を身につける必要がある。好き放題=自由ではない。 ◆自分の五感を沢山使って感じる。世界への理解へ。テレビは実体を伴わないため不完全。 ◆体験を通して概念を習得する
Posted by
モンテッソーリ教育についてわかりやすく書いてあった。 ----------以下メモ---------- 子どもが本来持っている自分で生きる能力を伸ばすか、伸ばさないかは生まれた後の環境にかかっている。 苦手なものに向けた努力は好きのパワーにはかないません。 子どもがチャ...
モンテッソーリ教育についてわかりやすく書いてあった。 ----------以下メモ---------- 子どもが本来持っている自分で生きる能力を伸ばすか、伸ばさないかは生まれた後の環境にかかっている。 苦手なものに向けた努力は好きのパワーにはかないません。 子どもがチャレンジできるようになるには、親が彼彼女をまるごと肯定してあげることが一番 子どもの誤りに気づいても、努めてそれを直接的に訂正しないようにする 小さなうちから子どもが毎日できるかぎり、たくさん手を使うように習慣づけてあげる 〇〇だからだめ、よりも、〇〇するのが良いというポジティブな言い換えに変える工夫 理科 学術用語に触れる 秩序の敏感期 2〜3歳 感覚の敏感期 3〜6歳 運動の敏感期 4歳半ごろまで 言語の敏感期 6歳ごろまで
Posted by
モンテッソーリの本はこれが2冊目で、だいたいの内容は理解したつもりでいたが、良かれと思ってやらせていたことが、親のエゴになってしまっていたことや、大人目線で褒めるよりも子供の気持ちに共感してあげるほうが良い影響を与えること、子供にとってテレビから受け取る情報は実態を伴わないこと等...
モンテッソーリの本はこれが2冊目で、だいたいの内容は理解したつもりでいたが、良かれと思ってやらせていたことが、親のエゴになってしまっていたことや、大人目線で褒めるよりも子供の気持ちに共感してあげるほうが良い影響を与えること、子供にとってテレビから受け取る情報は実態を伴わないこと等、改めて気付かされることがいくつかあった。 後半は教具やスクールの紹介がほとんどで退屈だったが、この本を読んだことで、子供との接し方を見直す良いきっかけとなった。
Posted by
日本でのモンテッソーリ教室の様子と先生が考えていくることの概要が解説されている。 先生は、自らが子供の環境因子であることを意識する、というのは気づきがあった。親子でそれくらい客観視できたらなぁと。
Posted by
自分が小さい時に受けていたら良かったなと思う。子どもには家庭でできる範囲でモンテッソーリ教育を実践したい。体系的に分かりやすい本でした。
Posted by
モンテッソーリについての入門書。 すごくわかりやすかった。 こどもの力はすごいのに、なんで、扱いやすくするために制限をかけながら育てなきゃいけないんだろう…と、今の日本の教育について考えた。
Posted by
入門書。何となく全体像が見えました。敏感期というのは押さえておかなければと思いました。実際にはイヤイヤ期を目の前にするととてもそんな余裕はないというのが正直なところですが。。。
Posted by
幼児期の教育に焦点を当てて書かれている本で、読み終わってすぐに妻にも勧めた。反省すべき点としては、子どもの自主性を重んじる声かけを意識して行なっていなかった点、子どもの感覚器を存分に刺激させるための環境を与えていなかったこと。というかそもそもしっかりと向き合う時間を十分に確保して...
幼児期の教育に焦点を当てて書かれている本で、読み終わってすぐに妻にも勧めた。反省すべき点としては、子どもの自主性を重んじる声かけを意識して行なっていなかった点、子どもの感覚器を存分に刺激させるための環境を与えていなかったこと。というかそもそもしっかりと向き合う時間を十分に確保していない。選ばせる、認める、共有する、疑問をもつ、目を見る。大切な我が子のために、もっと勉強するのではなく、もっと一緒にいる時間をつくることの方が大切なんだなあ。
Posted by
原宿にあるモンテソーリ子どもの家の教育について述べられている。体験を通しながら自立の基礎を養う。子どもが自分でするようになるために大人が環境を用意してあげる事が大切である。
Posted by
モンテッソーリについては2冊目。実際の園での教育の様子がわかる。日本でもより多くのところで、モンテッソーリメソッドを取り入れてほしいものだ。
Posted by