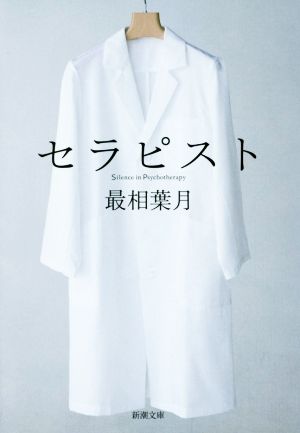セラピスト の商品レビュー
箱庭療法を主なテーマに、現代人の心の病について語られるドキュメンタリー。 箱庭療法パートや精神医学の歴史は読むのが苦痛のレベルで退屈な時もあるが、第八章「悩めない病」と九章「回復のかなしみ」が秀逸で、読んでいてはっとした。 心理関係に興味がある人にはお薦め。
Posted by
セラピストが相手にするクライエントの傾向(トレンドと呼んでいいものか分からないが)は、時代によって変化する。確かに、子供の頃に読んだ『こころの処方箋』には違和感を覚えたことを思い出した。 著者本人もセラピストのお世話になっているからこその視点が含まれているのもこの本の魅力だと思...
セラピストが相手にするクライエントの傾向(トレンドと呼んでいいものか分からないが)は、時代によって変化する。確かに、子供の頃に読んだ『こころの処方箋』には違和感を覚えたことを思い出した。 著者本人もセラピストのお世話になっているからこその視点が含まれているのもこの本の魅力だと思う。偏りなく、一人一人と向き合うセラピストに対しても、丁寧に一人一人を見つめる姿勢が安心感の信頼感を高めているように思う。 文庫版にのみ収録されているあとがきが、最も心があたたまる穏やかな光を感じるものだった。
Posted by
「胎児のはなし」で著者の本を面白いと感じ、他のものも読んでみたいと、借りた本。 自身がカール・ロジャーズの来談者中心療法を学び、カウンセラーの真似事をしているため、まず読むならば、これだな。と思った。 読む中で、知るのは、心理療法の歴史。 そして、芸術療法と呼ばれるものたちの歴...
「胎児のはなし」で著者の本を面白いと感じ、他のものも読んでみたいと、借りた本。 自身がカール・ロジャーズの来談者中心療法を学び、カウンセラーの真似事をしているため、まず読むならば、これだな。と思った。 読む中で、知るのは、心理療法の歴史。 そして、芸術療法と呼ばれるものたちの歴史。 特に、自身が一番好きだと思っている箱庭療法と風景構成法がかなりの分量で記されていることに、ワクワクしながら読み進めた。 また、河合隼雄先生はじめ、多くの人たちのセラピストとしてのクライアントに対する関わり方、考え方も多く書かれているので、とても勉強になったと共に、カウンセラーというものの重たさを感じざるを得なかった。 箱庭療法が何故良いのか? 「言葉だけでは表現できないものがあった場合、言葉にしてしまうことで削ぎ落とされてしまう。言葉にできないもののほうが大事かもしれないのに、言葉になったことだけが注目されて、あとは置き去りにされてしまう」(48頁) この言葉で、ストンと落ちた。 そう、言葉がない分、あの箱の中に自分というものを表現しやすいのだと。 カウンセラーは、自分を知らなければならない。 それは、ずっと言われてきたことであるが、この本にもちょくちょくその言葉がでてきた。 そう、知らなくてはできないことなのだ。 でも、自分を知るというのは、苦しいことでもあり、とても難しい。 本の評価を☆5としたいところだったが、1落としている理由。 それは、一度読んだきりでは、理解しづらいものがあり、もっと深く読まなければな。と思ったから。 単に、セラピストというものがなんなのか?を知りたいだけなら一度で良いかもしれないが、登場されている数々のセラピストたちの姿勢、目指すものをしっかりと読むのであれば、一度では無理だなと思ったから。 まずは、図書館にこれを返して、本屋で購入してこようかな。 赤線、青線、色とりどりに線を引いて読み直したい。
Posted by
セラピスト木村晴子の仕事から、河合隼雄、中井久夫とたどる、最相自身の自己発見のプロセス。精神科医療の入門的「売れんかな」本でないことが本書の命。 なんといっても、精神科医中井久夫の仕事に対する誠実な記述が好印象の好著。
Posted by
仕事で、「心の病」のある人、あるいはその家族と話すことがある。 現状、苦しんでいる人がどのように悩み、もがき、治療を受けているのかはわからない。 私たちは、ただ、淡々と、その事実を記録して、案件の処理をするだけだからだ。 だから、各々に対して思い入れはしない。 けれども、たまたま...
仕事で、「心の病」のある人、あるいはその家族と話すことがある。 現状、苦しんでいる人がどのように悩み、もがき、治療を受けているのかはわからない。 私たちは、ただ、淡々と、その事実を記録して、案件の処理をするだけだからだ。 だから、各々に対して思い入れはしない。 けれども、たまたま私は治療をするほど追い詰められなかったけれど、かつて自傷したこともあるし、何度も自殺する方法について考えたこともある。 本が私を助けてくれたから、自力で立ち直ることができたが、それはあくまで私の体験であり、すべての人に有効な方法でもないし、共通する経験でもない。 だから、私は苦しむ人々がどんな治療を受け、どう関わりを持っているのか知りたいと思った。 心理療法士、精神科医はどんな思いで、相手と関わっているのだろう? 424〜425頁で女性患者がこう言った。 「この前箱庭を作ったとき、先生はこれで治せると思ったでしょう」 「私は別に治してほしくないのです。私はここに治してもらうために来ているのではありません」。 一瞬何を言っているのかわからなかったし、患者特有の意固地さなのかと思った。 しかし、「治さねばならぬ」という思いは、一体誰のためなのかを考えたとき、自分の子供を思った。 普通級ではなく、支援学級を勧められた時、教育委員会は、何のために、誰のために支援級と判定したのか、その時の怒りに似た感情を思い出したのだ。 「普通」とは何だ、誰のための「普通」なのか。 実際はそんな悠長なことを言っていられないかもしれない。 自傷や他害を起こさせないことは必要なことだし、実際に苦しんでいて治したいと思う患者も多いだろう。 だが、違うことは悪いこと、同じでなければ価値がないというのは、優生思想ではないか。 かつて、人類が何度も犯してきた過ちと同じことをまた、繰り返すのか。 なぜ生き物がこれだけ多様性を持ち、変異を起こしてきたか、私たちに足りないものは、そのゆとりなのだ。 人が人らしく生きるには遊びが必要だ。 心とは、多様性とは、生きるとは。 本書が問いかけるものは、広く、果てしない。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
■逐語録(上) 第一章 少年と箱庭 第二章 カウンセラーをつくる 第三章 日本人をカウンセリングせよ 第四章 「私」の箱庭 第五章 ボーン・セラピスト ■逐語録(中) 第六章 砂と画用紙 第七章 黒船の到来 ■逐語録(下) 第八章 悩めない病 第九章 回復のかなしみ あとがき 文庫版特別書き下ろし 回復の先に道をつくる 参考・引用聞文献
Posted by
心の問題にアプローチする場所。 そこでどんなことが行われるのか、克明に描かれる。 待つことが大きな要素だが、忙しい今日の社会はそれを許さなくなってきている。 治療の開発者たちは、一人一人の個別性に付き合い、長く待つ。
Posted by
昨年買って読んでは諦め、読んでは諦めを繰り返した一冊が読み終わった。 逐語録とか絵とか箱庭とか淡々と書いてたりストーリー性というよりもより正確に書いてあるという感じで時間がかかってしまった。 本全体としては回復の過程のストーリーになってると思うのだが、1年以上かけて読んだためそう...
昨年買って読んでは諦め、読んでは諦めを繰り返した一冊が読み終わった。 逐語録とか絵とか箱庭とか淡々と書いてたりストーリー性というよりもより正確に書いてあるという感じで時間がかかってしまった。 本全体としては回復の過程のストーリーになってると思うのだが、1年以上かけて読んだためそう感じただけかと、、、 かなり読み応えのある一冊。 心理系の勉強をしてる方にはいのかも?
Posted by
私も15歳のときに読んだ「絶対音感」でノンフィクションの世界に華々しくデビューした著者の現時点での最新作となる本作は、<心の病>をテーマに、精神医学や心理学などがどのように発展してきて、どう人々の心を癒すのかについて書かれたルポルタージュである。 本書では、著者自らが両親の介護...
私も15歳のときに読んだ「絶対音感」でノンフィクションの世界に華々しくデビューした著者の現時点での最新作となる本作は、<心の病>をテーマに、精神医学や心理学などがどのように発展してきて、どう人々の心を癒すのかについて書かれたルポルタージュである。 本書では、著者自らが両親の介護と死去に際して、自身も心の病を抱えていることを自覚しながら、自らも箱庭療法や絵画療法などを受けることで、深く治療の実態に迫っていく様子は強い説得力がある。5年間にも及ぶ取材と自らの治療を踏まえて書かれた本作は、そうした生々しい実態がわかりやすく描かれているともに、かつての治療では患者が喋りたくなければ10分間でも沈黙を続けられるような鷹揚な雰囲気があったが、近年の患者数の増大とそれに追いついていない医師・セラピストの人員数により、そうした治療が今や望めない等の問題提起がなされる。 個人的に強く関心を持ったのは、独自の絵画療法である風景構成法を生み出した精神科医の大家、中井久夫へのインタビューの中で、言語を操ることで、必然的に因果関係を作ってしまうという人間の根源的欲求について触れている点であった。 「言語は因果関係からなかなか抜け出せないのですね。因果関係を作ってしまうのはフィクションであり、治療を誤らせ、停滞させる、膠着させると考えられても当然だと思います。河合隼雄先生と交わした会話で、いい治療的会話の中に、脱因果的志向という条件を挙げたら多いに賛成していただけた。つまり因果論を表に出すな」ということです」(p366~367)
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
「心の病はどのように治るのか」がテーマのノンフィクション。 河合隼雄さんも、中井久夫さんも『待つ』ことが大事なのだと教えてくれた。 『傾聴』って言葉が今言われてるけど、お二人は大分前からそれを実践してらしたんだ、と思った。 ちょっと私には難しかったけど、とても興味深く読めた。
Posted by