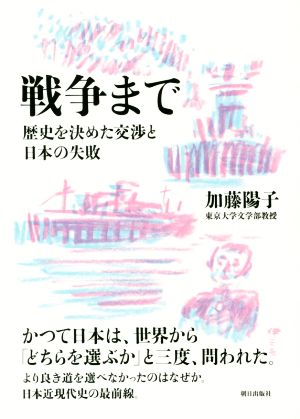戦争まで の商品レビュー
戦争における分岐点となった3つの出来事(リットン報告書、三国軍事同盟、日米交渉)を、中高生とのやり取りをしながらみんなで考えていくといったスタイルの一冊。 ページ数は決して少なくないが、著者のわかりやすい語り口や所々にある写真や図表などで理解が助けられる。戦争関連本にしてはかなり...
戦争における分岐点となった3つの出来事(リットン報告書、三国軍事同盟、日米交渉)を、中高生とのやり取りをしながらみんなで考えていくといったスタイルの一冊。 ページ数は決して少なくないが、著者のわかりやすい語り口や所々にある写真や図表などで理解が助けられる。戦争関連本にしてはかなりわかりやすい部類に入ると思う。 戦後も70年以上を経過しているが、当時の出来事が必ずしも正確な形で後世の記憶や「歴史」に残されているとは限らない。実は日米も歩み寄ろうとしていたし、日本の中にも冷静な人はいたし、陸海のパワーバランス(見栄みたいなものも?)もあった。なんとなく「こうだろう」と思っていることが、実はちょっと違ったりもする。今回採り上げた3つの出来事は、そういう側面を持っている。 戦争は大きな一つのうねりではなく、様々な様子が少しずつ影響しあって、いわばピタゴラスイッチみたいに最後に戦争になったと分かる。ただ、それをどうやって今後の時代に防いでいくのか。戦争の内実がわかってくればくるほど、それを防ぐ難しさも分かる。でも、それは現代人が不可避的に立ち向かわなければいけないことだから、やはりこういった本はちゃんと読んでおくべきなんだろうな、と思った。
Posted by
前作「それでも日本人は戦争を選んだ」に感銘を受けて読んだ。 真珠湾の「ローズベルト陰謀論」の全面否定は、意外だったが、説得力のある内容だったので、自分の認識を改めた。 教育の影響は勿論甚大なのだろうが、泥沼の日中戦や勝てる見込みの無い日米戦に民意諸共嵌り込んだ根本原因は、「10万...
前作「それでも日本人は戦争を選んだ」に感銘を受けて読んだ。 真珠湾の「ローズベルト陰謀論」の全面否定は、意外だったが、説得力のある内容だったので、自分の認識を改めた。 教育の影響は勿論甚大なのだろうが、泥沼の日中戦や勝てる見込みの無い日米戦に民意諸共嵌り込んだ根本原因は、「10万人の英霊と20億円の戦費を投入した日露戦の成果を手放したく無い」という、既得権への執着に行き着くのだろうなと感じた。(行動経済学的視点から) そうであれば、こうしたベストでない選択をするリスクは、日本人固有のものというより、人間のDNAレベルのものだろうから、余程意識的でないと、再現するリスクがありそうだ。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
非常にわかり易く解説された講義です。 歴史から学ぶというけれど、結果を知っているからこそ振り返る事ができ、その選択肢の評価ができる。 時の為政者たちは本当にいろいろ考えを巡らせていることがわかるが、総意としての選択肢は一つ。 今回、失敗と言ってしまっているが、そう言っていいのだろうか。確かに沢山の人が亡くなったわけだけど、その選択肢の結果である今の日本は失敗なのか。 過去を総括するのもいいけど、歴史に学ぶのは未来に対してだけでいい。 少なくとも、今の為政者たちが、半径3mの幸せを考えている群衆へのプロパガンダやアジテーションの方法を歴史から学ぶことがないことを望む。
Posted by
かつて日本は世界からどちらを選ぶかと三度問われた。そして愚者の道へ道へとそれていってしまった。それはなぜか?その背景などがわかる。とても面白い日本の近現代史であった。
Posted by
面白いし、分かりやすい。聴講している高校生達は本当に賢いと思うし、高校生とは思えないほど。私も歴史を勉強して、思考に深みを持たせたい。
Posted by
日本が歴史上戦争で負けたのは2回だけ。と、昭和天皇が白村江で負けた天武天皇に習おうとしたのは、天皇制の深遠さを感じさせるエピソード。全体的には「交渉とは何か?」「認識とは何か?」について教訓的な所があり、考えさせられた。ただし、史料を都合よく引用し、主観的に解釈していると思える部...
日本が歴史上戦争で負けたのは2回だけ。と、昭和天皇が白村江で負けた天武天皇に習おうとしたのは、天皇制の深遠さを感じさせるエピソード。全体的には「交渉とは何か?」「認識とは何か?」について教訓的な所があり、考えさせられた。ただし、史料を都合よく引用し、主観的に解釈していると思える部分もある。が、歴史学はそういう事から逃れる事はできないので仕方ない。また、肝心の南部仏印進駐と全面禁輸のところが、想像とか仮説に留まっており、解明されていない点が残念。また、日独伊+中提携の汪兆銘政権承認の方針転換所も原因がよくわからないので説明が欲しかった。あと、犬養は満州国を承認しないから殺されたとあるが、満州国は犬養内閣の国策(閣議決定もしている)なわけで、承認しないという事はありえないと思うのだが。
Posted by
●→本文引用 ●次に、日本と戦っていた中国が、三国同盟をどう見ていたかをお話ししましょう。(略)1940年8月4日の蒋介石日記を読んでみましょう。(略)日本が南下したい、石油を取りたいと思っているときに乗じて、中国に有利な条件を日本が出すなら、それで講和するのは悪くない、と述べ...
●→本文引用 ●次に、日本と戦っていた中国が、三国同盟をどう見ていたかをお話ししましょう。(略)1940年8月4日の蒋介石日記を読んでみましょう。(略)日本が南下したい、石油を取りたいと思っているときに乗じて、中国に有利な条件を日本が出すなら、それで講和するのは悪くない、と述べています。(略)これは当時、部内で「桐工作」と呼ばれた和平工作の一つです。講和案のの内容が蒋介石まで届けられていましたし、昭和天皇もその成否を非常に気にかけていました。(略)蒋介石のもとで作戦を指揮していた軍令部長の徐永昌が、9月29日に蒋介石にこう提言していました。(略)日本軍と中国国民党軍双方が死力を尽くして戦えば、漁夫の利をしめるのは共産党だ、こういって蒋に停戦を薦めます。 ●確かに日本軍が、中国軍を戦闘という面で圧倒していたのは事実です。1944年、戦争が終わりに近づく頃、日本軍の兵隊は、中国大陸の海岸線を千キロ以上も行軍して、アメリカ軍が使いそうな中国側の飛行場をすべて潰してまわります。これを大陸打通作戦というのですが、この作戦によって、中国側が蒙った地域社会の変化や国家の仕組みの変化が、非常に大きかったということが最近の研究でわかっています。端的に言えば、蒋介石の国民政府軍が、この日本軍の作戦によって疲弊させられ、戦後の共産軍との内戦において不利になったということです。 ●総体として見ると、アメリカは1941年4月段階にも、資源を共有しませんか、船舶を貸与してくれませんか、資金援助してあげますよ、と日本に呼び掛けていた。一緒に共産主義に対抗していきませんか、中国との戦争をやめませんかといって、「世界の道」を、日米諒解案として示していました。 →後付けの知恵を承知で言えば、結局のところ、日本は大局、日中戦、欧州の第二次世界大戦後の世界情勢、自由主義対共産主義を見据えていなかったのだろう。「ラストバタリオン-蒋介石と日本軍人たち」でも指摘されていたが、日中戦争を対共産主義で国民党政府と停戦していれば、アメリカと戦うことも無かっただろう。
Posted by
中高校生向けの講演を整理した本で分かりやすい。気付かない歴史の裏側を、資料に基づいて新しい視線で示してくれる。よい本だが、図書館から借りて(第2章の満州事変まで)返却日が来てしまった。また読みたい。
Posted by
第二次世界大戦、太平洋戦争を冷静に振り返る本。右左でいえば左ということになるだろう。最近は右寄りの歴史修正主義の本が多い気がするので、そういった本を読む前、読んだ後に加藤陽子さんの本読むことは、極端な結論になるのを防ぐ意味で役立つと思う。一次資料に基づいた考えが多いので、その点で...
第二次世界大戦、太平洋戦争を冷静に振り返る本。右左でいえば左ということになるだろう。最近は右寄りの歴史修正主義の本が多い気がするので、そういった本を読む前、読んだ後に加藤陽子さんの本読むことは、極端な結論になるのを防ぐ意味で役立つと思う。一次資料に基づいた考えが多いので、その点で信頼性が高い。
Posted by
国際連盟脱退、日独伊三国同盟、日米交渉と3つの選択を謝った日本が第二次大戦の敗北という憂き目に遭うまでの歴史を丹念におった良書。決して日本は米国に嵌められたから戦争を行った訳でなく、自身の選択ミスもあった訳だ。 しかし、民衆に真実が伝わっていなかったから、選択を誤ったという説も...
国際連盟脱退、日独伊三国同盟、日米交渉と3つの選択を謝った日本が第二次大戦の敗北という憂き目に遭うまでの歴史を丹念におった良書。決して日本は米国に嵌められたから戦争を行った訳でなく、自身の選択ミスもあった訳だ。 しかし、民衆に真実が伝わっていなかったから、選択を誤ったという説もあるが、民衆に質実を伝えるのは難しいのと違いますか? 佐藤優の『国家の罠』でも、「この国=日本の識字率は5%以下だからね。新聞に一片の真実が出ているもそれを読むのは5%。残り95%の世論はワイドショーと週刊誌によって形成されるのだ」とあったではないか、逆に言うと真実は民衆に分かり難いようにし、マスコミを使い世論誘導していかないと政治が成り立たないとも言えるのでは?
Posted by