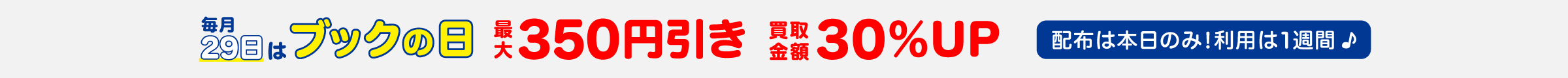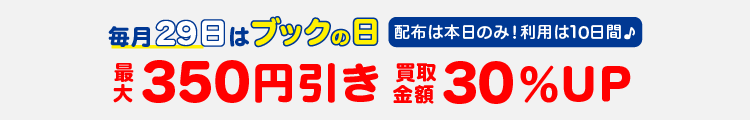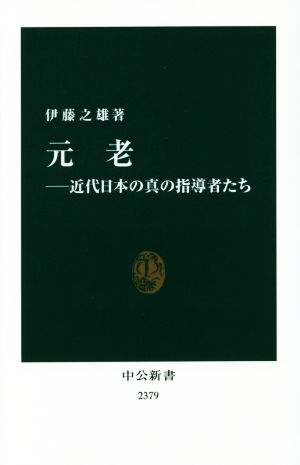元老 の商品レビュー
歴史の教科書では「護憲運動を阻害した老害」とのイメージしかわかないインフォーマルな集団「元老」についての解説本。明治~昭和初期において政界に影響力を及ぼしたこの集団について細かい注釈を加えながら丁寧に説明している。 この本で特に惹かれるのは元老内での人間模様を細かく描写して...
歴史の教科書では「護憲運動を阻害した老害」とのイメージしかわかないインフォーマルな集団「元老」についての解説本。明治~昭和初期において政界に影響力を及ぼしたこの集団について細かい注釈を加えながら丁寧に説明している。 この本で特に惹かれるのは元老内での人間模様を細かく描写していることだろう。一般的には元老というと大正期の「護憲運動の敵」としての山県有朋、もしくは昭和初期の「首班指名のご意見番」としての西園寺公望のイメージしかないだろう。しかしこの本では元老の形成過程での伊藤博文・山県・黒田清隆の権力争いや明治天皇の政治的志向、大正期の桂太郎・大隈重信と元老の一部との対立、昭和期に入ってなぜ西園寺が元老を補充せず終焉に導いたかなど、元老を取り巻く人間関係はさながら大河ドラマを見ているようで面白い。 更には元老が必ずしも世間から「絶対悪」とはみなされていなかったことも興味深い。当時の新聞には必要悪として存続を認めるばかりでなく、元老の指導力の発揮すら求めた時期がある。また平民宰相と名高い原敬も山県との連携を密に保ち、山県が宮中某重大事件で窮地に追い込まれた時には助け舟を出すなど、世間や時の政権が受容する立場にあったこともあるという点は新しい視点だった。 理想を言えば一部の人間に権力が集中しない完全な民主主義こそが理想なのだろう。しかし世の中は(この現代であっても)そう理想論通りにはいかない。その中でどのような体制が国家を維持するための最適解なのか。この本は元老という制度を通してこの時代が出した「解」を教えてくれたように感じた。
Posted by
元老と呼ばれる戦前日本の政治指導者たちを肯定的に捉え直した一冊 要は、彼らは明治維新を経て近代立憲制を日本に定着させてゆく黎明期において、大日本帝国憲法のシステム運用上の機能不全を回避すべくインフォーマルに立ち回り、政党内閣誕生で結実する立憲国家への道を舗装していったという。 ...
元老と呼ばれる戦前日本の政治指導者たちを肯定的に捉え直した一冊 要は、彼らは明治維新を経て近代立憲制を日本に定着させてゆく黎明期において、大日本帝国憲法のシステム運用上の機能不全を回避すべくインフォーマルに立ち回り、政党内閣誕生で結実する立憲国家への道を舗装していったという。 具体的には、総選挙で民党が影響力を持つ過程で政党政治を求める世論の高まりを理解しつつも、政権運営能力のない政党に国家運営を任せることの懸念から、政党側に実務運営ノウハウをゆっくりと身につけさせる「自転車の補助輪」の役割を果たした。(例えば、第1次大隈内閣、立憲政友会の創設等) 確かに上からの改革でしかないという批判も当たるが、当時の日本を取り巻く国際状況や国内状況を踏まえると、形式上の制度が機能するまでの間は中長期的ビジョンを持った非公式のエリートが微調整をする必要性があったのかもしれない。
Posted by
愛国だけでなく国際感覚を持っていた元老たち。 異なる藩からの集まりでよくまとまった。今の日本とは大きな違い。 庶民よりも裕福な暮らしであったが、今の独裁者たちと比べれば質素。それが明治天皇の言葉からというのも面白い。
Posted by
それぞれの元老の紹介や制度の変遷(主に首相推薦)について丹念に追った本です。研究である著者の説を分かりやすく一般向けに書いたイメージです。ところどころに別の学説への批判など、専門書向けの書き方も入っており、専門書を読んだことがない人が読むと少し違和感を覚えるかもしれません。
Posted by
元老。天皇の最高顧問。日本の国際協調と民主化・近代化を安定して進めていくことに寄与した。1889~1940。 黒田清隆・伊藤博文・山県有朋・松方正義・井上馨・西郷従道・大山巌 桂太郎・西園寺公望
Posted by
現代の私たちは間接的であっても首相が選挙によって選ばれることが当たり前と思っているが、必ずしもそれが最善ではないこともあるということ。日本の近代化が成功したのは政党政治の統治能力を疑い、私心なき公共心で長期的視点から国家建設を行った元老の功績が大きかった。 近年密室政治は批判され...
現代の私たちは間接的であっても首相が選挙によって選ばれることが当たり前と思っているが、必ずしもそれが最善ではないこともあるということ。日本の近代化が成功したのは政党政治の統治能力を疑い、私心なき公共心で長期的視点から国家建設を行った元老の功績が大きかった。 近年密室政治は批判されるが、元老制はその最たるものであるがゆえに首相推薦の正当性を保持するための政治的努力は並々ならぬものがある。天皇や元老が開戦を止められなかったのかという後世の批判は皮相的で、無理に行えば権威を失墜して一層開戦を速めたであろう。 他の学者を批判するような箇所がいくつかあり、客観性を損ねている。伊藤博文への傾倒も強く感じられ伊藤の評価はほかの文献にもあたってみる必要がある。
Posted by
元老制度を通して、明治〜昭和初期の日本を描く。 制度と書いたけど、元老には法律的に何の根拠もない。にもかかわらず、後継首相を推薦し、国の政策判断に寄与してきた。およそ民主的ではなかった。山県が政党内閣を支持しなかったのは、選挙のために腐敗・汚職がまかり通るからだし、国よりも選挙を...
元老制度を通して、明治〜昭和初期の日本を描く。 制度と書いたけど、元老には法律的に何の根拠もない。にもかかわらず、後継首相を推薦し、国の政策判断に寄与してきた。およそ民主的ではなかった。山県が政党内閣を支持しなかったのは、選挙のために腐敗・汚職がまかり通るからだし、国よりも選挙を優先に考えるからだ。山県が指摘する政党内閣の危険性は、現代もまったく変わらない。でも、もう元老はいないし二度と現れない。政治的には不幸な時代だ。
Posted by
元老について辿るとそのまま日本の近代史になるんだな。元老というものに殊更興味がなかったとしても明治維新後にどのように日本の政治制度が整えられていったのかがよくわかるし、原敬なんかの政治手腕も凄いもんがあるなと改めて勉強になることが多かった。西園寺と昭和天皇と陸軍や右翼との政治的バ...
元老について辿るとそのまま日本の近代史になるんだな。元老というものに殊更興味がなかったとしても明治維新後にどのように日本の政治制度が整えられていったのかがよくわかるし、原敬なんかの政治手腕も凄いもんがあるなと改めて勉強になることが多かった。西園寺と昭和天皇と陸軍や右翼との政治的バトルのところは、著者の熱意も伝わってきて、それぞれの想いを考えたときになんだか胸が熱くなってしまった。
Posted by
元老が近代日本の外交、内政にどのような役割を果たしたのか、天皇との関係、そもそも元老とはどのような制度で誰が作り変えていったのか、制度の正当性はどのように確保されたのか、そして最後に一人元老となった西園寺死後、誰が首相を決めていったのか、について詳細かつ、わかりやすく解説している...
元老が近代日本の外交、内政にどのような役割を果たしたのか、天皇との関係、そもそも元老とはどのような制度で誰が作り変えていったのか、制度の正当性はどのように確保されたのか、そして最後に一人元老となった西園寺死後、誰が首相を決めていったのか、について詳細かつ、わかりやすく解説している。 日本のような後進国がいきなり議会制度を機能させることは難しく、その意味で元老というインフォーマルな制度が日本の民主制度発展にもった積極的な役割をもっと評価すべきであるという主張には大いに首肯できる。 ところで、「あとがき」で慶應義塾大学の八代先生のお名前が登場してきて、ちょっとびっくり。私も2003年の在外研究時にはお世話になったので。著者の伊藤先生も2015年のオックスフォード滞在時にお世話になったのだとか。
Posted by
本書は実に興味深い本である。 明治において我が国は、西欧の科学技術のみならず政治システムを大胆に導入した。異文化の土壌に「立憲体制」を移植し機能させるために我が国の支配エリートが作り上げたものが「インフォーマルな元老」であったというのが本書の考察である。 しかし、日本の歴史は「立...
本書は実に興味深い本である。 明治において我が国は、西欧の科学技術のみならず政治システムを大胆に導入した。異文化の土壌に「立憲体制」を移植し機能させるために我が国の支配エリートが作り上げたものが「インフォーマルな元老」であったというのが本書の考察である。 しかし、日本の歴史は「立憲体制」を補完する「元老政治」が明治大正には機能したものの、昭和には破綻し「軍部独裁体制」に変質してしまったことをも教えている。 「元老政治」が最終的な目標としたものが本書で主張するように「政権交代可能な二大政党政治」であり、日本の昭和戦前期までの経過がそれが失敗した歴史であるとするならば、2012年の民主党政権の崩壊はもっと長い文脈でみる必要があるとも思えてくる。 すなわち、日本においては明治期に導入された「立憲体制」は未だに咀嚼されていないのではないのかという疑問である。 本書は読者にそのような想像の翼を広げさせてくれる良書であると思えた。
Posted by
- 1
- 2