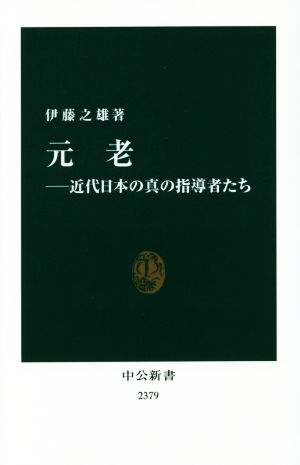元老 の商品レビュー
日本史選択であれば覚えているであろう戦前の「元老」。おそらく、主に一線を退いた政治家が裏で首相選定など重大な政務を牛耳ったというイメージが強いように思われる。(というか僕がそう)しかし、この本は元老の仕事をより広くとらえ、かつ元老の影響を重視することで、イメージの刷新を狙うもので...
日本史選択であれば覚えているであろう戦前の「元老」。おそらく、主に一線を退いた政治家が裏で首相選定など重大な政務を牛耳ったというイメージが強いように思われる。(というか僕がそう)しかし、この本は元老の仕事をより広くとらえ、かつ元老の影響を重視することで、イメージの刷新を狙うものである。まず、こう指摘される。 「近年まで、「元老」の用語を、藩閥有力政治家で第一線を退いても政治的影響力を及ぼす人々、と第一線を退くというニュアンスを込めて高校日本史教科書でも説明するのが普通であった。これは、元老とは「黒幕」という現代イメージを、歴史上の慣例的制度に遡らせて理解しようとしたものであり、ようやく修正された。」p71 ここから、一般のイメージより大きな役割を果たした元老の実像が主要な政治史的事件に沿って展開される。そして、こうまとめる。 「元老は、後継首相推薦やその他の重要問題で天皇を補佐することで、日本の国際協調と民主化・近代化を安定して進めていくことに、全体として寄与したと言える。…世界や東アジアの流れに対する長期的なヴィジョンを持った元老が、後継首相推薦などを通して外交・内政の調整と方向づけを行った。」p298 本書は新書にしては珍しい、「他研究者への当てつけ」の側面を持った本である。学会で論争を繰り広げるのではなく、成果を直接一般市民に問うという変化球である。また、豊富に一次資料を引用することで、他説への批判も行う。単なる自説の開陳や事例の解説に止まらないという意味で、日本史学の豊穣な世界を覗かせてくれる、中公新書きっての歴史書になり得る一冊である。
Posted by
京都大学大学院法学研究科教授(日本政治外交史)の伊藤之雄(1952-)による、近代日本における元老制度の概説。 【構成】 序章 元老とは何か 第1章 明治維新後のリーダー選定 第2章 憲法制定と元老制度形成 第3章 日清戦争後の定着 第4章 元老と東アジアの秩序・近代化 第5章...
京都大学大学院法学研究科教授(日本政治外交史)の伊藤之雄(1952-)による、近代日本における元老制度の概説。 【構成】 序章 元老とは何か 第1章 明治維新後のリーダー選定 第2章 憲法制定と元老制度形成 第3章 日清戦争後の定着 第4章 元老と東アジアの秩序・近代化 第5章 政党の台頭による制度の動揺 第6章 第一次護憲運動による危機 第7章 元老制度存廃の戦い 第8章 原内閣下の首相権力拡大 第9章 危機をどう乗り越えるか 第10章 新しい首相推薦様式 第11章 昭和天皇の若さと理想 第12章 満州事変後の軍部台頭の時代 第13章 二・二六事件と元老権力 第14章 太平洋戦争は避けられないか 終章 元老制度と近代日本 本書で紹介されるのは近代日本において、帝国憲法には全く記されていないが、しかし明確に政治上の重要事項に関わり続けた「元老」と呼ばれる立場の人々である。 著者が元老とみなしているのは、伊藤博文、山県有朋、黒田清隆、松方正義、井上馨、西郷従道、大山巌、西園寺公望の8名である。このほかに、元老として天皇を補佐するよう「元勲優遇」の勅語を受けた桂太郎、それに準ずる沙汰書を受けた大隈重信が挙げられる。また、元老になる可能性はあったが、死亡によりそれがかなわなかった原敬、加藤高明は候補者と言える。 内閣制度・帝国憲法の運用が確立した1890年代半ばは、初期議会・日清戦争を経て、伊藤、山県、黒田、松方が少なくとも1度は内閣総理大臣として組閣した経験を持った。しかし、政党の台頭を受け、元勲のトップである伊藤ですら、第二次内閣退陣時に単独での後任首相の奏薦をすることができなかった。このため、明治天皇の下問を受けて、合議により次期首相の奏薦をする元老制度がスタートすることになる。 評者は本書のテーマについて、専門的な知見を持たない。 素人なりに読めば、桂太郎を元老と見なさないと明言しているところに象徴されるように、元老を他研究者よりも狭義に定義していることに伊藤の主張の第一の特徴があるように思える。 元勲優遇の詔勅を受け、元老会議に出席して、後任首相奏薦についての合議に加わった桂ですら、他の元老から正式な元老と認められていないし、桂自身の自覚も無いという理由で、退けている。松方、西園寺から元老入りを反対された大隈も然り。 一方で、加藤孝明の元老入りの可能性については、ごく主観的な評価を下している。外相時の加藤高明に辛い評価をつけていた西園寺が、首相就任に同意した点、没後10年あまりが立った時点で「ひとかどの人物だった」と表現した点をもって「元老に推していたであろう」というのはあまり根拠のない主張のように感じる。 第二の特徴としては、元老自身が「元老という憲法外のグループの正統性」をどう担保しようとしていたのか、を軸に元老制度の推移を論じていることである。 桂園時代が終わる頃から、新聞は元老の非立憲性について、批判を展開する。そこが大隈の追い風になるわけだが、山県はこれに対抗する。その一方で、薩派の山本権兵衛を退ける一方で、政友会の原敬のリーダーシップを頼りに、元老制度の維持を図ろうとする。 山県、松方が相次いで死を迎えた後、一人元老となった西園寺は元老制度の後半を一身に引きうけ、その幕引き係となった。元老の補充をしなかったのも、いつまでも元老が首相を選定するのではなく、「憲政の常道」に代表される政党政治に基づく首相交代を目指した。一番最後に元老となり、最期まで元老であり続けた西園寺が「元老」という存在を必要悪とみなしている姿は面白い。 著者はすでに明治天皇、伊藤博文、山県有朋、原敬、西園寺公望、昭和天皇の評伝を書き上げ、近代史における宮中・府中の力学を論じてきた。本書はその仕上げとしての「元老論」である。引用される先行研究のほとんどが著者自身の著作物となっており、著者の自信、主張の強さを随所に感じる。西園寺が病床についてからの立ち位置については、説が分かれているようであり、本書の主張だけを鵜呑みにするのは避けたいが、それにしても説得力は十分にある。
Posted by
- 1
- 2